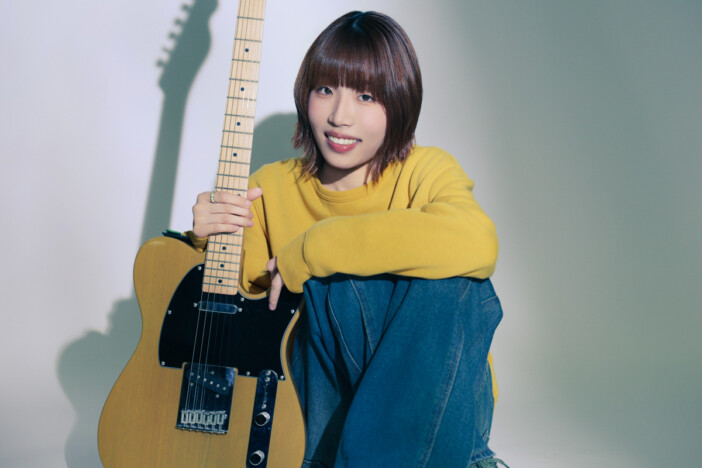今井美樹は正しい場所に、正しい時にいる アルバムリマスター配信を機に考える、新たな時代のロールモデルになるまで

right place, right time. 「正しい場所に、正しい時にいる」といった意味のこの言葉は、成功の秘訣を言い表す際に用いられる慣用句だが、これほど今井美樹の音楽キャリアに当てはまる言葉はないだろう。この度リマスター配信が成った活動初期のオリジナルアルバム6枚も、あの時、あの場所でしか生まれ得なかった珠玉の作品群だ。
オーディオ専門店を営む音楽好きの父を持つ今井は、幼少期から父が聴くジャズやボサノバ、ブルースやソウルなどを耳にして育ち、バート・バカラックを始めとした最上級のポップスにも早くから慣れ親しんだ。小学校6年の時にユーミンの「あの日にかえりたい」を聴いて、「なんてかっこいい曲なんだ」と衝撃を受けたというから音楽的にとても早熟だ。荒井由実/松任谷由実の音楽に夢中になると、彼女の曲をピアノで弾きつつ口づさんだりもしたと言う。モデル、女優業で先にブレイクした今井だが、彼女がシンガーになるのは運命だったに違いない。際立った透明感を持ち、美しさ、やわらかさ、煌めきに溢れながらも、凛々しさ、たくましさも同時に感じさせる天性の魅力を備えた歌声の良さ。女優業での成功にも通じる感情表現の豊かさはもちろん、ピッチ(音程)の正確さやリズム感の良さは幼少期からの豊かな音楽体験によって育まれた人並外れたもの。今井のヴォーカルに備わる力、魅力は一朝一夕に身についたものではなく、まさに人生を通して彼女が育んできたもの。他の誰にもマネのできないものだ。
今井美樹の音楽を特徴づける大きな要因のひとつに、曲のテンポがある。テンポは、メロディや音色と同様にその曲の印象を決定づける、音楽の非常に重要な要素。今井の曲はデビュー当初からBPM80〜100ほどのものが多い。このテンポは日本だとバラードに多いが、海外だと優れたリズムがあてがわれメロウグルーヴやスロウジャムと呼ばれる曲にもアレンジされる。例えばAORの有名曲であるボビー・コールドウェルの「What You Won't Do For Love」はBPM84。バックの演奏陣はもちろん、主役の歌がうまいから遅いテンポでもグルーヴが生まれ、心地よくリスナーの耳に届く。今井の歌、曲は、まさにこれだ。
テンポはジャンル、という言い方がある。テンポを表す数値がBPM(1分間に刻む拍数)で、昭和の歌謡曲はアップテンポのものでもBPM120〜140ほどだったが、令和のJ-POPは150〜170ほどとかなり速いテンポのヒット曲が多い。ロックやヒップホップにもそれぞれ好まれるテンポがあり、そのテンポの違いが音楽を分類〜ジャンルを形成する要素のひとつになる。1970年代末〜80年代はAOR(アダルト・オリエンテッド・ロック)ブームが起こり、日本の音楽シーンでもAORが流行った。けれどBPM80〜100の曲をバラードではなく、グルーヴ感のあるポップスとして歌う慣習が当時の日本にはあまりなく、AORを歌いこなせるシンガーは多くなかった。そこに現れたのが今井美樹だ。
今井は請われて制作したデモテープに、松任谷由実「青いエアメイル」、小林明子「恋におちて」などを吹き込んだという。フォーライフ・ミュージックのディレクター、松田直はそれを聴いてすぐに彼女のシンガーデビューを後押ししたそうだが、さもありなん。今井のシンガーとしてのすごさのひとつは、遅いテンポの曲で聴かせる海外のシンガーと同様のグルーヴセンスにある。「彼女とならようやく、世界標準のAORがつくれる」、松田はそう思っただろう。それほどに今井の「テンポ感」はスペシャルだ。「ふたりでスプラッシュ」(アルバム『elfin』収録)や、今のシティポップ人気を受けて近年さらに人気を高める「Boogie-Woogie Lonesome High-Heel」(アルバム『MOCHA』収録)、この2曲を聴くだけでも彼女のテンポ感の特別さがわかるだろう。
今井のシンガーとしての可能性を探るべく、さまざまなテンポ、曲調にチャレンジしていた最初の2作『femme』『elfin』。これを経てリリースされた、1988年の3rdアルバム『Bewith』と、翌年の4thアルバム『MOCHA』の2枚が「世界標準のAOR」そのままのつくりと思うが、テンポの普遍性という面で国内にこれと並ぶ作品は実はほとんどない。その時の流行りだけでも、日本だけで好まれるものでもない、世界的に普遍性を持つテンポで多くの曲が歌われていることが、今井の作品をエヴァーグリーンなものにし、幅広いリスナーを今も魅了している。
フォーライフ・ミュージック在籍時の今井美樹作品全てをプロデュースした松田直は、他にも多くのシンガーの名作を手がけた名物ディレクターだ。彼の下でシンガーとしてのキャリアを歩めたこと、しかもデビューが1986年だったことは、まさにright place, right time. 今井のシンガーとしての成功の大きな要因となった。
松田が今井作品で重用し、初期のアルバム6枚全てでメインアレンジャーを務めたのは佐藤準。1973年にはCharや金子マリらとスモーキー・メディスンを組んでいた佐藤は、洋楽を知り尽くした上で日本ならではのポップスを仕立てることが出来る、プロ意識のとても高い職業編曲家だ。佐藤は、日本流に翻訳しすぎない、AORの本質を突いた楽曲づくりを、国内最高のプレイヤーたちと実現していく。初期今井作品に参加したのは、ドラムスは青山純、山木秀夫、江口信夫、ベースは高水健司、美久月千晴、ギターは今剛、キーボードはアレンジャーでもある佐藤準と武部聡志、国吉良一と、スタジオミュージシャンのトップ中のトップばかり。このほぼほぼ限られたメンバーで構成された、まるで専属バンドのような働きをした彼らは、初期の今井作品においてシグネチャーサウンドとも呼べるものを構築。それは夫である松任谷正隆ひとりが全てをプロデュースするユーミン作品にも似たクオリティの高さと統一感を感じさせるもので、この時代のシティポップの完成形とも呼べるような傑作群の誕生に寄与した。
特に山下達郎バンドの要だった青山純のドラムスと、今井の歌の相性の良さは特筆ものだ。彼の叩く16ビートがタツロー・サウンドの核だったわけだが、ヒップホップ時代を迎えてさらに人気を上げた重〜い青山のドラムスは歌い手を選ぶ。その深いグルーヴに往々にして歌が負けてしまうからだ。ところが今井は、ジャズやソウルも聴いて育ち「後ノリ」をよく理解しているからか、青山のドラムスに実にうまく乗る。例えば「Anytime Manytimes」(アルバム『MOCHA』収録)や、「冷蔵庫のあかりで」(アルバム『Bewith』収録)を聴いてみよう。一聴して青山のものとわかる重さと、後ノリ感が特徴的なドラムスに乗る、今井のこれも特徴的なテンポ感が心地いい歌声の組み合わせの妙は、他では聴けないもの。近年のシティポップブームを経て、ふたりが生み出したケミストリーは今さらに輝きを増している。
今井美樹の作品は音が良いことでもよく知られる。ヴォーカルの置き方、低音の出し方、全体のバランスなど、録音〜ミックスの時点から国内作品の多くとは明らかに違う考えの下でつくられていたことがわかる。制作陣の念頭にあったのはやはり、当時はまだまだ先を行っていたアメリカの音楽シーンに負けないサウンドであっただろう。今井の初期6作がリリースされた80年代後半〜90年代初頭は、楽器プレイヤーたちの技量も、録音エンジニアの技術も、それまで何十年と続いてきたアナログレコーディングの術がピークを迎えていた時代だ。松田や今井が目指したサウンドを得るには、この時期がベストだった。彼女たちが求めたサウンドは、デジタルレコーディングの急速な普及によりこの後すぐ、永遠に失われてしまう。音楽業界とはままならないもので、多くはその時の流行りの音を求められる。また、好きなサウンドが今の機材ではもう出せないということもある。愛するサウンドで、愛する楽曲を奏でることは、活躍の場が広がれば広がるほど難しくなる。心から愛するAOR的な音楽を最高のメンバーと、最高のサウンドで作品にすることが出来た今井美樹は、やはり音楽の神様に愛されていると思わずにはいられない。