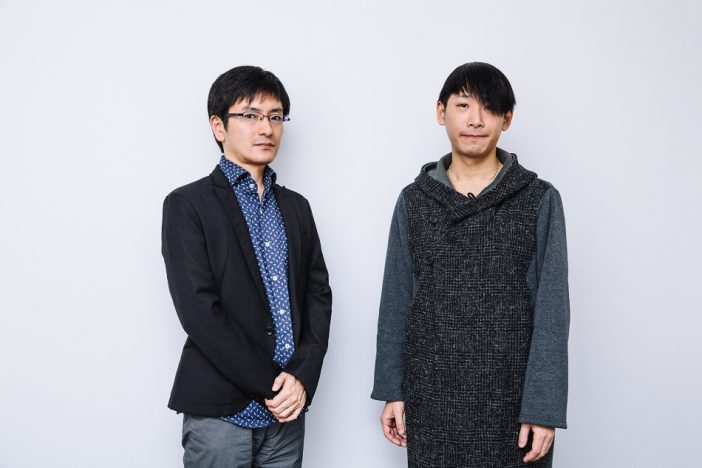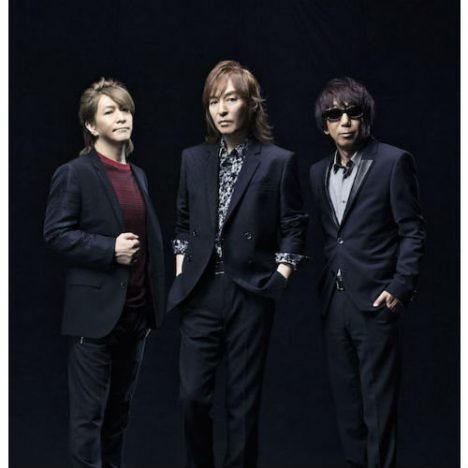クラムボン ミト、音楽家としての原体験 TM NETWORK、大江千里ら輩出したEPIC・ソニーの革新性
元を辿ると大体がEPICに着地するんじゃないか
ーー先ほど当時のEPICの音楽はシンセが印象的だったという発言がありましたが、僕も同じ印象を持っていて。あの煌びやかなシンセの音が新しい時代の音に感じたんです。
ミト:それはあるんじゃないのかなと思うんですよね……僕の知っているEPIC好きの人って結構女性率が高いんです。出自にピアノやオルガンを習っていたり、何かそういう関連性がある方が多いイメージがありましたね。大江千里さん、渡辺美里さん、TM NETWORK、松岡英明さん、岡村靖幸さんなどもどちらかと言うとシンセティックしているし、そういう傾向があったのかなと感じますね。それと歌詞の世界に“恋バナ”が多い(笑)。今回『EPIC 45 -The History Is Alive-』で、「大江千里さんで『Rain』を選ぶんだ!? 」っていうのが僕の中で少し衝撃的だったんです。後々考えてみると、今の子達は秦基博くんの『言の葉』(※2013年公開の新海誠監督作品『言の葉の庭』にて「Rain」のカバーが使用されて話題になった)のカバーで「Rain」を知るのか、なるほどねとかいろいろ考えました。
ーー1988年に千里さんがアルバム『1234』をリリースされたとき、楽器を弾く人が話題にしていたのは「『Rain』は何回転調するんだろう!?」ってことで、当時は結構実験的な楽曲というイメージだったんですよね。
ミト:僕もマッキー(槇原敬之)さんが大江千里さんをアナライズしているのを観たことがあるんですけど(※槇原敬之は1998年リリース『Listen To The Music』筆頭にたびたび「Rain」をカバーしている)、正直その時点では今のような人気曲のイメージはなかった。
ーー今になってシングルカットされたりして、いつの間にか千里さんの代表曲になったという(笑)。
ミト:僕の知らぬ存ぜぬ世界からEPICの潮流が今の若い人たちにコミットしていくっていう、これが音楽の面白いところだな……。
ーーこういうコンピレーション盤って今までも出ているので、変化をつけたかったのかなと思うところもあるんです。本来ならシャネルズの「ランナウェイ」が入るところが「街角トワイライト」だったり、それこそ一昔前なら千里さんは「十人十色」か「格好悪いふられ方」が入ったはずなんですけど……。
ミト:BARBEE BOYSの「Blue Blue Rose」に至ってはシングル『もォ やだ!』のカップリングですからね(笑)。「どうしてそこきた!?」みたいな。たしかにいまみち(ともたか)さんのギターがかっこよくて、むしろああいうギター感って今っぽい気もします。今回の45周年盤のセレクトはある種“今”というものをものすごく意識したのかもしれませんね。松BOW(松岡英明)さんだったら「『KISS KISS』をあげないんだ!?」とか、リアルタイムにいた人間からすると選曲にすごく外しがあるんですけど、それはいわゆるシティポップの再評価とか、今にコミットした流れなのかなと思いましたね。
ーー特に大胆だったのは渡辺美里さんの「My Revolution」が収録されていない(笑)。
ミト:そうなんですよ! でも「サマータイムブルース」っていう、予想しないタイミングで僕らにドンピシャな曲を出してくるんですよね。「サマータイムブルース」と言ったら「あの雨の中の西武球場しか思い出せないよ!」みたいな(笑)。突然ノスタルジーを腹の底から引っ張り出すみたいな選曲になっていて衝撃でした。編集された方はなにか相当な想いを持っているんだろうなと、深読みしてしまうレベルというか。
ーー小比類巻かほるさんも「Hold On Me」ではなくて「City Hunter~愛よ消えないで~」で、その前の「Get Wild」とともに『シティハンター』まとめになっている。
ミト:プレイリスト企画で小比類巻さんの「TOGETHER」を選んだら「サブスクにございません」と言われて。で、もっとびっくりしたのはQujilaはサブスクにあるという(笑)。
ーーTM NETWORKはYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)に代わり登場したイメージが僕にはあって、ガラリとシーンを変えたというか。このコンピ盤でいうと佐野元春さんや一風堂、シャネルズ/RATS & STAR、大沢誉志幸さんはその前のタイミングだと思うんです。やっぱりTM以後、美里さんの「My Revolution」がヒットして何かガラッと空気感が変わっていったというか。
ミト:バンドっぽくない音がめちゃくちゃ肯定された感があるのかなって。音楽を始めたり、好きになるきっかけみたいなのって、楽器とかそういうものじゃない。ビジュアルから入っていくところはアイドル文化に近いかもしれませんが、でもアイドルソングではない。そういう目新しさがあったのかもしれないです。それがある種、洋楽的に映ったのではないかと思いましたね。
ーー80年代後半の頃の日本人ミュージシャンは洋楽コンプレックスみたいなものがあって、海外ミュージシャンと同じ音を鳴らしたいと頑張っていたけどそうはならなかった。全然別のものになっているんだけど、そこがすごく面白いというのが、僕がEPICに感じていたことなんですよ。
ミト:わかります。だってどんなに松BOWさんがあの歌い方をしてもDuran Duranにはならないし、Dead or Aliveにもならない。「(Dead or Aliveの)ピート・バーンズの声とか意識しているのかな?」とか最初は思いましたけど、向き合い方がやっぱり違うんですよね。EPICには、いまだにそういう衝撃がありますよ。
ーー岡村靖幸さんや遊佐未森さんに至っては、洋楽コンプレックスがぶっ飛んじゃうくらいの個性になっていて(笑)。
ミト:岡村ちゃんの出自はいわゆるミネアポリスサウンドが好きだったんだろうなというのはわかるんですけど、遊佐さんはどうしてあそこに行き着いたのかが、世代的に僕には不思議で。歌い方は矢野顕子さんの着地が見えるんです。デビュー当時、ご本人は曲を書かれていなかったですけど、あの遊佐さんの声にいわゆるワールドミュージック的なものを入れるという発想もすごく独特だなと思いますよね。僕は遊佐さんやZABADAKを通じて、当時周りは誰も知らなかったASTURIASとかプログレ系を好んで聴いていました。そこから巡り巡って、高校の早い時期にはもうCocteau Twinsなどに辿り着いてましたからね。さらに言うと、90年代のアニソン関連は僕もいろいろと考察してきましたけど、元を辿ると大体がEPICに着地するんじゃないかと思ったり。