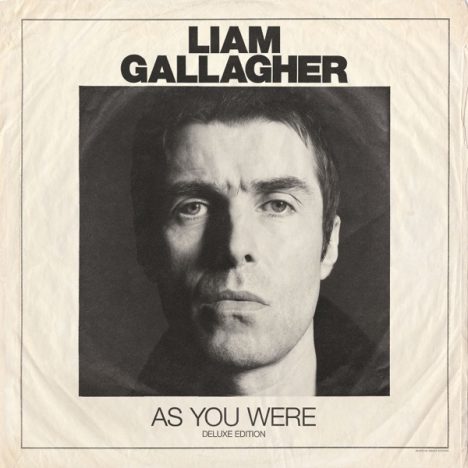『アメリカン・ユートピア』の希望を感じさせる音楽 デヴィッド・バーンが語る、選曲の物語性

デヴィッド・バーンがソロ名義では14年ぶりのオリジナルアルバム『アメリカン・ユートピア』を発表したのは2018年のこと。さらにバーンはそのアルバムをベースにしたショウを作り上げて、2019年にブロードウェイで上演した。その仕上がりを気に入ったバーンが、スパイク・リーを監督に招いて映画化した『アメリカン・ユートピア』だ。本作はバーンがトーキング・ヘッズ時代に制作したライブ映画『ストップ・メイキング・センス』(1984年)で見せたアートとエンターテインメントの融合を、さらにバージョンアップしたしたような作品だ。そこで今回、バーンにリモートインタビューをして、音楽面からショウの魅力を紐解いてみた。まず、気になったのが選曲だ。ショウではアルバム『アメリカン・ユートピア』収録曲を中心にしてトーキング・ヘッズ時代の曲も演奏しているが、バーンは選曲に物語性を感じるように構成したという。

「冒頭では一人の男、つまり僕が歌っている。世界はどんな風に動いていて、そこで自分はどう振る舞えばいいんだろうってね。そこから彼は家族や友人といったグループというつながりを見つけて、最後には社会に参加するようになる。そんな流れを作ったうえで、その時々の男のエモーションに近い曲を選んでいったんだ」
ひとつの物語に沿って歌われることによって、曲にこれまでとは違った魅力が生まれてくるのが面白い。さらに時代を超えて並べられた曲に統一感をもたらしているのが、ショウのために集められたバンドだ。バーンとは古い付き合いのマウロ・レフェスコを筆頭にして、メンバーの半数以上がパーカッション奏者で、バーンがこだわり続けてきたリズムを強調したアレンジが施されている。本作のサントラは2020年にリリースされているが、映像で見ると改めてバンドのユニークさがわかるだろう。パーカッショニストは身体にハーネスを装着して、そこに楽器を固定。ギターやキーボードにはコードをつけず、バンドは隊列を組んでステージを自由に動き回る。その姿はニューオリンズのセカンド・ラインやサンバのパレードのようだ。そういった集団のドラムサウンドの魅力について、バーンはこう語る。

「一人のドラマーが叩く音と集団で叩くドラムとではフィーリングが違う気がする。様々な人たちが力を合わせているのを見てそう思うのか、それとも、サウンドに何か秘密があるのか。その理由はわからないけれど、とにかくエキサイティングなんだ。そのサウンドをステージで捉えることができたら素晴らしいんじゃないかと思っていた」