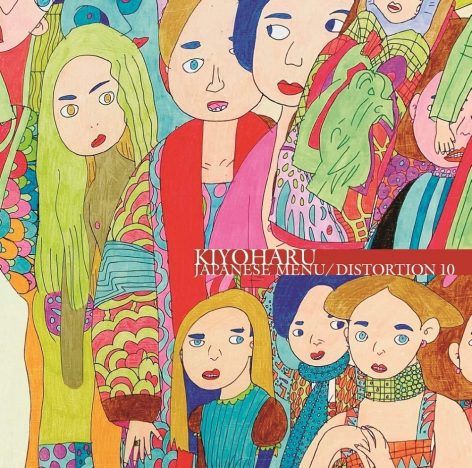清春が明かす、黒夢やソロイストとしての活動で磨き上げた美学「人間的な魅力のある、強い人だけが最終的には残る」

世の中にアピールする中で実際に重要なのは、売上枚数ではなく影響力
──黒夢のインディーズ時代について語っている章には、「売れることよりも影響力のある存在であること」や「ワンマンライブにこだわった」という言葉もありました。
清春:憧れていた人がそうだったので。テレビの中の沢田研二さんとかそういう人たちは別なんですけど、ロックという体験でいうとめちゃくちゃ売れている人にはもともと興味がないので、美学的には間違えたことをしたくないというのがありました。ただ、当時僕らがデビューした頃、90年代前半って売れないと続けられなかったというのもあって。当時のレコード会社の人達はロックバンドがオリコンチャートのベスト10に入っていくことへ果敢に取り組んでいたし、インディーズバンドがデビューして、売れたらライブハウスツアーじゃなくてホールツアーをやるとか、「ここまでいったら勝ち組ね」というのもあったし、僕らもその中で自分たちのやり方を探りながらもクリアしてかなくちゃいけないこともたくさんありました。
また、当時はフェスなんてまだ存在せず、音楽雑誌のイベントはあったものの、せいぜい多くて5、6バンドが渋谷公会堂でやるとかそういうものだったので、目標が今のバンドとは違ってワンマンしか目標じゃないと思っていた。ワンマンという美学は、やっぱり続ける上で大事でした。どこどこのフェスに出られたらうれしいとかよりも、何十年ワンマンが続けられるかというほうがミュージシャンとしても、人としても価値があるんじゃないかという価値観でしたね。
──黒夢が画期的だったのは、メジャーデビュー後に男性ファンを着実に増やしていったこと。かなり意識的に取り組んでいたそうですが?
清春:楽曲的にも外見的にも自分が憧れているものは男性に人気があったので、黒夢がどんどんソフトな方向に行ってしまうことに当時抵抗を感じていました。やっぱり、世の中にアピールしていく中で実際に重要なのは、売上枚数ではなく影響力の戦いなんです。狭い日本で何十万枚売ろうが何百万ダウンロードされようが、世界レベルで見たら架空戦争が起こっている中で夫婦喧嘩をしているようなもの。であれば、若い子たちが当時「矢沢永吉さんになりたい」「長渕剛さんになりたい」「氷室京介さんになりたい」「甲本ヒロトさんになりたい」と憧れを抱いている中で、「清春になりたい」と思われたほうがカッコいいなってシンプルに思ってました。
やっていることや音楽、生き方が本能的に同性に認められないと始まらない。それもあって、黒夢を始めた理由と違うことをやっていると悩み落ち込んだ時期もありました。『feminism』(1995年)というアルバムの時期で、メンバーがひとり辞めて2人になったとき。今は亡くなってしまった佐久間正英さんと制作に取り組んでいて、ギターがいないから、ロックっぽくなくなるんですよね。佐久間さんにはその出口を示してもらったんですけど、音楽がよりディープに、よりスウィートになっていく感じが、僕らの中ですごくありました。作品自体の完成度は高いんですけど、「これはロックか、ロックじゃないか」ということにこだわった僕と彼(人時)の差もあったと思う。
また、それ以前は音楽番組にも結構出ていたので、出続けるのか出なくなるのか、ライブ中心にやるのかチャートにこだわっていくのか、もっと有名になるつもりなのか、あるいはすごく好きな人だけに支持されるような活動をするのかというのは、何年かかけて迷いましたね。でも、当時はテレビなんか出なくても大丈夫だろうという過信もあったんですよ。
──今「過信もあった」とおっしゃいましたが、清春さんからは自信を強く持って新しいことにチャレンジしたり新しい場所に臨んでいく印象も受けます。
清春:自信というか、思ったらすぐに行動したいんですよね。それはアマチュアのときからそうだったんですけど、僕がリーダーで、メンバーがいて、手伝ってくれる人がひとりいて、カメラマンもいて。だけど、ミーティングってやったことがないんですよ。手伝ってくれる人に「これやろうよ」とかメンバーに「どう?」って僕から話し合いをしたのって、ほとんどないです。初めて本格的な話し合いをしたのはたぶん、ギターが辞めて黒夢が2人になったとき。続けていくのか解散するのか、メンバーを新しく入れるのかっていう。はっきりとは覚えていないんですけど、何カ月かはいろんなライブハウスに行ってギタリストを探して、それでいい人が見つからなくて「いいよ、2人で続けよう」というのを決めて、2人になったんだと思います。
それは僕のほうが身分が上とかじゃなくて、役割だと思っていたので。別に仲は良かったですし楽しかったですけど、メンバーの意見を聞いていると時間がかかるので、面倒くさいと思っていたんです。それに、僕も親父との約束で、デビューが決まらなければ音楽を辞めなくちゃいけなかったので、早く決めたかったというのもあった。今ではもっとスローペースですけど、当時は決めたことが3日後にできていないとすごく嫌でした(笑)。
──そのバンドを、会社に例えていたのも興味深かったです。
清春:それは親父が自営業だったというのが大きいと思います。僕、就職を一回したあとに親父を手伝っていたので、会社員のときと自分ひとりでやっているときの差とか、どうやってお金をもらっているんだろうとか、シンプルにどれぐらい月にお金を稼げるのかとか、気になるじゃないですか。それに、バンドはやっぱり団体なので、ひとつの目標を成し遂げるという意味では会社ですよね。今の子たちもみんなそうで、インディーズで自分でやっている子たちもみんな会社だと思います。