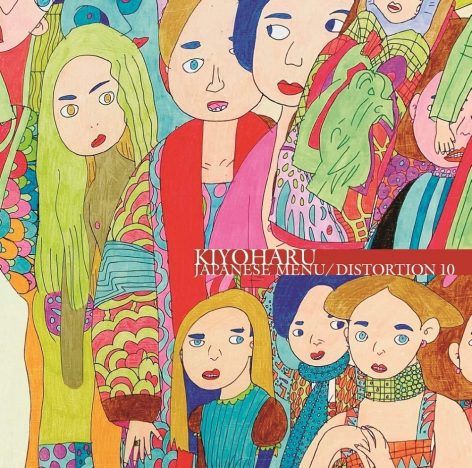清春が明かす、黒夢やソロイストとしての活動で磨き上げた美学「人間的な魅力のある、強い人だけが最終的には残る」

デビューから25年。常に強い個としての存在感を放ち、多くのロックファンの憧れの存在としてシーンに君臨してきた清春。彼が初の自叙伝を刊行した。その名も『清春自叙伝 清春』。ロックへの目覚めから黒夢やSADSといったバンド活動、ソロイストとしての自分ーー自身の半生を振り返りながら、いかにして“清春”というブランドを確立してきたのかが明らかにされていく。今回のインタビューでは本書の内容を軸に、様々な視点から清春ならではの一貫した美学に迫った。(編集部)【インタビュー最後にプレゼント情報あり】
侘び寂びっぽい曲のほうが子供の頃から好きだった
──初の自叙伝『清春』、興味深く読ませていただきました。特に90年代のお話は当時、雑誌やテレビなどでは知ることができなかった内容も多く、非常に面白かったです。今回はこの書籍の中に出てくるトピックについて、いろいろお話を聞かせていただきたいと思います。まずは憧れや理想像について。自叙伝の中には子供の頃、最初に憧れた存在として沢田研二さんや西城秀樹さんの名前が挙がっています。
清春:はい、ジュリー(沢田)や西城秀樹さんが好きだったんですね。テレビで観る範囲では圧倒的に歌のうまいスターだったし、ラジオで聴いていてもちゃんと歌として“聴けた”というのが、今思えばあります。
──確かにジュリーも西城さんもスター感が強かったですし、当時のテレビってスターしか出ちゃいけない場所でしたものね。
清春:昭和のスターは特にそうでしたよね。当時はレコードがめちゃくちゃ売れているかと言われるとそうではないし、レコード大賞とか獲っていたとしても、今の何百万ダウンロードとかの数字とはまた異なる価値基準でしょうし。でも、今では真似できない「テレビの中でのスター」感があった。あの時代に生まれて、あれを子供のときに体験した人たちというのは、どうしても本能的に憧れちゃいますよね、あれが正しい姿なのになって。特にジュリーの映像を今観ても、ファッションも全然古くないし。ジョニー・デップみたいにカッコいいですよね。
──あまり女性アイドルには惹かれなかった中、中森明菜さんの歌だけは好きだったという話が出てきます。当時、清春さんの中でどういうところが引っかかったんですか?
清春:明菜さんは歌やメロディが暗かったからかな。キョンキョン(小泉今日子)も松田聖子さんも、売れた曲は明るいですものね。明菜さんはマイナーコードの曲で売れましたし、そこじゃないですか。
──そういう、マイナー調の曲に惹かれる?
清春:侘び寂びっぽい曲のほうが子供の頃から好きだったんでしょうね。今聴くと、明菜さんの歌ってすごく上手というわけではないのかもしれないですけど、当時は女性アイドルの中では歌がうまいと思っていました。アーティスト風というか、1曲1曲髪型を変えたりとか、そういうところもジュリーっぽかったし、惹かれたのかもしれませんね。
──ジュリーにしろ明菜さんにしろ、曲ごとに世界観を作り込んで魅せるような表現にも、子供の頃から惹かれるものがあった?
清春:あったのかなあ。僕が子供の頃はまだエンターテインメントの歴史が薄かったというか、演歌があって歌謡曲があってニューミュジックがあってという中で、ロックはまだ本当に少なくて。なので、日本のエンターテインメント創世記って周りと被らないとか、マネにならないことにもこだわっていたと思うんです。だから、ジュリーのようなスターが生まれたんでしょうかね。そして、そういうものを普通に観て育ったから、それが当たり前だと思っていたのかもしれません。
──そこからロックの世界にどんどん興味を見出していき、THE STREET SLIDERS(以下、スライダーズ)の蘭丸(土屋公平)さんやDEAD ENDのMORRIEさんに夢中になった話も出てきます。
清春:僕が高校生の頃はとにかくBOØWYがめちゃくちゃ流行っていたんです。ロックもポップスも、男も女もヤンキーもみんな飲み込んで、とりあえずBOØWYが好きと言っておけば間違いない時代だったけど、僕はスライダーズに惹かれてた。BOØWYみたいな躍動感はなくてダルい感じで、だけどロックの持っている毒も華も持っている。わかる人にしかわからない、勝手にやっている感じがカッコよくて、その中でも僕はビジュアル的には公平さんがすごく好きでした。当時は「もう本当にこの人になりたい!」と、服も靴もアクセサリーも真似したいと思ったくらいでしたから。
──スライダーズって音楽的には、中高生にはちょっと難しいことをやっていましたよね。
清春:あれは難しいですよね。当時はTHE WILLARDも好きだったんですけど、THE WILLARDも高校生当時の僕には難しい音楽でしたし。先輩の家にそういったバンドのレコードやカセット、雑誌がほぼ揃っていたので、すごく勉強したんですけど、一番難解だったのがスライダーズでありTHE WILLARDであり。だから、当時は音よりも先にビジュアルから入っていたんですよ。音楽雑誌を見てカッコいいと思ったら、先輩のところでレコードを聴いて。ネットもない時代だし、ラジオでそういったロックが流れることもほとんどなかったので、音楽から先に入るということは当時あまりなかった。先輩のところにあればダビングしてもらって、なければ地元の岐阜から名古屋まで買いに行くという状態だったので、そういうことにもワクワクしていたし、不便ゆえに手に入れたときの達成感も強くて。
──DEAD ENDも音からではなくビジュアルから入ったんですか?
清春:同じくその先輩の話なんですが、先輩の家には自分がカッコいいと思うものしか置いていないんですよ。しかも、先輩は基本的にパンクスで、パンクスでもスライダーズはカッコいい、でもメタルはダサいから好きじゃないという。でも、先輩の家にDEAD ENDのアルバム『DEAD LINE』のジャケットが飾ってあったんですよ。で、「これはメタルだけどカッコいいから大丈夫」って聴かせてくれて、聴いた瞬間にMORRIEさんの歌に「なんだこれは?」と衝撃を受けて。すべてのカッコよさが詰まっていて、アリかナシかの判断基準が詰まっていた。あれにノックアウトされた人は当時の世代は多かったと思います。