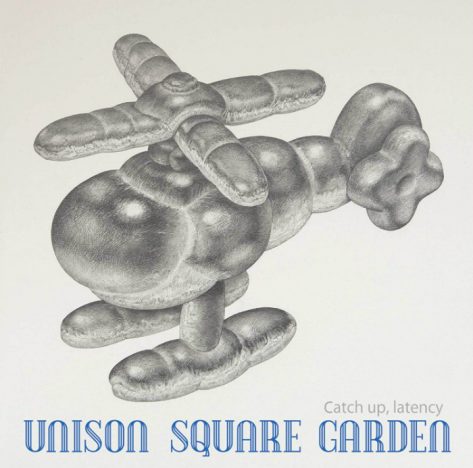金子厚武の「アーティストの可能性を広げるサポートミュージシャン」
向井太一らサポートするMop of Head George、同期を使ったライブセットの可能性を説く 「演出面で生きることも多い」

米津玄師をサポートしているARDBECK(須藤優、堀正輝)を筆頭として、00年代のエレクトロを起点に、ロックとクラブミュージックの融合を試みた世代が、若いアーティストを後ろから支えている2010年代後半。Mop of HeadのGeorgeは間違いなくその主役の一人である。向井太一やiriといった新世代のR&Bシンガーをサポートしつつ、その一方でBACK DROP BOMBのようなハードコア/ミクスチャーのバンドにも関わるというのは、カテゴライズからするりと抜けだしていくGeorgeらしさをよく表していると言えよう。同期が当たり前になった時代のライブセットのあり方や、下の世代に対する想いなど、幅広く話を聞いた。(金子厚武)
「なるべくミニマルなセットですごいことをやりたい」
――GerogeさんがサポートをやるようになったきっかけはKeishi Tanakaさんだったそうですね。
George:そうです。Riddim Saunterが解散した後に、いきなりMop of Headのライブに来てくれて、お誘いいただいて。僕はRiddim Saunterが好きだったので、びっくりしました。もともとサポートには向いてないと思ってて、他のアーティストに関わるなら、楽曲提供の方がいいかなと思ってたんですけど、Keishiさんが誘ってくれるなら、やってみようと思って。実際やってみると、全然違うジャンルを演奏するのはすごく勉強になるし、そこからいろんな方にもお誘いいただくようになって、80KIDZのツアーを一緒に回らせてもらったり、the chef cooks meのライブで弾かせてもらったりするようになりました。
――近年では向井太一さんと密接に関わっていますよね。
George:向井くんはちょっと変わってるというか、もともと事務所から連絡が来て、「こういうアーティストがデビューするんだけど、既存のライブセットじゃない、新しい打ち出し方をしたい」っていうお話をもらったんです。ちょうどその頃に海外でDisclosureとかが出てきて、主流になりつつあったんですよ。あれってスタイリッシュではあるけど、やってることはわりとシンプルだと思ったので、ああいうことを自分の解釈でやってみたくて、向井くんとならそれができるんじゃないかと思い、「やらせてください」って言ったのが始まりです。

――同期を用いた自由な編成のライブセットは日本にもかなり浸透してきましたよね。
George:ラップトップセットも多いですけど、自分的に「ラップトップだけじゃない方がいい」って思うのは、自分がバンドマンだからかなって。マニピュレーターって難しいポジションで、押せば音は出るわけですけど、0.1~0.2秒の感覚で、お客さんの高揚感って変わってくるんです。「この曲が終わって、次の曲スタートします」っていう、その間隔がすごく大事で、「前の曲が終わったら、すぐ次の曲が来てほしい」とかもあるじゃないですか。もともとバンドをやっていたから、最初からそこは意識できていて、sumikaも彼らが同期を入れたいっていうタイミングで連絡をいただいて、マニピュレーターのみで入ったりもして。
――そもそもMop of Headではクラブミュージックを人力で演奏していて、80KIDZのライブセットでは同期を使っていただろうから、素地があったわけですよね。
George:「このタイミングで次の曲が欲しい」みたいなのって、DJの感覚にも近いかもしれなくて、人を高揚させる間だったり、曲順だったりは自分がDJをやるときにずっと意識してたことでもあるから……もともと向いてたのかもしれないですね。
――向井さんのライブセットはどのように変化していったのでしょうか?
George:一番最初は2人だけでやったんですけど、すぐに「ドラムを入れたい」って言って、Satoshi(Mop of Head)を呼んで、会場がデカくなってくると、「ベースも入れられるね」って。これからどうなっていくかはまだわからないですけど、個人的に、あんまり人は増やしたくなくて、なるべくミニマルなセットですごいことをやりたいんですよね。同期の音楽で難しいのが、ただ生に当てて演奏すれば合うってわけでもなくて、例えば、ギターは音源に入ってる音をそのまま使った方が、ライブでも馴染んだりするんです。プレイヤー目線で言うと、弾き過ぎちゃったり、感情をつけようとしちゃうけど、感情がない方が音楽としての聴き心地はいい場合もあって。
――なるほど。
George:最近向井くんのライブでギターを弾いたりもしてるんですけど、「この曲のここは生に置き換えるのがベスト」みたいなことは常に探ってますね。ドラムにしても、音源と同じキックの音をそのままパッドに入れた方がいいのか、ライブだったら別の音にした方が抜けるかとか、そこを考えるのにすごく時間がかかるんです。
――打ち込みの音源をバンドの生演奏で再現すること自体はもちろん昔からあったわけですけど、機材の進歩もあって、よりシームレスになるなかで、そこの精度が求められるわけですよね。それこそ、今は同期を使ってない方が珍しいくらいになってきてるし。
George:そうですね。そのうち「同期だから、生だから」みたいな会話すらなくなっていくと思うし、同期ってものがライブにおいて異物じゃない時代が……今すでにそうかもしれないし、これからのミュージシャンにとっては、クリックを聴いてライブをすることが当たり前になるでしょうね。同期の役割って、外に出る音ももちろんなんですけど、演出面で生きることも多いんです。細かい話ですけど、生演奏だったら曲に入る前にドラムがカウントを出して、テンポをみんなで共有するってことを人力でやるわけじゃないですか。でも、カウントなしで、いきなり全員で入ったら、それだけでお客さんの印象って全然違うと思うんです。
――確かに、そうですね。
George:さらに、照明さんにもクリックを送れば、照明のタイミングも完全にシンクさせられる。USのヒップホップがやってきた演出って、そういうことかなって。日本のライブシーンって、照明だったりVJだったり、モノ的な方に頼っちゃうけど、僕はディテールの方が大事だと思うんです。演出をすごくしようとすると、派手な方向というか、「盛る」方向になりがちだけど、でも「明るい/暗い」だけでも表情は作れるし、海外のバンドとかってそういう中でめちゃめちゃ盛り上げたりしてて。外国の人って大雑把なイメージも強いけど、美的センスに対するこだわりはめちゃめちゃ強いなって。
――アーティスト、照明、VJがそれぞれ盛り上げようとするんじゃなくて、その全部がシンクすることによって、派手なだけではない、強烈な世界観を構築できる。
George:そうですね。そのためには、みんなが同じ時間軸を共有してることが大事で。そうやって時間に縛られるのって、本質的な音楽からはかけ離れちゃうのかもしれないけど、ショウとして考えると、時間に縛られるって、すごくきれいなことだと思うんですよね。美しく始まって、美しく終わる。そういうライブを作るのは、すごく楽しいです。