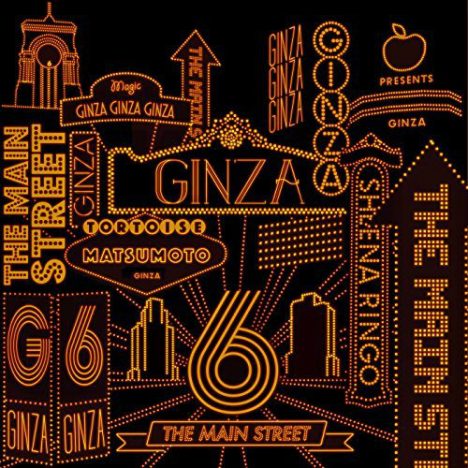椎名林檎が見せつけた“プロ作家”としての本質と底力 『逆輸入』シリーズが示すもの
演歌は「日本の心」といわれ、伝統芸のように思われている。確かに歌いかたに関しては「こぶし」をまわすことに顕著なように、浄瑠璃、民謡、小唄、浪曲といった伝統芸からの流れも含まれているが、バックのサウンドは明治以降に輸入された洋楽をベースに作られたのである。輪島裕介著『創られた「日本の心」神話 「演歌」をめぐる戦後大衆音楽史』が再検証していたように、それまで流行歌、歌謡曲と呼ばれていた領域から「演歌」というくくりが浮上したのは1960年代だった。
以後も吉田拓郎や大瀧詠一を作曲に起用した森進一、坂本龍一の曲を歌った前川清など、非演歌のロック、ポップス系のアーティストと組んでチャレンジした演歌の例はしばしばみられる。近年、市川猿之助が歌舞伎の様式に現代的手法を加味したスーパー歌舞伎の新作として人気漫画『ONE PEACE』を舞台化したことが話題になったが、いわば“スーパー演歌”的なことが行われてきたのだ。
それに対し、石川さゆりは紅白歌合戦で定番の「津軽海峡冬景色」、「天城越え」を歌うだけでなく、フュージョン系のアレンジで制作した『童~日本童謡唱歌集~』(1988年)、岸田繁や奥田民生などロック、ポップス系の作曲家を起用した『X Cross』シリーズ(2012年~)など、“スーパー演歌”的なチャレンジを繰り返してきた人である。
かつて、「演歌」のくくりが成立してから1970年前後に演歌の星と呼ばれたのは、18歳でデビューした藤圭子だった。彼女の娘、宇多田ヒカルと椎名林檎の仲の良さは知られている。宇多田の8年半ぶりの復帰作『Fantôme』(2016年)には2人の共演曲が収められていた。そして、藤圭子の1969年のデビューシングルが「新宿の女」だったのに対し、19歳でデビューした椎名林檎は2ndシングル「歌舞伎町の女王」で「新宿系自作自演屋」を自称していた。初期には昭和歌謡のテイストとオルタナティブロックの合体で注目された椎名林檎は、和洋の融合という点では日本の流行歌のありかたを受け継いでいたし、藤圭子的な要素も持っていた。そんな椎名林檎と石川さゆりは異色の組みあわせではなく、むしろ互いに引きあって当然のコラボだったと思える。
石川に提供した3曲を中心とした『逆輸入~航空局』は、プロ作家・椎名林檎の本質と底力を見せつけたアルバムなのである。
■円堂都司昭
文芸・音楽評論家。著書に『エンタメ小説進化論』(講談社)、『ディズニーの隣の風景』(原書房)、『ソーシャル化する音楽』(青土社)など。