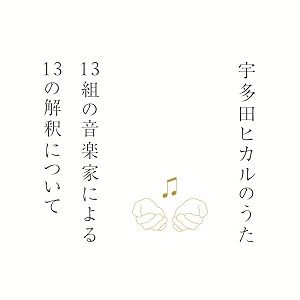宇多田ヒカル スタッフが語る、活動再開で得た実感「ポップミュージックの価値は目減りしていない」

ファンの方々の反応は間違いなく刺激に(梶)
ーーメディア展開は一つ大きな鍵になったと思うのですが、SNSと同時に大手マスメディアとも巧みに連動した印象があります。梶さんの中でそれぞれのメディアの位置付けはどうなっているんでしょうか?
梶:流行っている仕組みを使って何かをやるという発想は、結局手段が目的になってしまって目的を見失ってしまいがちです。なので、僕はまず戦略と文脈作りを明確にして、それを組み立てていきました。レガシーメディアはトリガーとして使い、そこから広がりやトレンドを作っていくのはSNS。テレビだけがトレンドを作れるかというとそうじゃなくて、それをきっかけにSNS上で会話を生んで、その会話の広がりがトレンドを生んでいくんです。一方で、SNSだけでトレンドが作れるのかというと、それも難しい。テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・広告をトリガーとして、SNSでトレンドを作るということを複合的にやっていきました。今回はその流れがうまく作れたと思っています。
ーー宇多田さんは、『Fantôme』のタイミングでかなりの本数のテレビ番組にご出演されていましたが、一連のテレビ出演を振り返ってみていかがですか。
梶:彼女の人間としての成長、昔の宇多田ヒカルとはちょっと違うところを見せることができたかなと思います。見せ方に関しては、相当気を使いましたね。なんだかんだ言って、今、SNSのトレンドのほとんどはテレビがソースになっている。若者がテレビ離れしているとよく言われますけど、そんなことはないんですよね。見方が変わっただけ、リアルタイムで見ていないだけなんです。だから僕は若者に関してはリアルタイムの視聴率よりもSNSでシェアされたか、会話のトレンドにどれだけなったかということを重要視しています。視聴率はリアルタイムの指標としては大事ですが、我々がプロモーションとして考えた時にはトレンドの作り方やシェアされた量、語られている内容の質、そこがすごく大事だなと個人的には思っています。
ーー番組では宇多田さんがご自身の人生をかなり赤裸々に語っていました。ご本人のお考えもあるかと思いますが、これも言葉をどう届けるかという戦略の一つだったのでしょうか。
梶:まず4月4日に新曲を公開した時、宇多田ヒカルはかなりドキドキしているように見えました。なぜならば、彼女にとって母親は大切なリスナーの一人でしたが、母親というリスナーがいない初めての作品だったからです。その時はまだ公言していませんでしたが、今は亡き母親に捧げる作品ということもあり、どのように世間に受け止めてもらえるかということは気になっていたみたいですね。
沖田:「花束を君に」はもちろんドラマのために作った曲なんですよ。ただ、重層的に彼女のお母さんへの思いが織り込まれていた。それは「真夏の通り雨」もしかりです。聴き手によって様々に解釈されるというのは、ミルフィーユのようにいろんなものが織り込まれた構造の曲だということですね。
梶:お聴きいただいた中には、さっそく宇多田ヒカルの思いに気づかれた方もいて。ちゃんと思いを受け止めてくださったことが彼女的にはすごく救われたというか。それがあって実はこのアルバムの制作はどーんと進んだんですよね。
沖田:そうだね。フォーカスが合ってきたんだと思います。
梶:だってこんなに早く作れたの初めてじゃないですか(笑)?
沖田:きっとスター・ウォーズ的に言うと、「母」というフォースを得たんですよ(笑)。そこからは「二時間だけのバカンス」のような妖しげな恋を暗喩させる曲だったり、「ともだち」のようにストレートではない恋愛を想起させる世界に踏み込んでみたり。曲を作っていく中で作家として自由と勇気を得たんだと思いますね。
梶:彼女のクリエイティブの中で、今回のファンの方々の反応は間違いなく刺激になっていて。それで一気にアルバム制作を進めることができたんです。
沖田:実はテレビ番組の収録は『SONGS』が一番最初だったんですよ。『SONGS』が終わった後に本人と「かなりシリアスに喋ったね」と話していて。「次、タモリさんとはちょっと明るく行こう」「そうだね」と、世の中からの自分の見え方を冷静に捉えることができるようになったのも、この6年間の活動休止で得た彼女の新たなフォースだったんじゃないかなと思いますね(笑)。
梶:でも、それは元々ありましたけどね。ソーシャルリテラシーが高くて、空気の読み方が上手なので、相手を見て何を求められているのを瞬時に判断して出せる。今回はそういうことも含めて各番組でバランスのいい表現ができたのと、自分をさらけ出してもちゃんと受け止めてくれる人がいるという安心感があったからこそ、自分の中で一つ鎧が外れたというか。楽曲の広がり方とファンのみなさんの楽曲の受け取り方が彼女を開かれた状態にしていったんです。作品を作っている間も、SNS上のいろんな言葉や感想から刺激を受けていましたしね。
ーー作り途中の作品にファンの声がフィードバックされていくのは新しいですね。
梶:歌詞サイトでも、ハッシュタグを付けてみなさんの意見が一カ所に集まるような設計にしました。本人も全部チェックしていて、どういう風に自分の作品が受け取られているかを見て楽しんでましたね。僕はそういった場をとにかく作っていき、積み重ねていった感じです。あんまり複雑化しないでシンプルに展開していきましたね。
沖田:僕は、2014年に『宇多田ヒカルのうた』というカバーアルバムを出した時、宇多田ヒカルの曲が持つ「寛容性」というか、チャレンジができるなと感じたんです。今回のフィーチャリングゲストに関しても、今ならできるという確信が持てたからこそ実現できた部分もあって。今作で行った、情報を溜めて溜めて最後に弓矢のようにバンと引くという梶の手法も、この時すでに行っていたものなんですね。『宇多田ヒカルのうた』の時も参加アーティストを発表したのが発売の3週間前で(笑)、発表した瞬間に作品に対する注目度が一気に高まりました。この時に得たものは我々二人にとって大きかったですね。しかも本人不在の場で宇多田ヒカルの名前を使うという実験的な場でもあったので。彼女の音楽は本人だけのドキュメントではなく、図らずもその時代の音楽シーンにおいてのドキュメントになっていたり、聴く人たちのドキュメントにさえなっているという、すごく珍しいケースのアーティストなのだということにも気づけました。『Fantôme』はリリース前からいろんな方に注目していただいていて、宇多田ヒカルのオリジナルアルバムに何かを重ねていらっしゃるようで、その期待感はものすごく感じていました。結果として、しっかり2016年の音楽業界のドキュメントの一つになれたかなとは思います。とても幸せなことです。