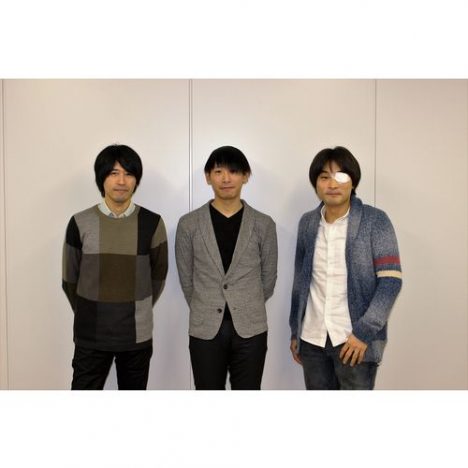クラムボン・ミトの『アジテーター・トークス』Vol.3 大沢事務所・松岡超
花澤香菜は声優&アーティストとしてどう成長してきた? クラムボン・ミト×花澤マネージャーが語り合う


「アニメキャラを演じるのは、キャラソンも含めて演技の一つ」(松岡)
――北川さんの起用に始まり、リリースした楽曲の方向性やコンポーザーの人選など、花澤さんのアーティスト活動は音楽ファンからも注目されるものになっています。これも松岡さんが北川さんと相談のうえで仕掛けたことなのでしょうか?
松岡:そうですね。キャラソンの延長線上でやるのが無しというわけではなく、僕自身が音楽好きとして、もっとガッツリ取り組みたいと思って北川さんに話をしました。楽曲制作も打ち込みメインではなく楽器の演奏でオケを制作したほうが良いし、ライヴだってバンドを背負っていた方が楽しいとか、そういう話をしつつ、本人も活動を通して音楽に対する興味が膨らんでいるようです。もちろん、声優さんのなかには歌うことに対して抵抗のある人もいるのですが、僕はお芝居や声優業などに跳ね返る部分もあると思うし、アニメのキャラクターを演じている場合は、キャラソンも含めて演技の一つだと考えているんです。
ミト:だとしても、これまで音楽をやっていなかった花澤さんを歌うことに飛び込ませたのはすごいと思いますよ。
松岡:幸いなことに周りの方にも後押ししていただけましたし、何より本人が一番努力をしているので、その相乗効果だと思っています。あと、今回アーティスト活動を始めるうえで、アニプレックスさんには「タイアップを付ける必要はないです」とハッキリ言いました。アニメのメーカーさんなんですけどね(笑)。もちろんタイアップが付くこと自体を悪いとは思っていないのですが、イチから時間をかけて花澤香菜の音楽を作っていくにあたって、作品に引っ張られることは避けたかったので、そのように提案させてもらったんです。
ミト:そういうところが松岡さんの特殊な部分だと思いますよ。だって、声優・アニメ業界のいちタレントさんに対して投げ与える課題ではないでしょ(笑)。
――プロジェクト初期から長期スパンで“花澤香菜の音楽”というブランドを作り上げることを考えていたんですね。
松岡:そうなんです。1stシーズンである『claire』までの期間は“春夏秋冬”と銘打って北川さん、中塚武さん、神前暁さんに制作してもらい、4枚目の『Silent Snow』ではアニプレックスさんに「アニメと融合したMVを作りたい」とお願いし、下田監督とサンライズさんに協力いただきました。で、そこに冬服バージョンの守凪了子(カミナギ・リョーコ)も登場してもらっているのですが、この発想自体は作品をつくる3年くらい前から考えていました。
ミト:松岡さんの構想話、あちこちに漬物みたいに長く漬けてあるので「これも!?」って驚かされますよ(笑)。
松岡:基本的に普通なことが嫌いなタチなんです。だから安易に想像できることとは違うものをやりたがるというか。例えばビートルズのアルバムだったら、『Revolver』のあとに『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』があるわけで。そんなことを考えているもんですから、2ndアルバム『25』の制作会議で北川さんとメインで作詞をしてもらった岩里祐穂さんに「25曲やりたいです」と言って、「えっ、本当ですか!?」と本気で驚かれてしまいました。
ミト:僕も北川さんから話を聞いた時に「あっ、松岡さんは狂っている」と思いました。結果的に楽曲も良いものが揃ったし良かったんですけど、これだけは言わせてください。ビートルズは2枚目にして『ホワイト・アルバム(The Beatles)』は作らないんですよ(笑)! このままいくと、4枚目にしてジョン・レノンの『Double Fantasy』を作りそうだし、そうなってくると我々みたいなバンドや音楽家が食いっぱぐれていく世界になりますから、できることならば、これ以上幅は広げないでいただきたい。これを忠告しに対談したようなものです(笑)。
松岡:逆にその取り組みを経て色々なものが上手く重なれば、とんでもなく新しいものが生まれる可能性があるわけじゃないですか(笑)。
ミト:ダメだ、わかってもらえない(笑)。松岡さんとは、レコーディングの時にマニアックな音楽の話をするんですけど、彼の口からはオレンジ・ジュースだったり次々に声優のマネージャーさんとは思えないアーティストが出てくる出てくる。
松岡:1970年代後期から1980年代頭のポスト・パンク/ニューウェイブが大好物で(笑)。そういう意味でもミトさんとは音楽性が合うし、なによりすごい曲を書く人だと思うんです。毎回「そこか!!」ってところを持ってくるし、僕はリファレンスとして洋楽を挙げることが多いんですけど、そもそも日本の楽曲とは構成が違うじゃないですか。でも、そこも理解したうえで提示した曲の要素を感じさせつつ、全く違うものにしてくれるんです。
ミト:クリエイターとしては、僕が花澤さんに何かをしたいということはあまりないです。だって、松岡さんの中でイメージが固まっているし、まさに「Trace」(3rdAL『Blue Avenue』収録曲。ミトが作編曲を担当)というか、そこに自分が曲を書いて、花澤さんの歌を当てることで色がついていくんですよ。あまり拘りを持って気負っていると作品自体が狭くなってくるので、窓を開けたままどうやって作るかというのは、自分の作品作りでは重要視しているので、良い関係性だと思います。これは音楽家だけじゃなくて、声優さんも俳優さんも同じかもしれない。

――今のお話を聞いて花澤さんが毎作、毎シーズンごとにファンを驚かせる試みに取り組んでいる理由がわかりました。
松岡:花澤プロジェクトも4thシーズンに入って、花澤を新しい音楽に触れさせるというテーマはずっとあって、『あたらしいうた』ではカップリング曲含めて全曲作詞にも挑戦しました。ここにきて本人も歌うだけじゃなく自分で作ることへの楽しさを見出してきたんです。
ミト:彼女の作詞した曲って、個人的には実音に対して素直に言葉を入れることができているという印象で。思いつきで言葉がはまればいいんだって人もいるけれど、音節的には「これがここにハマらないと実は気持ち良く聴こえない」というものは必ずあるし、それって筋トレが必要なのに、あっさりできているのがすごい。多分それって、今まで多くの曲を歌って、自分で口を動かしたことで「この言葉を当てていくと気持ち良い」という感覚が潜在的に出来上がっていたからだと思うんです。
――これまでの積み重ねがバッチリ活かされているわけですか。
ミト:そうだと思います。これ、作曲家の中でも結構問題になることで、歌わないで作れるメロディって大体売れない要素が高いんですよ。順番でいうと、メロが先に出てくることが実は大前提で、トラックから逆算してメロディを足していくと上手くいかないことが多い。リリックにおいても同じようなことで、良い曲ってとにかく歌ったほうが良くて、その口の動かし方や音節でラインが出来上がってくることもあるし、バンドにおいてもボーカリストの作る曲がキャッチーになりやすいのって、そういうことだと思うんです。
松岡:歌いこんできたところが詞の向上になっているというのは、確かに腑に落ちるところはありますね。