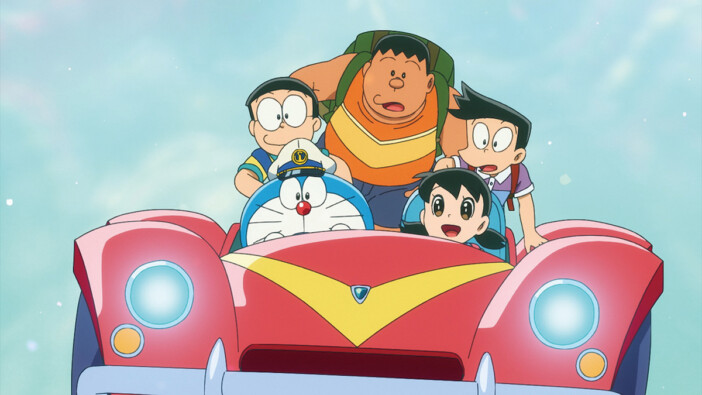小野寺系の『メアリと魔女の花』評:“ジブリの精神”は本当に受け継がれたのか?
近年、新作を作る度の風物詩となっていた、宮崎駿監督の「長編引退宣言」。『風立ちぬ』完成時にも、本人が「またかと思われるかもしれませんが、今回はマジです」と言いながら、その後また撤回されたわけだが、スタジオジブリの製作部門は、復帰宣言の前に本当に解体されてしまった。
『魔女の宅急便』で動員数200万人を突破してから、安定的に大ヒット作品を連発、「ジブリブランド」を確立し、国内の劇場アニメのシェアを握ることになっていった、スタジオジブリと宮崎駿。スタジオ解体という状況のなかで、日本の多くのアニメーションスタジオは、その王国に成り代わることを望み、アニメーション監督は、「ポスト宮崎」という玉座をねらう事態が起きている。
そこで注目されていたのが、スタジオポノックである。『思い出のマーニー』でコンビを組んだ西村義明プロデューサーと米林宏昌監督、従業員の8割がジブリの作品づくりに関わってきた人たちが集結したという、この新しく設立されたスタジオは、最もスタジオジブリに近しい存在であるはずだからだ。
だが、完成した記念すべき第一作、『メアリと魔女の花』を公開初日に劇場で見た私は、絶望的なまでに作品が面白くないことに驚愕してしまった。この作品を褒めてしまっては、信用問題に関わると思ったほどだ。映画評論は、映画の魅力や面白さを伝える役割がある。だが作品が全く面白くない場合、言葉を尽くして理由を述べて、駄目なものをしっかりと駄目だと伝えるという使命もある。今回はあえて、『メアリと魔女の花』の駄目なところをじっくりと多角的に語っていきながら、アニメーションの未来を考えていきたい。
「ジブリの精神」は受け継がれたのか
「ポノック」という、「深夜0時」を意味するスタジオ名には、「ゼロからの挑戦」という意図が込められているという。だが同時に、西村プロデューサーは「ジブリの志、精神を受け継ぐ」とも表明している。これは、「会社としてはジブリから離れてやっていくが、作風はそのままでやっていきたい」ということだろう。 動画枚数が9万枚を超えていることからも、ジブリが目指してきた「フルアニメーション」を、引き続き志向しようとする意志が見える。
『メアリと魔女の花』は、絵柄のみならず、多くの描写が、これまでのジブリ作品を想起させるものになっている。上映が始まり、スタジオジブリのトレードマークであるトトロの横顔を模した、少女メアリの横顔が表示された時点で、この作品の「ヤバさ」がすでに漂ってくる。少女の顔をスタジオの象徴にするというセンスはともかくとしても、こういったパロディーを面白いと思っているユーモア感覚に不信感を覚えてしまう。それは、『魔女の宅急便』を意識した「魔女、ふたたび。」という煽りを、『メアリと魔女の花』のキャッチコピーに選んだセンスとも通底している。
そのマークが象徴するように、劇中では、雲の上のお城で冒険する『天空の城ラピュタ』、動物たちが駆け回る『もののけ姫』、『借りぐらしのアリエッティ』でも引用した、少女が大粒の涙を流す『千と千尋の神隠し』、魔法使いの戦いを描く『ハウルの動く城』など、強引なまでにジブリ作品を思わせるような要素が散りばめられている。本作は英国の児童文学が原作となっており、たしかにジブリ映画のような要素は多く含んでいる。しかし、それを全力でジブリ的な表現に引き寄せているので、とりわけ宮崎作品のダイジェストを見せられているような気分になってくる。
たしかに宮崎監督自身も、マックス・フライシャーやレフ・アタマーノフ、メビウスなど、自身が見てきた世界中の様々なクリエイターの作品を、そのまま自作でパロディー化してしまうことが多い。しかしそこには、その描写に至るまでの作家的な必然性や、作家自身が面白がっていることを皮膚感覚で理解できるものになっていたはずだ。しかし、『メアリと魔女の花』の既視的描写というのは、そのような作家性が熱くほとばしってくる発露というよりは、ひたすら義務的で冷めきったものに感じられるのだ。
実績のない新しいスタジオが、資金を集め大ヒットを狙っていくためには、プライドを捨てスタジオジブリ出身というアドバンテージを最大限に利用し、古巣におんぶ、抱っこをして人気を集めるような演出をやらざるを得なかったというのも、理解できなくはない。だが、ここまでの過剰なジブリファンへのサービスを、果たして観客側は望んでいたのだろうか。そして最も深刻なのは、そこまで泥臭く、不自然な印象を与えてまで挿入した描写一つひとつが、作品の面白さに寄与できていないという点である。