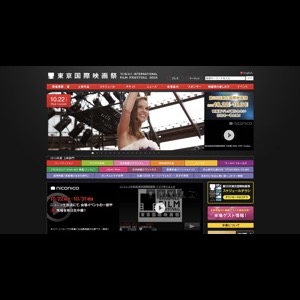『クリムゾン・ピーク』がホラー映画と断言できない理由 ギレルモ監督の作家性から読み解く

「幽霊は実在する」という語りから幕を開けるギレルモ・デル・トロの『クリムゾン・ピーク』は、彼の十八番であるダークサイド映画の極地である。死者の亡霊を見ることができる作家志望の女性が、実業家の男と恋に落ち、海を渡りイギリスの田舎町の廃れた屋敷で男の姉と3人で暮らす物語だけを聞くと、どこか古典的なメロドラマを想起させるものがある。とはいえ、そこに深紅の亡霊の姿を可視化させることで、一気にデル・トロのテリトリーであるダークな世界に観客を引きずり込むのである。
序盤から頻繁に登場するその亡霊の造形は、この映画の最大の見せ場である。舞台となる屋敷の周辺で発掘される赤粘土にまみれたような、深紅色に染まったモンスターのような出で立ちによって、この映画はホラー映画というジャンルに滑り込むことができよう。しかし、総じて幽霊話を軸にしたところで、これはホラー映画と断言することはできない。限りなく、いや、紛れもなくメロドラマのジャンルに相応しいのではないか。

何故これが「メロドラマ」と呼べるのか。前述のような文芸ドラマのような設定に加え、ヒロインと幼馴染と姉弟の四角関係を、閉ざされた屋敷という狭い世界の中で描き出したこと。さらに、タイトルにもなっている“クリムゾン・ピーク”と名付けられた、赤粘土の土壌が雪原に浸透し、辺りを赤くさせるミステリアスな現象によって、扇情的な雰囲気を醸し出したことに他ならない。
ハリウッドの大作映画で活躍するキャストを集めたアンサンブルでありながら、アメリカンビスタの画面に集約されることで、大作感を感じさせない。そこがまさに、5~60年代のハリウッドのメロドラマを彷彿とさせるのではないだろうか。
つまりはギレルモ・デル・トロがデビュー作から一貫している選択によってもたらされた成果でもある。デビュー作である『クロノス』から本作に至るまで、彼の長編作品9本は全てアメリカンビスタの画面に集約されている。一般的なテレビの画面(16:9)よりも若干横長の、1.85:1の画面に、彼は定番のヨーロピアンホラーからマーベル映画、さらにはSF超大作さえも収めてきたのだ。2.35:1のシネマスコープによって生み出される大作感は映画を商業的娯楽に見せる大きな役割を果たしているが、彼はどんなタイプの作品でも、それを選択してこなかった。現に、彼が監督した『ブレイド2』は、マーベル映画では数少ないアメリカンビスタサイズの作品である(他に『スパイダーマン』と『アベンジャーズ』がそうであったはずだ)。

ヨーロピアンホラーの代表である、ダリオ・アルジェントの『サスペリア』はシネマスコープで撮られた作品だった。本作も同じように、赤の色を強調したゴシックホラーとしてのジャンルを目指すのであれば、同じ画郭で足並みを揃えることもできたであろう。また、白黒映画であるが、英国屋敷もののホラーとして真っ先に思い浮かぶであろう、ジャック・クレイトンの『回転』でさえもシネマスコープで作られていた。これら名作ヨーロピアンホラーの空気を踏襲することよりも、あくまでも「ギレルモ・デル・トロの映画」が辿ってきたセオリーを貫き通したことは、彼の作家としての誇りを感じずにはいられない。
その結果として、適度なスケール感と高級感をキープしただけでなく、幾度となく劇中に登場する一点透視図法的な構図は、この画郭でしか表現できない奥行き感を最大限に活かしていたし、被写体との距離の加減や、それに伴って画面に映らない部分へ観客の好奇心が向くように巧みに操られている。オーソドックスな画郭であるアメリカンビスタの最も素晴らしい使用例である。