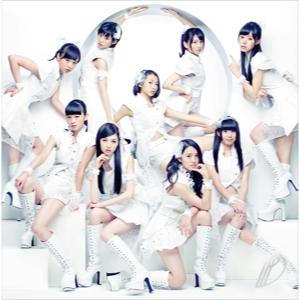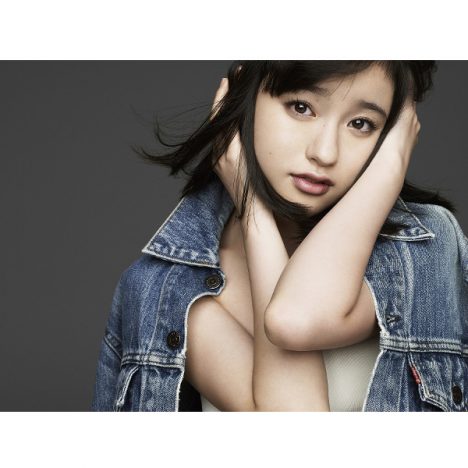ターボ向後のマニアック音楽シーン探訪
フェアリーズはなぜ物語を必要としない? ターボ向後が“妖精学”から魅力を読み解く
「Fairyology=妖精学」という学問をご存じだろうか? あまり一般にはなじみのない言葉だが、古代ケルトの時代からヨーロッパを始め世界中で伝承されている妖精という存在について、民俗学他あらゆるアプローチで思索を深めていくものだ。そんなフェアリー研究にハマってしまった著名人に、ヒットアニメ『名探偵コナン』の主人公・江戸川コナンの名前のもとになっている作家、アーサー・コナン・ドイルがいる。
本格探偵小説の礎を築いた『シャーロック・ホームズ』シリーズの後、彼の晩年における執筆活動の多くは、いわゆるオカルト現象を研究・解明する著作に集中していて、「スピリチュアリズムのパウロ」と呼ばれるほどだった。なかでも当時、最も世間を驚かせたのは、有名な「コティングリー妖精写真」について書いた問題作『妖精の到来』。撮影を行った少女達によって、事件の60年後にねつ造だったと告白された世界一有名な妖精たちの写真を、ドイルは「間違いなく本物である」と断定してしまったのだ。
現在ならSNSで炎上必至なトンデモ本である。しかしそのテキストを100年経ったいま、現代的な妖精学の視点から読んでみると、その評価は一変する。ケルト神話において「目に見えない美しい国(フェアリーランド)に住む美しい人々」とされた妖精という存在を巡る、メタフィジカルな散文詩として読むことが可能な傑作となっているのだ。
「真夏の夜の夢」から「テンペスト」まで、自らの多くの作品に妖精を登場させ、現在、我々が思い浮かべる"いたずらで可愛い"妖精像を作り上げたのは、シェイクスピアやドイルといった作家たちだった。そして、妖精=フェアリーに向き合うということは、歴史においていつも、その時代の社会性を照射するポップなアイコンを、いかにして手に入れるかを考察することだった。
フェアリーズの1stライブツアーDVD『SUMMER PARTY』は、まさに妖精学的視点から読み解いてこそ魅力が浮き彫りとなる、画期的なアイドル作品である。
彼女たちの場合、一般的なアイドルヲタ目線で捉えようとすると、正直なところ「推しがいのなさ」を感じることもあるだろう。運営は、あの安室奈美恵を擁する大手事務所で、ワイドショーではデビュー前から特集が組まれ、いきなりTVで看板番組を持ち、その年(2011年)の日本レコード大賞最優秀新人賞も受賞してしまう。その華々しさは、現在のアイドル界において大きな魅力のひとつとして機能している“物語性”とは無縁で、彼女たちを応援することで得られる一体感ーーアスリート競技におけるチームとサポーターのような関係性は生まれにくい。「まぁ、俺らが応援しなくてもなんとかなるっしょ?」というシニシズムに陥ってしまうのだ。
さらに、マニアックといってもいいほどの洋楽指向が、彼女達をいわゆるアイドル楽曲のシーンとは異なるところに位置付けている。90年代のアン・ヴォーグやデスティニーズ・チャイルド的なR&Bと歌謡曲のミクスチャーをとことん極めたデビュー曲「More Kiss」から始まり、大滝詠一氏がナイアガラレーベルのシグニチャーの一つとして追求した“ギミックサウンド”を、エレクトロポップの文脈で大胆に導入した「Tweet Dream」、地鳴りのするようなハードトランス系リフが切ないはずのウインターラブソングを侵食していくダークポップの傑作「White Angel」、そして2000年代に一世を風靡したネプチューンズサウンドと最新EDMをまるで映画トランスフォーマーに出てくる変型ロボのように合体させた傑作「BLING BLING MY LOVE」と、書いているとキリがないほど、非常に凝った曲ばかりを発表しているのだ。その過剰な楽曲の構造は、いわゆる“楽曲派”と呼ばれるようなアイドルヲタからも、支持を得にくいものだったかもしれない。