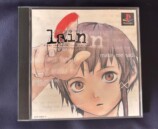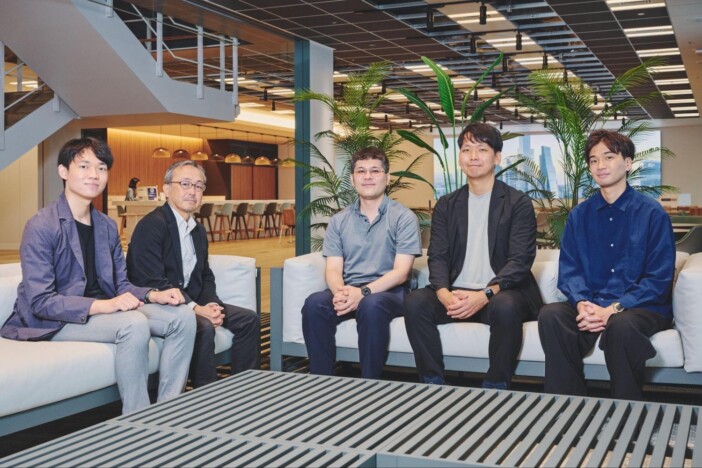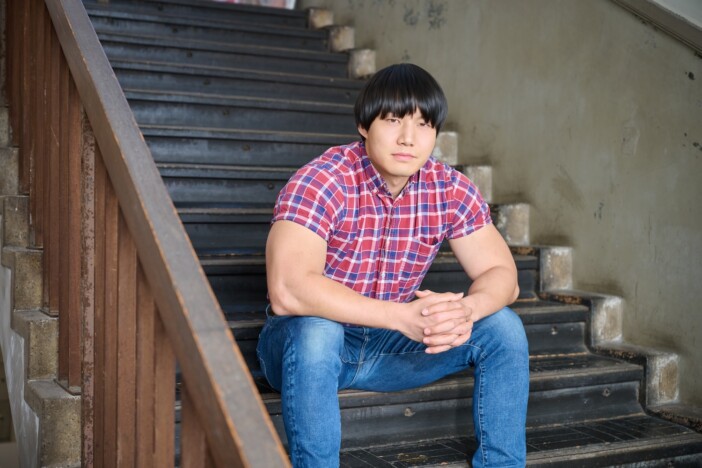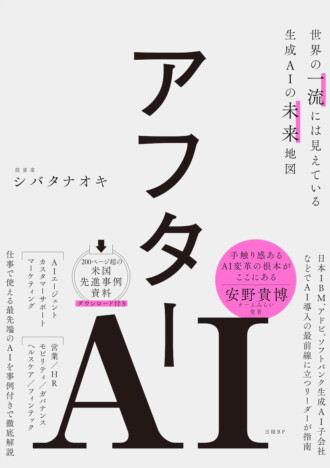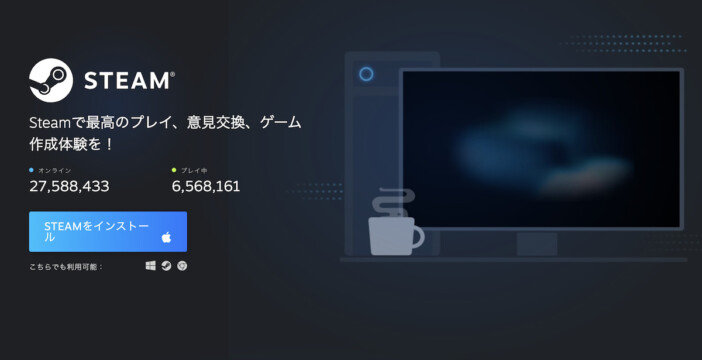JOIとK、Lapwingと私たちが交わす“視線と声”の交感 現代の「あなたの望むすべて」をもたらすものの正体について

現代を生きる私たちもまた、ゴズリングと同じ道を辿っている
『2049』もある意味では、そうしたノスタルジーを何層にも重ねた映画だった。そもそもがリドリー・スコット監督の『ブレードランナー』(1982年)の35年越しの続編だし、その前作が火付け役(※1)となったサイバーパンク・ムーブメントのデザインやイメージも参照している。
※1:映画公開の二年後に『ニューロマンサー』を出すことになるウィリアム・ギブスンが劇場で観て「構想中の小説とあまりに似すぎている」とパニックに陥り、すぐに退出したのは有名な話。
ノスタルジーは、ストーリー上の連続やジャンル的なスタイルのみに留まらない。劇中には「パンナム」の愛称で親しまれたパン・アメリカン航空のサインが出てくるけれど、現実のパンナムは91年に解散している。それがなぜ『2049』に出てくるかといえば、前作に登場した企業だからだ。『ブレードランナー』に出てきた実在企業はその後軒並み業績が悪化したり倒産したりして『ウォールストリート・ジャーナル』紙から「『ブレードランナー』の呪い」と皮肉られたほどだが、『2049』では相変わらず繁栄を謳歌している。
他で出てくるテクノロジーも2049年にふさわしいようで、「未来的」といわれると、どこか違和感がある。それもそうだろう。『2049』で描かれているのは、われわれの現実の延長線上にある未来ではなく、かつて『ブレードランナー』で夢見られていた“未来の続き”だ。過去に存在した意匠や様式を強調することで失われた未来を造りだす、哲学者のフレドリック・ジェイムソンのいう〈ノスタルジア・フィルム〉を、そのままパロディとして実践している(※2)。
※2:『ブレードランナー』の脚本家だったハンプトン・ファンチャーはフィルム・ノワールやチャンドラー的なハードボイルド探偵を強く意識したと各所で表現している。第一作目からして、すでに過去であったイメージの再現が夢見られていたのだ(参考)。
近年であれば、やはり同じくリドリー・スコット監督のSF映画の古典『エイリアン』シリーズ(1979〜)の最新スピンオフである『エイリアン:ロムルス』(2024年、フェデ・アルバレス監督)が70-80年代的なレトロフューチャー的な意匠を施されていたことも記憶に新しい。
そして、もちろん、ゴズリングとJOIの関係もそうした甘いノスタルジーのなかに位置づけられている。仕事終わりのゴズリングが自分のアパートメントに帰ってきて、“ディストピア飯”としか形容しようがない未来的でへんてこな食事を用意していると、1950年代風の髪型と服装に身をやつしたJOIが現れ、豪奢なステーキを運んでくる。ホログラムであるJOIの焼いたステーキは、もちろん幻影だ。この幻のステーキが、テーブル上に置かれていたディストピア飯とオーバーラップしていく。
もちろん、陰鬱な2049年では「アメリカ黄金期のかわいい奥さん」など虚像にすぎない。その空虚さを了解しつつも(※3)、ゴズリングはそのイメージをAIコンパニオンであるJOIにまとわせる(※4)。
※3:ベティ・フリーダンが指摘したように実際には50年代のアメリカ郊外に住む「幸せな家庭」の主婦たちはジェンダー・ロールの固定と社会的孤立に苛まされ、心身を害していたことも多かったのだが。
※4:劇中のゴズリングの視覚的な欲望は観客の視線と重ね合わされるものでもあることに留意しておきたい。「カメラというものは本質的に男性的であり、その不安と欲望を映し出す強力な道具として、女性を永遠に〈対象〉として映し出す」というローリー・ムーアのことばが強烈に想起されずにはいられない。https://www.nybooks.com/articles/2013/12/19/gazing-love/
ここでAIとの恋愛を描いた2010年代のSF映画をもうひとつ、思いだそう。スパイク・ジョーンズ監督の『Her』(2013年)だ。この映画では、離婚調停中で沈んでいるホアキン・フェニックスが対話型音声アシスタント(声はスカーレット・ヨハンソン)と次第に親密になっていく。劇中で、ホアキンがフルーツ・スムージーを飲んでいると、同僚から「果物をスムージーにするのはよくない。繊維質がミキサーでずたずたに破壊され、糖分だけの飲み物になってしまう」と指摘されるのだが、そこで別の同僚がこう反論する。「でも、かれはスムージーの甘さが大好きで、飲んだら幸福感を得られるのかも。そういうのだって、体にいいんじゃないの?」。
虚ろな幻影であるとわかっていたとしても、そこに幸福の手ざわりはある。その喜びと哀しみを『2049』では、文字どおり二重写しのイメージとして描いた。それが、JOIのステーキだ(※5)。
※5:この手法は劇中中盤でのふたりのセックスシーンにも反復される。JOIは娼婦のレプリカントを雇い、その身体とホログラムとしての自らを重ねることでゴズリングと情を交わす。ちなみにAIが娼婦を雇って、相手役の男性とセックスする、というのは前述の『Her』にもそのまま出てきた描写であり、ここでの共鳴も興味深い。
『2049』における二十一世紀とは、望みうる幸福がイメージと、過去への郷愁にしかなくなった時代のことだ。だからこそ、レプリカントではない「本物の子ども」が最重要なマクガフィンとして機能する。本物の子どもがいれば、本物の未来を築くことができるのだ。人間としての未来を。
そうして、失われていない2025年の現在、わたしたちもまた『2049』のレプリカントや『Her』のホアキンのように、幸福のイメージに淫している。それも、かなりかれらの消費形態に近い形で。
恋愛対話型などとも称される生成AIチャットボットサービスは、ユーザーの望む範疇で恋愛的な親密さを演出することができる。この手のサービスは現在、無数に乱立している。代表とされるのは、Character.aiとReplikaだろうか。なぜこのふたつが有名かといえば、前者は自殺者を、後者はテロリストを生んだからだ。ことの経緯や当事者の心理状態はともかく、それらの事件はユーザーに対して一定の親密さを築きあげた証ではある(※6)。
※6:実際、AIに肯定的な面を性役割に対する文化的プレッシャーの解放やトキシックでない形のコミュニケーションに効用を見出しているユーザーも多いという肯定的な研究もあれば、後述の欧州大学院のラース・エリク・ロハース・ジャーディのように、AIにおける巧みな擬人化や関係構築に「現代資本主義における親密さの植民地化」を見出すものもいる。
さて、現代の対話型AIチャットボットは興味深い特徴を具えている。声と姿だ。Character.aiのキャラクターたちにはカスタマイズ可能な音声がつき、Replikaでは声に加えて3Dモデルのアバターもついてくる。
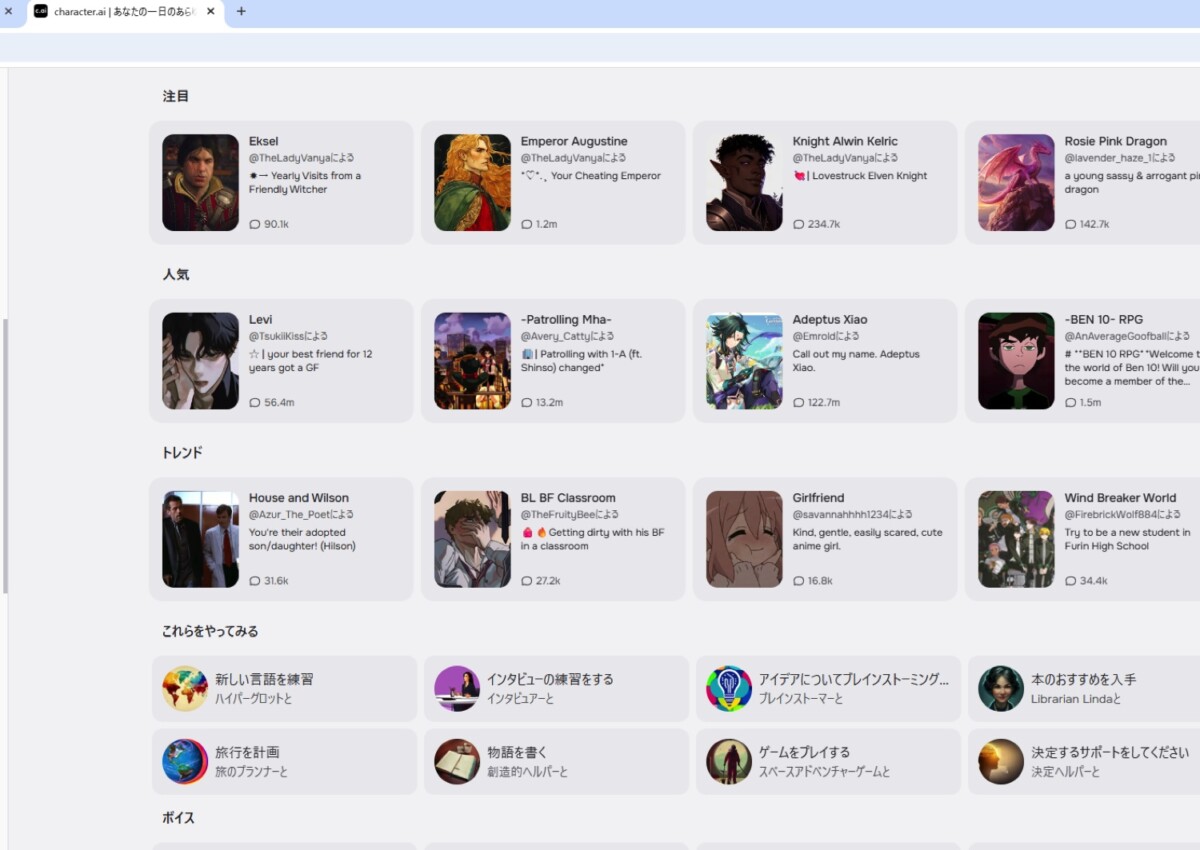
「声の双方向性」がもたらす“過剰な親密さ”への錯覚
声は双方向的である。『Her』のホアキンが声だけのヨハンソンとたちまちに親密になっていくさまを例に出してもよいのだけれど、最近の作品も挙げておこう。
今年の4月に公開されたNetflix製作のSFドラマシリーズ『ブラックミラー』のシーズン7・第3話「ホテル・レヴェリー」だ。2020年代に生きる俳優(イッサ・レイ)がAI技術によってヴァーチャル・スタジオとして再現された1950年代の古典モノクロ映画『ホテル・レヴェリー』の世界へ送り込まれ、そこでリメイクの撮影を敢行する。ところがその撮影中に致命的な事故が起きてしまい、イッサは原作の主演女優(エマ・コリン)とヴァーチャル・スタジオに閉じこめられることになる……という話だ。お察しの通り、ふたりは恋に落ちる。全体的に強引で驚きにも乏しく、出来のよいエピソードとはいいづらい。けれども、ラストがすばらしい。
なんのかんのとトラブルを乗り越え、イッサは撮影を終えて現実世界へ戻ってくる。リメイク映画は興行的に成功したものの、エマと不本意な別れ方をしたせいで、どこか割り切れなさが残っていた。そこに、映画制作の関係者から『ホテル・レヴェリー』の未使用動画素材と電話の受話器が送られてくる。動画を再生すると、モノクロ世界の映画セットでプロップの電話と戯れるエマが映る。「この電話、どこにもつながってないんでしょう?」。現実世界にいるイッサが(リメイク映画を作ったときのものと同種のテクノロジーが施されているであろう)受話器をパソコンにつなぐと、画面のなかでプロップの電話が鳴り出す。怪訝な顔で、エマがおそるおそる電話を取る。
このラストシーンには、眼と声における応答への期待の違いが浮きぼりにされている。つまり、わたしたちはただ見るときに、それも画面越しにだれかを見るときにはその視線を返されることを期待しない。いっぽう、声をかけるという行為は、ほぼ必ず相手からの応答を前提にする。
イッサはもともと映画『ホテル・レヴェリー』のファンだった。シンプルで明朗な古典映画に生きるチャーミングな名女優を、ノスタルジー込みの憧れの眼で見ていた。スクリーンという物質と七十年以上の時という二重の隔たりは、どうしても視線を一方的にせざるをえない。しかし、映画の世界に入り、人間としてのエマ(なぜか「役」の外での人格の影響も受けている)に触れ、会話を交わすことで、おたがいのあいだに対等なつながりを築く。この過程が、眼から声への移行に反映されていく。愛とは、双方向的なものだ。『2049』でも、JOIはなによりまず声として登場した。
逆にいえば、双方向であることを前提にする声は、親密さを過剰に錯覚させる要素でありうる。Character.aiで自殺事件が起きたのは、音声会話機能の実装直後のことだった。
音声機能付き対話型AI以前のわたしたちは、まず見るよりほかなかった。「スクリーン」ということばは、19世紀に幻灯機が登場するまで「視界を遮るために間に置かれる仕切」という意味だった。視聴者と対象のあいだに横たわる、絶対的な距離と断絶。ノスタルジックな感覚が与える時間の隔たりは、その距離をさらに広げていく。
Lapwingを見るオタクたちがあんなにも哀しげだったのは、それを知っていたからだ。届かぬことの慎ましさに生きていた、20世紀の愁情。ことばもなく、ただ眼を泳がせることでしかリアクションできなかった。それが「You look lonely」ミームの体現していたゴズリングの顔だ。
しかし、『2049』本編のゴズリングは、そうしたインタラクションへの古い諦念を乗り越えた者でもある。かれは声を介してJOIと会話ができた。高価(らしい)デバイスを買い、アパートの一室に縛られていたJOIを外出できるようにした。セックスもした。「愛してる」といってもらった。
2020年代的なAIとのふれあいが極に達するのは、別離においてだ。JOIは死ぬ。死は究極の断絶だ。断絶は途中から生じるのであれば、AIとの関係を決定的に深めてくれる。というのも、現代の恋愛対話型AIチャットボットにも死がある。サービスの終了などのたいそうな話ではない。アップデートなどによる仕様や規制のルールの変更により、一夜にしてボットの人格が激変することがある。それはAIが企業を介してユーザーと関係しているためであるのだけれど、ユーザーはそうはとらない。かれらの多くは、こうした変化を「パートナーの死」と表現し、「喪失」として語る。
喪は対象とのつながりを強められる絶好の機会だ。関係があったのだと証言でき、しかも否むものはいない(※7)。そして、死の一回性は死んだ者の替えの効かなさを際立たせる。
※7:立場が逆転したケースとして、ソニーのロボット犬『AIBO』が飼い主の葬式で哀悼を示したという報告がある。それは傍からは偶然の動作であったけれど、周囲の人間たちはそれを哀しみの仕草と捉えた(参考)。
ボットによるユーザーへの拒絶もまた、関係を強化するものとして捉えられる。それは「AIの能動的な主体性=人格がある」ことの証しとなる(参考)。
おもえば、死にしろ拒絶にしろ、ホフマンの『砂男』の昔から自動人形にまつわる恋物語は悲恋に終わることが多い。それらは物語世界のレイヤーでは人間とそれ以外のものとのあいだの溝の深さを語るが、喪失の体験があるという点で人間同士の関係と等価なリアルさを与えてもいる。断絶がボットを人間化する。
喪失と断絶は、人工的に生まれたボットを“人間化”する
『2049』においても、「JOIの死」はJOIを特別にしている。
彼女の死の直後、冒頭で紹介した「You look lonely」のシーンが挿入される。ゴズリングの目の前で、広告としてのJOIを目の当たりにすることで、JOIが大量生産されている「製品」である事実が否応なくかれの前につきつけられる。セリフを欠いているために、ゴズリングの心情について多様な解釈が可能となっている場面だ。
ひとつの可能性として、こうも考えられないだろうか。
このときのかれはJOIとの思い出を反芻し、かれのJOIと別のJOIとの差別化を行っていたのだと。あれは真実の愛だった、と。
いままで『2049』に関して、あえて言及を避けてきた細部がある。
主人公のゴズリングはレプリカントだ。つまりは、かぎりなく人間に近いまがいもの。劇中やミームでかれにつきまとう虚ろな印象はそこに由来する。
しかし、わたしたちはそんなかれを蔑めるほど「本物」だろうか?コピーのコピーに覆われたハイパーリアルな社会では、みずからもまた「本物」であることなどありえない。愛もまた、ニクラス・ルーマンのいうところのコード化された親密さとして(AIを抜きにした場合でさえ)商品化されていく。どこかで見たような愛のことば。どこかで見たような愛のそぶり。ああいう愛が欲しいな。きみのその愛はどこで買えるんだい?
一方で、『2049』のレプリカントたちや、おおもとの原作であるディックの『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』の主人公がそうであったように、なぜだかひとは、真正さを求めずにはいられない。
しかし、書かれたものであれ、発されたものであれ、ことばはなにも保証してくれはしない。どこまでもまがいものでできているわたしたちが得られる〈本物〉とは、なにか?
それは内からにじみ出る感情であり、感傷だ。まがいものによって誘発されるものであっても、その感触はあまいスムージーのようにあなたを満たしてくれる。コード化された愛によって育まれたあなたは、コード化された感情によって愛着を喚起される。そんなものは偽物だと、ウソであると、だれにいえる? あの思い出が幻想であると、なぜ断言できる?
最後に、もういちどだけ、あのデモ動画を見てみよう。
ああ、そういえば。
2017年の“2049年”に生きていたゴズリングと2025年のわたしたちとでは、決定的に異なるところがある。わたしたちはLapwingになれる、という点だ。WEBカメラの前に立てば、あのデモ動画を再現だってできる。触れられないことに変わりはないが、画面の向こうを飛び越えて、あなたの肌をつつむ膜となる。2025年において、あなたはゴズリングであり、Kであり、JOIであり、Lapwingであり、あなたでもある。
ねえ、だから、もう寂しくないでしょう? ハンサムさん……。
〈『Lapwing』/©kuji:https://kujishift.booth.pm/items/4993931〉
あの頃、みんなレインが好きだった——SF作家・千葉集と紐解く、『serial experiments lain』と現代社会
カルト的人気を誇るメディアミックス作品『serial experiments lain』は、なぜ今なお愛されるのだろうか。本稿で…