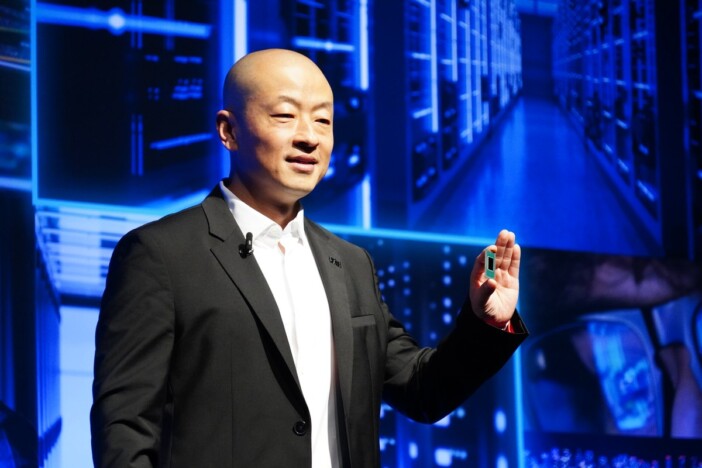『ノロイカゴ ゲゲゲの夜』に原作キャラクター不在のナゼ IPホルダーの姿勢に感じる“前例”への反骨心
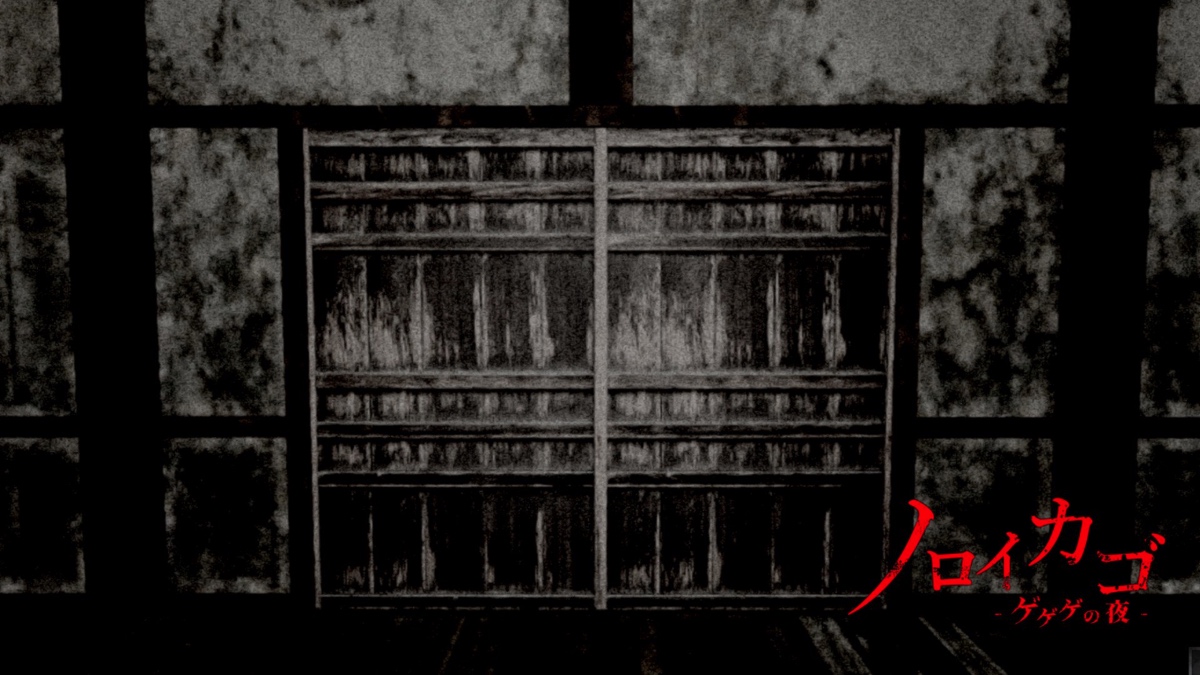
東映アニメーションは1月23日、『ノロイカゴ ゲゲゲの夜』(以下、『ノロイカゴ』)のアーリーアクセスを開始した。
人気マンガに着想を得たメディアミックス作品でありながら、原作からの影響を感じさせない同タイトル。なぜ『ノロイカゴ』は独自の路線で制作されているのだろうか。その背景を考察する。
『ゲゲゲの鬼太郎』を原作とする協力型脱出サバイバルホラー『ノロイカゴ ゲゲゲの夜』
『ノロイカゴ』は、東映アニメーションとトイジアムが開発/発売を手掛ける、オンライン協力型の脱出サバイバルホラーだ。プレイヤーは、恐ろしい妖怪が徘徊する領域のなかで、他の3人の参加者と協力しながら、自らの体を蝕んでいく半妖化の呪いの解除と、エリアからの脱出を目指していく。
タイトル名からもわかるとおり、原作となっているのは、水木しげる氏による妖怪マンガ『ゲゲゲの鬼太郎』。しかしながら、ゲーム内には、同作を連想させる主要キャラクターがほとんど登場しない。「既存のIPの利活用に焦点を当てたプロジェクトでありながら、本来は肝心要であるはずの人気キャラクターを前面に押し出さない」。そのような異色のバックグラウンドを持つタイトルが『ノロイカゴ』である。
今回、配信に至ったのは、製品版のローンチに先立ち、広くフィードバックを収集する目的で展開される早期アクセス版。公式によると、今後は2月上旬に大型アップデート第1弾として「新たな妖怪の追加」を、3月に大型アップデート第2弾として「新たな妖怪/新ステージの追加」を予定しており、さらに4月にはキャラクタースキンをダウンロードコンテンツとして販売する計画だという。
対応プラットフォームはPC(Steam)で、価格は1,480円(税込)。正式リリースの時期は、現時点で未定となっている。2025年2月5日までの期間には、早期アクセス版の配信を記念した20%オフセールも実施中だ。
ゲーム業界で広がる既存IPの利活用の動き

ゲーム市場では昨今、「既存IPの利活用」が重要なキーワードとなりつつある。ソフトウェア制作の領域では、“往年の名作”に位置づけられたIPを復刻させるムーブメントがトレンド化。1年間の総括といったタイミングで、そのようにして生まれた作品が成功の象徴として取り上げられるケースも珍しくなくなった。
一方、新作においては2024年、ソニーインタラクティブエンタテインメントによるアクションアドベンチャー『アストロボット』に、(本来は関係がないはずの)同社の歴史を彩ってきた人気キャラクターたちが“客演”したことも話題に。この例もまた、形は違えど、「既存IPの利活用」という枠組みにくくられるアプローチだろう。
また、上記以外では、2024年10月、京都府・宇治市に開業したゲーム博物館『ニンテンドーミュージアム』も好例であると言える。「任天堂の関連製品などが展示される2階部分」と「それらをモチーフにしたアトラクションが設置される1階部分」の2フロアからなる同施設は一貫して、同社が135年以上もの歴史のなかで世に送り出してきたさまざまなIPの、新たなコンテンツ化に取り組んでいる。開業までの動向には、ゲーム業界以外からも注目が集まった。
無論、こうしたIPをめぐる取り組みは、いまだけに限らず、昔から行われていた。人気や高評価を獲得した完全新作における、続編やスピンオフの制作、シリーズ化、メディアミックスなどはその一例だ。しかしながら、近年でさらに加速しつつあるのもまた事実である。ここには「(当然、両軸で取り組まれていくべきである前提のうえで)強力なIPを新たに創出するよりも、保有するIPを上手に利活用するほうが効率的である」という考え方の影響もあるのではないか。
ノベル/アドベンチャーの分野では、ビジュアルアーツ(keyブランドの母体)や5pb.(『STEINS;GATE』に代表される「科学アドベンチャー」シリーズの開発/発売元。現MAGES.)、ニトロプラス、アクアプラスといったキープレーヤーたちが、別の大手企業グループに合流するなど、業界の再編が進んでいる。一連の報道のなかで当該する両社の代表が揃って口にするのもまた、「IPの創出」「IPの利活用」という言葉だ。ゲーム市場で成功を掴み取ってきた企業にとって、「保有するアセットの再コンテンツ化」は目下、最重要のテーマなのかもしれない。今後しばらくのあいだは、こうした流れが続いていくはずだ。
なぜ『ノロイカゴ』には『ゲゲゲの鬼太郎』の人気キャラクターが登場しないのか

本稿で扱う『ノロイカゴ』もまた、こうした枠組みのなかで制作されたタイトルであると考えられる。しかしながら、業界にある他の事例と異なるのは、原作の影響を名称以外の部分にあまり感じないという点だ。
同様の座組で展開される作品では得てして、原作に登場する人気キャラクターたちが、そのゲームデザインやビジュアルにおいても重要な役割を果たしてきた。少なくともメディアミックスの界隈では、原作に含まれる訴求力の高い要素を展開先にも流用することが「IPの利活用」であると考えられてきた節がある。
なぜ『ノロイカゴ』には、『ゲゲゲの鬼太郎』からのキャラクターがあまり登場しないのだろうか。そこには、同作の権利を持つ東映アニメーションの「原作を大切にする姿勢」「ゲーム制作に対する真摯さ」を垣間見ることができる。

先述したように、人気IPのゲーム化では、原作のキャラクター人気に頼った制作が慣例となっている。このようにして生まれた作品は、発売前には話題を集めながらも、最終的には“キャラゲー”(ゲームそのものの本質的な楽しさよりも、登場キャラクターの魅力を堪能することに重きが置かれるタイトルの総称。侮蔑的な意味でも使われる)の評価に落ち着いてしまうケースが少なくない。ゲームカルチャーに詳しいフリークであれば、いくつかの例に思い当たるのではないか。このことが原作、さらにはゲーム化という動きそのものの意義を貶めている場合もある。
『ノロイカゴ』には、こうした“悪しき前例”に対する反骨心のような気概を感じる。「IPから得られる利益をただ最大化するのではなく、ひとつのゲーム作品として評価されるものを作りたい」。そのような想いを東映アニメーションが抱えていたからこそ、同タイトルには『ゲゲゲの鬼太郎』の人気キャラクターたちが(少なくとも現時点では)あまり登場しないのではないか。
そのように考えていくと、「『ノロイカゴ』が東映アニメーションのインディーゲームへの取り組みのひとつとして打ち出されていること」「アーリーアクセスという段階を経て正式リリースを目指していること」にも一貫性が見えてくる。ゲーム制作に対する同社の並々ならぬ情熱を形にしたゲーム作品が『ノロイカゴ』であるとも考えられる。

はたして『ノロイカゴ』は、そのような想いに見合うだけの評価を得られるだろうか。もしも成功と言えるだけの結果にたどりつくことができれば、「原作を大切にする姿勢」は、業界のトレンドに一石を投じるマインドとなる可能性がある。一定の評価へとつながった暁には、ひとつの伸びしろとして原作の人気キャラクターが登場する未来もやってくるのかもしれない。
2025年1月27日時点で、『ノロイカゴ』には40件ほどのユーザーレビューが寄せられ、約8割が「好評」と評価している。まずまずのスタートを切ったと言える同タイトルと東映アニメーションの、今後の快進撃に期待したい。
『エンダーマグノリア』の注目点は「一貫性」と「新作らしさ」 “苦渋の決断”に見る、発売元の矜持
1月23日、『ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist』が発売となった。150万本超えのヒットを記録し…