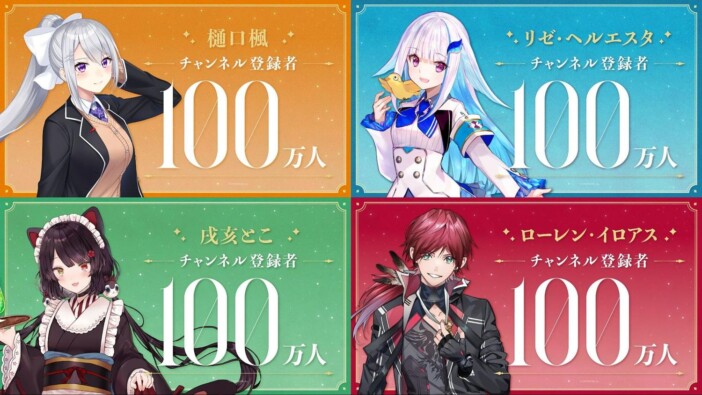未来はすでにここにある――コンサート『2024スターレイルLIVE』にみた“ものづくり”の極致

「崩壊」シリーズや『原神』などを運営するHoYoverseは、5月1日にスペースファンタジーRPG『崩壊:スターレイル』のコンサート「2024スターレイルLIVE」を全世界同時配信した。今年1月には本作のVer.2.0「ピノコニー編」がリリースされたが、このとき“オープニンテーマ”として「WHITE NIGHT」もMV付きで公開された。このMV(英語版)がYouTubeにアップされたばかりの頃、コメント欄には「HoYoverseは音楽会社のわりに素晴らしいゲームを作りますね」と洒落た称賛も見受けられ、それにはサムアップも多くつけられていた。
この称賛がもはやまったくジョークにならないほど、今回のコンサートは別次元のクオリティに結実していた。これまでにHoYoverseが開催してきたコンサートの集大成、それはゲーム音楽のライブだけでなくエンターテイメント、またはものづくりとしての極致である。その世界観の再現力は、さながらSF作家ウィリアム・ギブスンの名言「未来はすでにここにある、ただ均等に行き渡ってないだけだ」を彷彿とさせる。
カフカと三月なのかの3Dモデリングと共に各々のテーマソング「ドラマティック・アイロニー」と「ハイ、チーズ!」が初っ端から披露され、会場を沸かせた。ボルダータウンのBGM「喧騒」ではゲームの重要なファクトであるゴミ箱たちがステージ上で小競り合いを見せ、仙舟「羅浮」編のイベントテーマソング「水龍吟」では文字通り“海が割られた”。ステージ前に並べられた噴水装置が水のカーテンを作り、名場面を再現してみせる。『崩壊3rd』からHoYoverseが手掛けるコンサートを何度か見てきたが、ゲーム内の現象が有観客の舞台上でこれほど忠実に表現されたのは恐らく初めてではないだろうか。
刃のテーマソング「死兆、来たれり」ではキャラクターに扮したアクターが圧巻の剣舞を披露し、ピノコニー編の楽曲はいずれも豪華絢爛な世界観で展開された。かつてミュージカルが王道だった頃(バスビー・バークレーが台頭した1930年代〜40年代)のハリウッドを彷彿とさせるステージでは、アクターがところ狭しと駆け回る。上で言及した「WHITE NIGHT」もそういったバブリーなニュアンスを持ったダンスナンバーなのだが、その大仰なバイブスに負けないクオリティのきらめきがあった。
さらにこのピノコニー、作中屈指のディーバを擁している。物語を語るうえでも重要な“ロビン”という少女が、このコンサートでも高らかにアンセムを歌い上げた。彼女の歌唱パートを担当するChevy(「Uwu」のバイラルヒットで知られている)が、本公演で「傷つく誰かの心を守ることができたなら」、「銀河を独り揺蕩う」を続けて披露。また、この2曲は5月9日にリリースされたロビン名義のEP『INSIDE』にも収録されている。
『崩壊:スターレイル』公式がロビンについて「全宇宙で無数のファンを持つ」と打ち上げるが、彼女の楽曲はいずれもその表現に引けをとらない王道ポップスである。ヘイリー・スタインフェルドやケイティ・ペリーばりの剛速球。フィクションの中の歌姫がリアルワールドに踏み込んでくるさまは、『ONE PIECE FILM RED』のウタを想起させる。奇しくも、『崩壊:スターレイル』日本版のロビンに魂を吹き込んだ名塚佳織はウタの演技パート(歌唱はAdo)も担当している。
【キャンペーン】私のロビンプレイリスト
全宇宙で無数のファンを持つ #ロビン が、開拓者に歌を聞かせてくれます!
ロビンの曲を用意しました!イベントに参加して、今日はどの曲を聴くのか決めましょう!結果をシェアすることで、星玉×60をゲットするチャンスがあります!
【参加方法】
1.… pic.twitter.com/PB9s6JaZQf— 崩壊:スターレイル (@houkaistarrail) May 9, 2024
クリエイティブにおいて執念すら感じる近年のHoYoverse。彼らが標榜する「tech otakus save the world」のスケールのデカさは、まさにそういったものづくりに結実しているように見える。コンサートとは少し異なる角度から、この「実現力」について考えてみよう。2023年2月、中国のゲームメディア『手游那点事』が国内のゲーム会社の投資状況を報じている。同メディアは、『剣と遠征(AFKアリーナ)』などをリリースした『Lilith Games』や、3D着せ替えコーデRPG『シャイニングニキ』などを開発する『Diezhi Network』などがエンターテイメント事業に投資をおこなっているのに対し、HoYoverseの大元である「miHoYo」は先端科学に注力していることを明かしている。
『手游那点事』は同社の投資先をリスト化(2023年2月21日公開)し、「ひとつだけ確かなことは、miHoYoは現在ゲームを作っているものの、単なるゲーム会社になる気はないということだ」と指摘する。そのリストのなかには、人工知能や人間の感情をデータ化する研究をおこなう『零唯一思』や『瑞金病院脳病センター』などが含まれる。これを踏まえ、同メディアはmiHoYoの狙いについて「幻想に見えるメタバースを実現するためかもしれない」と見解を示している。人工知能と感情の定量化といえば、『攻殻機動隊』的なバーチャル空間が想起されよう。そもそも“HoYoverse”というブランド名も、没入型の仮想世界体験の創造・提供を目的として付けられたものだ。そしてもうひとつ、このリストの中で特筆すべきは、宇宙輸送ロケット開発を試みる企業「東方空間(Orienspace)」だ。
宇宙を舞台にした『崩壊:スターレイル』がリリースされたのは、『手游那点事』の記事が公開された2か月後の4月26日である。そしてHoYoverse作品の中では何度もメタバースが重要なテーマとして出てくる。ピノコニー編ではフルダイブ型の仮想空間が舞台だし、『原神』のスメール編もXRが重要なモチーフとして扱われている。すなわち、同社の作品においては宇宙もメタバースもすでに実現されているものなのだ。ギブスン氏は再度語る。「未来はすでにここにある、ただ均等に行き渡ってないだけだ」。
彼らの実現力の根源にあるのは、こういったフロンティア開拓のマインドだと思われる。「開拓者」だけに――。
……さて、コンサートの話に戻ろう。冒頭にも書いたが、本公演は間違いなくHoYoverseが提供する最高峰の音楽体験だ。しかし、それは暫定的なものだとも強調しておきたい。すなわち、まだまだ発展する余地がある。
その最大のポイントが音の鳴り方。「崩壊」シリーズにおいてはたびたびダンスミュージックがリファレンスにされるが、先に言及した「死兆、来たれり」やフォフォのキャラクターBGM「還魂の夜」は、ジャンルで言えばダブステップ~ブロステップにあたる。花火の「独り芝居」はブロステップとハードコアのハイブリッド、銀狼の「面白いじゃん」はエレクトロクラッシュといったところだろうか。
ダブステップなどは「(サウンド)システムミュージック」と呼ばれるほどに現場の音響が重要である。イベントによってはアーティストやパーティの特色にあわせて専用のスピーカーを導入するぐらい、このジャンルにおける低音の鳴り方は優先度が高い。
「還魂の夜」はその特徴が顕著で、サブベースの鳴り方はかなりダブステップ。うしろで「ブーン……」と鳴っているのがそれなのだが、システムミュージック仕様の設備で聴くと内臓が揺れるほど身体に響くのである。しかし、本公演の楽曲はどれもローが控えめだった。
念のため断っておくと、『崩壊:スターレイル』の楽曲に関わるプロデューサーの力不足を指摘したいのではない。本作でダンスミュージックをリファレンスにする場合、その多くでクレジットに名を連ねるのが文馳とTSARである。前者はダンスミュージックにオーケストレーションやシンフォニーを導入することに長け、後者はより専門性が高いアプローチをとる。TSARは2010年代に同郷のChace(Yellow Clawと共作したことで世界的にブレイク)などと並んで語られており、ベースミュージック系のプロデューサーとしての実力に疑いの余地はない。
ちなみに今回のコンサートでは披露されなかったが、この2人が共作者としてクレジットされているのがDr.レイシオの「愚の骨頂」である。
では、なぜ低音が抑えられていたのか? 推察するに、本公演がトータルアート的なゲーム音楽のコンサートだったからだろう。ダンスミュージックはその名が示す通りフィジカルな音楽ジャンルだ。リスナーの肉体にどう干渉するかが重要なポイントなのだが、それゆえに調整が難しい。しかもDJの場合はPAとコミュニケーションを取りながら最善を目指せるが、本公演はオーケストラのほか大量のアーティストがステージ上で音を鳴らす。
つまり、クラブやライブハウスなどでは音作りに関して綿密なやり取りが可能だが、この規模のコンサートでは最大公約数的なアプローチが関の山だったのだろう。いかに精鋭が集まっても、それだけの人数が一堂に集結すれば不確定要素は増えてゆく。
しかしこの手の課題は時間と経験が解決する。場数をこなせばこなすほど知見がたまり、最適な音作りに辿り着くはずだ。ジャンルは違えど、UKの御大Sashaなどはオーケストラを率いたライブを成功させている。黄泉の「君の色」が今回よりもド迫力で体験できる環境になったら、もはやとんでもない領域に突入してしまうだろう。以下の楽曲も、TSARが手掛けている。
そして、このダンスミュージック方面への進化は、恐らく『原神』にも期待できる。2023年、ひとりのプロデューサーがHOYO-MIXのチームに参画した。それが、エレクトロニック・ミュージックを得意とする路南だ。これまで映画やテレビのサウンドトラックを手掛けたほか、自身の名義で「300 Spartans」などをリリースしている。
『原神』の楽曲としてはフレミネの「寒晶の夢」、リオセスリの「霜烈の競争」、そして呑星の鯨戦のBGM「カタストロフの残影」などは同氏によるものだ。作家性に一貫性があり、ディレクター目線では大変発注がしやすそうである。筆者はアルレッキーノ(召使)の実践紹介BGMも路南によるものと見ている(違ったらすいません)。
こういった一連の楽曲が『崩壊:スターレイル』、ひいては『原神』のコンサートで聴けるかもしれないと考えると、明日も頑張れそうではないか?
発展途上とはすなわち、いまの余白に夢を託せるということだ。そろそろしつこいと思われそうだが、三度ギブスン氏の言葉を。
「未来はすでにここにある、ただ均等に行き渡ってないだけだ」
〈Source〉手游那点事
http://www.nadianshi.com/2023/02/339898
© COGNOSPHERE
いまこそ“開拓の旅”に飛び込もう! 1周年を迎えた『崩壊:スターレイル』の魅力とは
HoYoverseが開発・運営するスマホ/PC/PS5向けスペースファンタジーRPG『崩壊:スターレイル』は、4月26日に1周年…