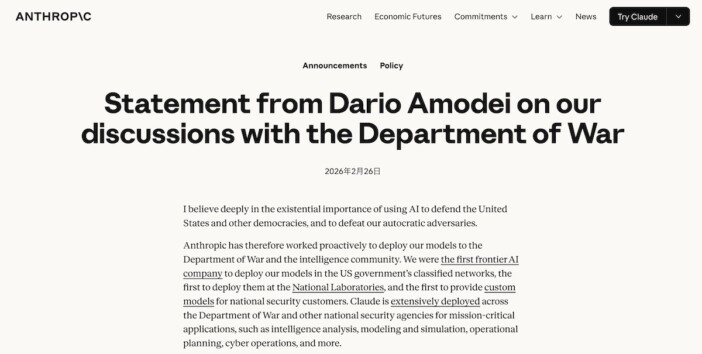SFドラマ『三体』のVRデバイスは実現できるのか “没入体験”の歴史と現在地から考える

Netflix版『三体』のVRデバイスは厳しそう でも原作やテンセント版なら……?
そうして、われわれの手元には装着すればバーチャルな世界に飛ばしてくれるHMDがいつのまにか、ある。Netflix版『三体』のメタリックなそれよりいくらかゴツいものの、十分にポータブルでスマートだ。
なにより、1990年代初頭のVRブーム時代にVR用のHMDを試したいとおもったら、大学かNASAのような機関に研究者として出入りするか、パナソニックの運営するショールームに予約を入れて一ヶ月以上待つしかなかった(『MMR マガジンミステリー調査班』第3巻のキバヤシは電話一本で即体験できたが)。今日、三万円そこそこで買えるHMDはその時代のデバイスよりずっと安価でお手軽で高性能だ。

とはいえ、Netflix版『三体』のオーバースペックぶりには程遠い。ここからNetflix版『三体』のVRグラスまでの距離は、200年前のホイートストンのステレオグラスからここまでの距離よりもはるかに隔たっている気がする。
ところで、さきほどからNetflix版、Netflix版としつこく連呼している。「Netflix版じゃなかったら、実現可能だとでもいいたいのか」と、そう思われるだろう。実は、可能かもしれない。
劉慈欣の手による原作『三体』では、VRのデバイスまわりはこんな描写がされている。
Vスーツは、いまゲームマニアのあいだで大流行しているインターフェイスで、ヘルメット型の全方位ヘッドマウントディスプレイと触覚フィードバック全身スーツで構成されている。全身スーツは、ゲーム中の感覚刺激をプレイヤーに伝える。こぶしで殴られたり、刀で切られたり、炎に焼かれたり。酷暑や厳寒も体験できるし、肉体が風雪にさらされる感覚までリアルに再現する。
[劉慈欣・著、立原透耶・監修、大森望 ・訳、光吉さくら・訳、ワン・チャイ・訳『三体』早川書房]
HMD+触覚を再現するハプティック・スーツ。原作が連載された2000年代後半には、この取り合わせはわりあいリーズナブルだった。
HMDはもちろん、ハプティック・スーツの発想も昔からあるもので、最も早期に実現したVR技術のひとつであるフライト・シミュレーションにおいては飛行服を加速度などに応じて空圧をかけていたし、1994年には音響信号から推測されるビデオゲーム内の衝撃を現実の振動に変換するスーツ、『Aura Interactor』(Aura Systems社)がアメリカで売り出され四十万台以上を売り上げていた。
また、現在では神経筋電気刺激で圧覚を得られるスーツも市販されている。

原作『三体』での「Vスーツ」も、物体それぞれの質感はある程度まで振動周波数の違いで再現しつつ、備わっているらしい温度調整機能で「こぶしで殴られたり、刀で切られたり、炎に焼かれたり。酷暑や厳寒も体験できるし、肉体が風雪にさらされる感覚までリアルに再現」しているのだろう。美麗で迫力のある映像によってクロスモダリティ(ある感覚へ訴える情報から、他の感覚に関する情報も補完する効果)も生じているかもしれない。
ちなみに中国で2023年に配信されたドラマ版『三体』(通称、テンセント版)では、『KATWALK』という実在するデバイスが登場している。これは円形のルームランナーと重心固定用のハーネスを組み合わせたような歩行用VRデバイスで、有り体にいえば、映画『レディ・プレイヤー1』に出てきたアレだ。
テンセント版では原作の全身スーツは着用せず、指先にハプティック・グローブをつけている。