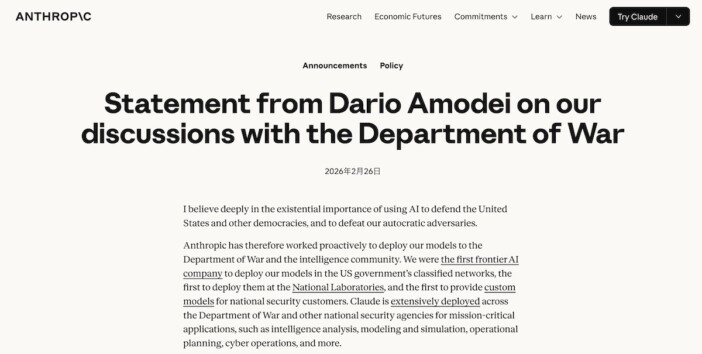自粛で“勝ち組”になったガジェットはどこに向かうのか? 『東京ゲームショウ2023』で感じたこと

ガジェットの潮流

ここからは今回の取材で筆者が感じた、ガジェットの傾向について記述する。
ファンビジネス化するガジェット
プロゲーマーとのコラボ、有名ストリーマーのアンバサダー起用がより活発になっている印象を受けた。
「性能や便利さ」で大きな差がつかないデバイスは、価格競争になりがちなので、価格を維持したい企業は「人や文脈」で売ることになる。
(コロナ禍での立ち回りで)良くも悪くもゲーム配信者の勝ち組と負け組が決まり「広告に使えるストリーマー」という存在が、合意形成されつつあるのも、企業がプロゲーマーや配信者を使いやすくなった背景だろう。
ファンビジネスを推進していきたいプロゲーミングチーム側にとっても、この流れは吉報である。
各ゲーミングチームは、賞金やスポンサー料以外のマネタイズの柱として、DtoCのファンビジネスに舵を切りつつある。
プロゲーミングチーム側としても、有名企業と共同制作のガジェットは、ファンビジネスの第一歩でもあるため、都合の良い話なのだろう。
将来的には化粧品のように、1つのブランドに1人のゲーミングアンバサダーがつくのが当たり前になるかもしれない。
使うモノから見せるモノへ
ゲーム配信という文化の一般化、SNSの普及に伴い、ゲーミングデバイスを中心としたガジェットは使うモノではなく、見せるモノになってきたといえる。
実際、会場で見かけたガジェットの多くは、機能面だけでなくデザインに力が入れられているのを感じた。
実用性だけでなく、見た目の格好良さや可愛さへの追求がされているのが近年の傾向である。
見せるモノの代表である産業といえばファッションであるが、ファッション業界で起きていることに「価格の二極化」「中間層の消失」が挙げられる。
これは、中途半端な価格のファッションは売れなくなり、極端に高価な高級ブランドか安価なファストファッションだけが勝ち組になったことを示している。
見せるモノとなったガジェットも、やがてはファッションのように「価格の二極化」「中間層の消失」が進むのかもしれない。
さいごに

ダウンロードやサブスクリプションサービスの普及により、ゲーム、音楽などソフトについては、基本的には無料に近い形で手に入るようになった。
ソフトにお金が掛からない時代において「どこにお金を使うか」がハードやデバイスに向かっているように感じた。
「コロナ禍で、ゲーマーのすそ野が広がった」「外出自粛期間が長引いたことで、ライトゲーマーからコアゲーマーに移行した」というのは、大方の見方であり、ゲーミング市場の伸びを見てもそれは明らかだろう。
コロナ明けで3年ぶりのオフライン開催となった、昨年の『東京ゲームショウ2022』の会場でも、その勢いは肌感覚で感じられた。
ここで注目すべきは、1年たった今回もその勢いは衰えていなかったということだろう。
池袋マルイは閉店、渋谷マルイは一時閉業、2023年には業績不振の「そごう・西部」が池袋西部百貨店を売却。新宿マルイアネックスも休日昼間にも関わらず閑古鳥が泣いている。
大手ファッションビルや百貨店は自粛期間を空けてもなお、厳しい状況が続いている。
令和4年3月で時短営業協力金の申請が終わり、店を閉める飲食店も目につくようになった。
「コロナが明けても、客が戻ってこなかった」といわざるを得ない。
自宅やオンラインの活動に寄与するガジェットの勢いは、これからも増していくだろう。
デバイスがFPSの実力を左右する? 話題の「ラピッドトリガー」の実力を『REALFORCE GX1 KEYBOARD』でチェックしてみた
昨今、ゲーミング界隈ーーとりわけ『VALORANT』を始めとする一部のFPSタイトルのプレイヤー間で話題になっているキーボードの…