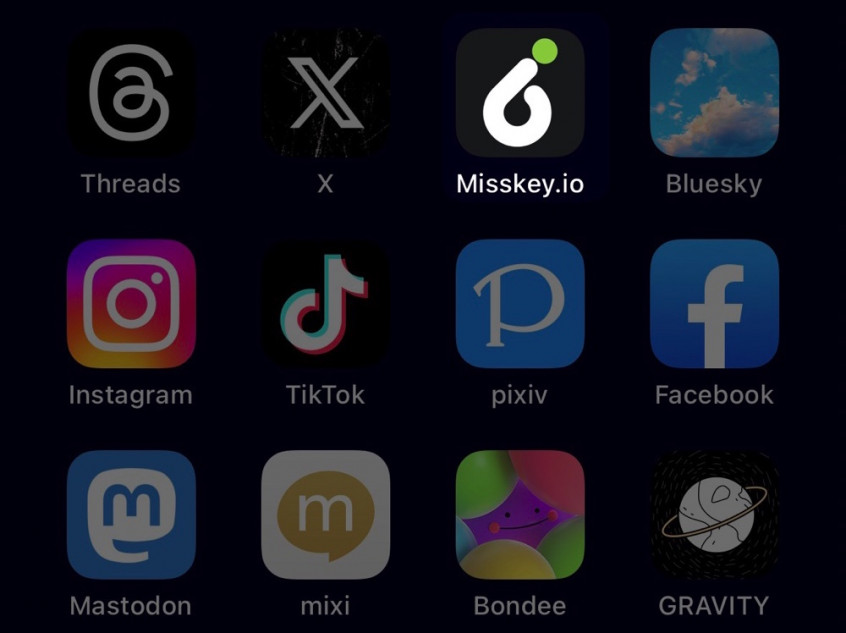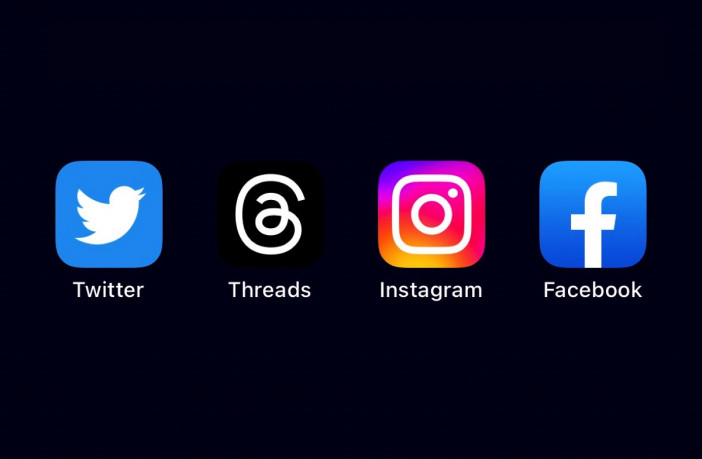目指すのは「オタク向けmixi」「平成のインターネット」……? ユーザー爆増の純日本産SNS『Misskey』開発・運営インタビュー

すべてはユーザーのために 「Misskey.io」が目指す“理想の姿”
ーーMisskeyは今後どのように進化・発展していくのでしょうか。
syuilo:さまざまな「ポスト・ツイッター」サービスが注目されているなかで、Misskeyとしては「ニッチを埋めるサービス」になれると良いのではないかと考えています。Xの規制が強まっている影響もあり、Misskeyのユーザー層としてはIT技術者やイラストレーター、コンポーザーといったクリエイターがとても多く、今後も自然とそういった住み分けがされていくものと思います。具体的にどのようなコミュニティを作るのかは各インスタンスの運営者次第ですが、開発者としてはXやThreadsと同じようなものを作っても面白くないので、「Misskeyにしかない特徴」を突き詰めて、Misskeyの魅力を高めていきたいです。
村上さん:同じく、いまMisskeyを楽しんで使っているユーザー層、つまり技術者やイラストレーター、同人作家、VTuberとそのファンの方々が、もっと快適に楽しく過ごせる場所になればいいと思っています。少し乱暴に言うなら「オタク向けのmixi」といった感じでしょうか。ThreadsやInstagramの客層とは違う部分です。「Xの代替になるか」と言うと、我々はそれを目指してはおらず、「ユーザーにとって楽しい場所を作る」というのが目標です。
それは「こういう傾向のユーザーに来てほしい、使ってほしい」という意味ではなくて、現状のユーザーの傾向やコミュニティを尊重しながら、それに合わせて進化していきたいということです。

ーーSNSはユーザーの利便性の視点から見ると「巨大であること」自体に価値があると思いますが、同時にXやFacebookの歴史を見ていると、SNSが巨大になることでいろんな問題が露見しています。対してSNSでは、コミュニティを育むことや、自分の求めるコミュニティを選んでそこに所属することができますよね。総合すると、SNSというのは「巨大であること」と「コミュニティを育む機能」をいずれも求められていて、これは相反する性質を持っています。運営者から見て、この相反する性質に対してどういった形をとるのが望ましいのか、考えをお聞きしたいです。
村上さん:その点ではXは途中までとてもコントロールが上手だったと思っています。Xにはものすごい数のユーザーがいるのに、興味関心が近いユーザーを「おすすめ」に出してくれる。要は大量のユーザーが居る中で「自分が好きそうな人たち」をユーザーに提案していくことで、コミュニティをさらに細分化して、独立させていくことができるんです。あの仕組みは問題を抱えつつも、「大量のユーザーの中でコミュニティを育む」という点で画期的で、我々もいずれあれをやらなきゃいけない日が来ると思っています。
現在その先駆けとして実装しているのが「チャンネル機能」です。これは連合していない(Fediverseに参加していない)ioだけで完結するつながりなのですが、トピックを作ってそのチャンネルの中で会話をする仕組みです。これによって、今までローカルタイムラインだけで行われていた会話がチャンネルの方にシフトして、話題に対して投稿した人たちが小さな単位で集まってコミュニケーションできる。

ーー閉じたコミュニケーション、小さなコミュニティを作れる機能ということですよね。同時に、「巨大になること」も必要だと考えていますか。
村上さん:規模が大きくなることはユーザーが選べる選択肢が増えることなので、それは良いことです。Misskeyの強みとして「ローカルタイムライン」という、全ユーザーの投稿が爆速で流れるタイムラインがありますが、これを今後整理をして利便性を高めようとしています。それと先ほど紹介したチャンネル機能を併せて使って頂きたい。開いていくことと閉じていくことを並行でやっていくことによって、オープンでありたい人・クローズでありたい人、両方の受け皿になりたい。
ioが目指している姿は、「平成のインターネット」に近いかもしれません。インターネットの面白さって色んな情報が流れていて、中にはちょっと汚い情報もある、そういう雑多さにあると思うんです。楽しいインターネットを維持していきたいし、そのためには汚さとか雑さって、絶対に必要なんですよ。でもふつうのユーザーの心情からすると「汚いのって嫌」ですよね。それも普通の話です。なので情報を制御すること、ユーザーの求める投稿が流れるような仕組みをつくることは必要だと思っています。実は投稿内容をネガポジ判定するような仕組みを今作っている最中で、これはユーザーがネガティブな投稿を見ないように設定できるんですが、オン・オフできるようにするつもりです。見たいユーザーは見れば良い。
ーーMisskeyやioがユーザーに強力な支援を受けているのは、ユーザーと運営者の間に信頼関係があり、コミュニケーションが上手く行っているからだと感じますが、ソフトウェア開発やサービス運営においてこうした相互関係が生まれるのはレアケースで、「フリーウェア開発者がユーザーの期待を無料で背負って困窮する」というように、コストの問題が大きな壁になることが少なくありません。とはいえ企業が運営すると、Xのように「巨大化したSNSがCEOの個人的な振る舞いで激変する」こともある。中央集権的な運営、分散型の運営いずれにも存在する課題を解決するアイデアがあれば伺いたいです。
村上さん:いまのところ、ないと思います。結局、選択肢にはどちらにも問題があってどちらを選んでもデメリットがついてくる。正直な話をすると、Xが今後さらに使いにくくなったとしても、ユーザーが居なくなることはないと思うんです。現状でもXのユーザーは、少なくともMisskeyのアクティブユーザーの100倍以上居て、名前がXになろうと、イーロン・マスクが好き勝手しようと、影響を受けるユーザーというのは極少数なんです。そこに対して「どうしても嫌だ」っていう人は、勝手に違うところに行くんですよね。それが分散型SNSで起きているだけの話で、たとえば村上さんっていうキャラクターがioで「明日から言論統制を始めます」とアナウンスしても、多分残るユーザーは残るんです。課題があったら人はそれを変えようと思うし、嫌だと思った人は離れていく。自分のいる場所を選べるわけですから、ユーザーの視点からすれば悪いことだとも思わない。
加えて開発者がコストを払うことも解決できない。なので分散型SNSという理念がポジティブに発展していくことはかなり難しいと思います。効率が悪いという話は先ほどもしましたが、これは技術的な効率だけではなく、お金の動き方も効率が悪い。たとえばXのCEOが変わって、これまでの改変を全部もとどおりにして、「Xをもとに戻すので寄付をください!」って言ったら多額の寄付が集まると思うんです。
同じことが分散型SNSで起きたらどうなるかというと、投稿が分散してしまうのでお金が集まらない。もしioっていう大きなインスタンスが今日いきなり無くなったら、ユーザーはさまざまなインスタンスにバラバラに散らばってしまう。散らばった先のユーザーがそれぞれのインスタンスに支援を行っても、大した金額にはならないですよね。だったら「ioという大きなインスタンスを支援すれば採算も取れて、スパムもブロックしてくれて、さらに使いやすくなっていく」っていう世界観のほうがユーザーにとっては快適だと、現状ではそう考えています。
ーーioに関しては一貫して「ユーザーファーストで使いやすく、楽しい空間を作ること」を大事にしているということですね。
村上さん:今日は最初から最後までずっとそればっかり言っていますね(笑)。どんな課題について考えても結論はそれです。ユーザーに楽しんでほしい。今のルール、今のスタンスでずっと続けたい。それを変えることについて考えるのは、たぶん登録者が100万人を超えたあたりなんだと思います。そういう数になると、いよいよ投稿を捌けなくなって、細かいルールを設定する必要も生まれると思うんですが、現状は困っていないので、困るまではこのままでいきたいです。
ーー最後に、今後実装を予定している機能や、Misskeyに興味を持っているユーザーに伝えたいことはありますか?
村上さん:今は嬉しいことに、Misskeyのコアユーザーに、クリエイターの方がとても多い。作曲家さんやイラストレーターさんなどがたくさんいらっしゃる状態なので、こうした層のユーザーが喜んでくれる機能を実装したいと考えています。VRやメタバースといった領域で活動する方もたくさんいるので、こうした領域に明るいユーザーの方もぜひ一度Misskeyで、ioに遊びに来てください。
syuilo:最後になりますが、興味があればぜひMisskeyを使ってみてください。Misskeyを通じてFediverseに触れ、「今後メジャーになるかもしれない」インターネットを体験していただければと思います。
分散型SNSはTwitterの後継足り得るのか? 僕らがSNSを使う理由とともに考える
ツイッターのように短文を投稿してやり取りする非営利のSNSソフトウェア『Misskey』が脚光を浴びている。イーロン・マスク氏が…
■関連リンク
「Misskey Hub」
「Misskey.io」
syuilo氏公式Misskeyアカウント
村上さん公式Misskeyアカウント