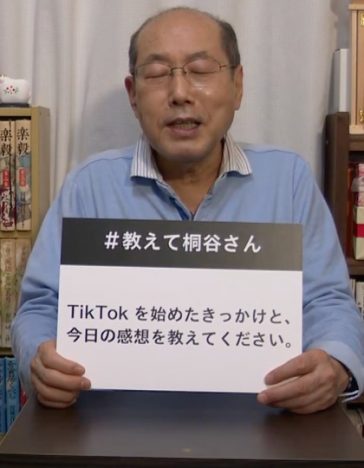伊吹とよへに聞く、TikTokクリエイター“ブレイク後のキャリア”って? ラジオ・アパレルと活躍広げる2人の挑戦

今やTwitter、Instagram、YouTubeと並ぶソーシャルメディアとなったショートムービープラットフォーム『TikTok(ティックトック)』。そのなかでオリジナリティ溢れるコンテンツを発信し、人気を博しているTikTokクリエイターがいる。マルチクリエイターコンビの伊吹とよへだ。
彼らはSNS総フォロワー数220万人を超えるマルチクリエイターで、独特な声色とメロディが癖になるドッキリムービー「イブ検証」や、映画・アニメーションをモチーフにした動画で一躍有名に。現在はPodcast番組『伊吹とよへ ラジオみかん』(ニッポン放送)でパーソナリティーに挑戦し、アパレルブランド「Udeal」をプロデュースするなど、ますます活躍の場を広げている。そんな伊吹とよへに、これまでのキャリア形成で工夫してきたことや今後の展望について話を聞いた。(Nana Numoto)
【記事の最後に伊吹とよへさんのサイン入りチェキプレゼントあり】
心がけているのは“全ての投稿に凝らない”こと
――まず、お二人がクリエイターになるまでの経緯を聞かせてください。

伊吹:小さい頃から、有名になりたいと思っていて、小学校の時に作文でもそう書いているくらいでした。その後、高校の時に芸人を目指して、オーディションに行ったら初めて心が折れて。本当に面白い人だらけで、もう勝てないと思いました。そこからは佐藤二朗さんやムロツヨシさんみたいなコメディ俳優を目指し、エキストラなどで撮影に参加していました。その時に周りがどんどんSNSで活躍していて「なんで俺はSNSをやってないんだろう」と思ったことがきっかけで、クリエイターの道を歩み始めたんです。
――よへさんは、いかがですか?
よへ:僕は伊吹に誘われてTikTokを始めました。人を笑わせるのは好きでしたが、伊吹のように小さい頃からの夢ではなかったですね。大学3年生の時にカナダに1年間の予定で留学をしたのですが、半年経った頃に伊吹から突然電話がかかってきて「よへ、一緒にやらないか」と(笑)。
伊吹:ちょっと違うぞ!(笑)
よへ:(止まらず真剣な顔で)「お前のおもしろさが、いま必要だ」というような熱い電話だったので、引き受けました。伊吹とは高校の最後の辺りから大学でも同じ学部で、ずっと仲が良かったんです。二人とも友達グループの中では“面白いキャラ”でしたが、直接「お前、面白いな」と言われたのはその電話が初めてで。その言葉が嬉しかったので、一週間後には帰国を決意しました。でも、その時にはすでに伊吹のTikTokアカウントのフォロワーが20万人ぐらいいたんですよ。この船には乗るしかないと思いましたね。

――途中帰国をして、周りから反対されたりはしませんでしたか?
よへ:やっぱり、親はびっくりしていました。1年後に帰ってくるものが半年で帰ってきているので。でも、自分は完全に決意が固まると突き進んじゃう猪突猛進タイプなんです。結果が出るようになってからは、親も認めてくれるようになりました。
――TikTokのフォロワー数がとても多いですが、日々の投稿で伸び悩んだ経験はありますか? 多くの人がSNSで有名になろうと思うと、必ず当たる壁だと思います。
伊吹:僕たちも壁には当たりますが、立ち止まって悩むことはないです。よへといつも話していますが、僕たちの動画にも全然バズっていない動画はたくさんあるんですけど、そんな動画も全て残しているので、遡ってみていただければわかると思います。とにかく動画を出せばどれかが当たると思うので、伸びてないことがわかったら、「じゃあ、次はこうしよう」と先のことを考えています。
編集部:壁にぶつかった時に、立ち止まってしまうことはないんですね。コツコツずっとできちゃうというか。
伊吹:「やばい、伸びないね」と笑っているぐらいです。「やばい!本当にどうしよう」と慌てるようなことはないですね。次は何をやるのかをいつも考えています。
――すぐに次のことを考えられる前向きさが、今の人気に繋がっているのだと感じました。努力が数値に表れなかった時にモチベーションを維持する方法や、SNSの運用でお互いに話し合うことはありますか?
伊吹:モチベーションの維持に関しては、こだわりがあります。僕らは、“全ての投稿に凝らない”ことを心がけています。本当に自分たちが自信あるものを出したからといって、全ての投稿が伸びるわけではないので。「絶対にバズる!もう命かけよう」ぐらいの気持ちで投稿していると、バズらなかった時にメンタルがもたなくなります。一つ一つの投稿にこだわりすぎず、ラフに、僕らの生活の一部を出していこうという感じですね。僕はドッキリを仕掛けられる側ですけれど、よへにはいつも企画は大きくし過ぎないでほしいと言っています。
よへ:高校生の昼休みみたいな雰囲気を大事にしつつやってますね。
――夏休みに高校生が家でわいわいしている空気感は、確かにすごく感じます。
よへ:いつも撮影しているのが伊吹の実家なんですよ。カメラマンも高校の時からの同級生で、そいつと僕がタッグを組んで伊吹にドッキリを仕掛けていて。その感じも、いつものふざけあっている関係性の延長線上なので撮影は楽しいですね。
――普通ならフォロワーさんやファンの方が増えれば増えるほど、どんどん企画の規模が大きくなっていきそうですが。
伊吹:今後の展開としては、ファンの方々のおかげでここまで大きくなれたので「皆のおかげでこういう大きなこともできるようになったんだよ」ということを伝えたいという思いはあります。ニッポン放送さんでのラジオとか、アパレルブランド「Udeal」も立ち上げさせていただきましたし、変に背伸びした大きな動画を出すのではなく、そういった部分で自分たちの活躍を伝えていけたらいいなと。
――ファンの方といい関係を築いているんですね。今の時代では、インフルエンサーやクリエイターの活動が副業を越えてお仕事になっている方も増えてきていると思います。差し支えなければクリエイターの仕事を職業として、生活していけるようになったきっかけや具体的な時期をおうかがいできればと思います。
伊吹:僕は今の事務所に入ってから生活できるようになったので、そのことに感謝しています。お誘いいただいた時に事務所の方とお話して、先方からの熱い気持ちが僕にも伝わったので、所属を決めました。当時はまだギリギリ僕ひとりでTikTokを出していましたから。
よへ:その後、僕も一緒にお世話になることになりました。最初に二人で活動した時はまだ収入が得られていなかったので、お互いに毎日ファミレスで早朝バイトをしていましたよ。朝5時とか6時から11時ぐらいまでバイトした後に伊吹の実家に集合して、とにかくいろいろ撮影していました。毎日夜まで撮影していましたね。
――飽きるとか、今日は撮りたくないという日はなかったんですか?
よへ:僕はもうカナダから帰ってきてしまったわけですし、やるしかないと思っていました。伊吹も同じ温度感だったので、そこはマッチしましたね。ちょっとでも多くやりたいぐらいでした。
――では今後の展望についてお話を聞かせてください。いずれは自身のテレビ番組を持ちたいということを、以前話していたかと思いますが、現在ラジオで『伊吹とよへ ラジオみかん』が始まってみていかがですか?
伊吹:めちゃめちゃ楽しいです。前は自分たちでラジオをやっていたのですが、その時はよへの笑い声と僕の笑い声しかなかったのが、周りにいるニッポン放送のスタッフさん方が爆笑してくださるのが快感で。もうたまんない、幸せだなぁと思っています。一緒に作り上げていくのが嬉しいですね。
よへ:いやもう、めちゃくちゃ楽しいですよ。
――ちなみに今後、ラジオ内で挑戦してみたいことや構想中の企画があれば教えてください。
伊吹:今回、コンセプトが「未完成の状態からラジオを作り上げていく」ことなので、その段階でファンの方々からメールやお便りをいただければそこに書いてくださったことに挑戦していきたいなと思っています。まだ作られていないラジオなので、逆に言うと何でもできるんですよ。読者の方もやってほしいことがあれば、ぜひ。
――伊吹さんは『MEN'S NON-NO(メンズノンノ)』のオーディションに参加された経験もありますが、今後ファッション分野で挑戦したいことはありますか? 例えば、モデルとして活動する可能性があるのかが気になっています。
伊吹:ドッキリ企画から始まってオーディションを受けましたが、最終選考まで残ってみて、憧れるモデルじゃなくて寄り添えるモデルになりたいなというのは感じました。メンズノンノのモデルさんたちはみんなすごいかっこよくて憧れですけれど、スッと隣にいるぐらいの親近感のあるモデルはまだいないなあと思って。必ずしもモデルでなくてもいいので、その世界観を表現しながらファッション分野での活動を広げていければと思います。
――ドッキリから始まったことながら、伊吹さんがオーディションの「TikTok賞」ファイナリスト10人に残るという快挙を遂げたことを、よへさんはどう思いましたか?
よへ:本当に奇跡ですよね。最終的には伊吹も本気になっていたので、そこは自分としても応援したいなと思いました。何かいい形で、相方としてサポートしていければなと思います。
――過半数が伊吹さんに投票していましたが、惜しくも……という結果でしたね。
伊吹:そうですね。やっぱり70~75%くらいが僕への投票だったので、何もなかったのが悔しいですけれど。この悔しさが今回アパレルブランドを立ち上げる原動力にもなったので、どちらでも良かったかな。悔しかったですけれど、ここまで来たら違うところで見返してやろうという気持ちもありましたから。