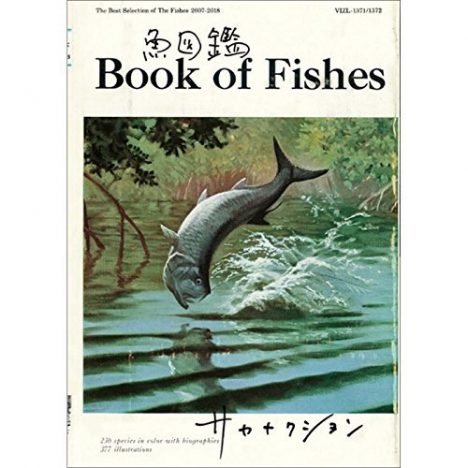サカナクション“最高峰のオンラインライブ”の裏側ーー田中裕介に聞く「ライブミュージックビデオ」の演出法

8月15日に行われたサカナクションによるオンラインライブ『SAKANAQUARIUM 光 ONLINE』。「従来のライブの制約にとらわれず、オンラインライブの表現を再解釈した生配信」とアナウンスされた同ライブでは、サウンドテクノロジー企業KLANG:technologiesによる3Dサウンドの採用がされ、映像についてもオンラインライブならではの演出、映像効果などで観る者を圧倒した。
コロナ禍をひとつの契機とした“オンラインライブ”の発展、その一つの結実を迎えたといえる今回のライブ。前回記事では、立役者「チームサカナクション」からPA・ミックスエンジニア・マスタリングエンジニアを務める佐々木幸生氏、浦本雅史氏を取材したが、今回はMV監督やライブ演出を手がける田中裕介氏にインタビュー。「ライブミュージックビデオ」と銘打った演出のコンセプトやオンラインライブであることの利点や課題まで、多岐に渡る話を聞いた。(編集部)
前半と後半で大きく分けた“照明”のコンセプト

――サカナクションとしては、元々予定していたライブができなくなったというところから始まったとはいえ、オンラインライブになったことで、演出面においてはかなり変更点があったと思います。今回の演出については、どういったところから考えていきましたか。
田中:僕は映像の専門家なので、ライブというものを映像的なアプローチで構築していくとどうなんだろう、と思ったのがスタート地点です。初期からそういう考え方でやろうと決めていたので、「ヤバい、どうしよう!」と追い込まれたわけではありませんでした。
――では、「ライブミュージックビデオ」というコンセプトはかなり早々に決まっていたと。
田中:そうですね。「二時間の生演奏のミュージックビデオを作る」というのは最初から決めていました。
――サカナクションメンバーからは、どのようなオーダーがあったのでしょうか。
田中:当初から、「無観客ライブをシンプルに撮ることは、自分たちには多分できない。テンション的にもできないし、仕上がったものとしても面白くないんじゃないか」と言われていたんです。なので、無観客ライブをオンラインで配信するより、オンラインだからできる全然違うことをやりたいと。そのうえで「外から始めたい」「スナックをやりたい」というオーダーがあったのと、中止になってしまったホールツアーとセットリストやライブの大きなコンセプトをあまり変えず、オンラインライブとしてどう再構築していくか、というテーマがありました。

――外からスタートするオープニング演出は、見ていて度肝を抜かれたところでした。様々なオンラインライブを見ていく中で、最初からステージが映されていて、そこで演奏がはじまってーーと、見ている人からすればあまり没入できないのが課題だなと思っていたので、こういう解決の仕方があるのか、と驚きました。
田中:「外から始めたい」「映画みたいな演出で」というのを考えていくにあたって、(山口)一郎くんが歩いてステージに向かっていくというストロークが映画っぽいなと。あとは、クラブなどに行ったことのある人はわかると思うんですが、音が籠っている場所に入っていく際、ドアを開けた瞬間にワッと音が聴こえる体験って、音楽好きな人にとっては輝かしい共通体験じゃないですか。映画の演出でもそういうものがよく出てくるので、それをやってみたいと。
――今回は「光」と銘打っていることもあり、照明演出が普段のライブ以上に手を変え品を変え工夫されていた印象があります。
田中:「ボイル」でメンバーを囲む壁が開いていくまでの曲は、とにかく映像的なアプローチでいこうと考えていて。照明も普段一緒に映像を作っているチームでデザインしました。そして「ボイル」以降はこれまでのライブと同じく平山和裕さんがステージ照明を作ってくれていて。映像的な照明とライブ的な照明を前半と後半でする、という大きなコンセプトがありました。

ーー前編と後編におけるコンセプトの違いは理解したのですが、照明器具などのハード面などで具体的に大きな違いはあったのでしょうか。
田中:前半では、普段ライブだと絶対置けない位置に照明を置いたりしているんです。正面から光をあてて影を見せるというのは、通常お客さんがいる位置なので絶対にできないんですよ。ライブの照明ってお客さんに対しても光を見せることによって、その点滅で気持ちを高揚させることがあるんです。ただ、映像においてはそういう考え方ってそこまでなくて、被写体にどう光を当てていくかが第一なので、狭い世界に照明をめちゃくちゃ密に配置して、いろんな表情を作れるように演出していたんです。
あと、前半は特に「光」というコンセプトをとり入れたいというのがあって。「ネイティブダンサー」に関しては、個人的に夜の都市が頭に浮かぶので、都市の光をテーマにした映像にしようと思い、車でドライブした際に流れる“街の光”を映像にしたいと考えたので、実際に車で走りながら撮影した風景を使った映像にしたり、映像がない時間帯はトンネルの中を車で走行している時のイメージで、オレンジ色のライトを走らせてみたりしました。
――そして、後半はライブに近い光の演出でした。
田中:後半はとにかくライブっぽさを意識していて、一番最初はフラットにカメラを配置してみたんですけど、それだとライブ感が出てこなかったんです。そこから撮影チームともいろいろ検討して、意図的に普段のお客さんがいる環境でのカメラアングルみたいなものを作りまいた。今回はお客さんがいないのでステージの高さを上げる必要がないんですけど、ライブを見ているお客さんの視点だと、少し見上げる形になるじゃないですか。だからあえてカメラを低い位置に置いたりしていて。前半はカメラをバンドに近づけてるんですけど、後半はあえてそんなに近づかないようにして、ずっと離れた距離から望遠のレンズで狙うようにしました。そうしてライブの疑似体験をしてもらう、というのが狙いでしたね。

――後半で山口さんがカメラに向かっていくのはライブっぽくあり、音楽番組っぽくもあるなと感じました。
田中:その演出は、前半において絶対やらないと決めていました。前半はメンバーは自分の世界に没入して、カメラも絶対見ないし意識しない。それを客観的に撮っていく風にして。そして「陽炎」以降は、急に一郎くんがお客さんとコミュニケーションを始めるという。その方が効果的にスイッチが変えれるし、メリハリがつくなと。

――「ミュージック」におけるRhizomatiksの演出は、この前半後半の分け方でいうと前半っぽいなと感じました。
田中:一応前半でも「ワンダーランド」でRhizomatiksに登場してもらっているのですが、後半は「ミュージック」が立っているのでそう感じたのかもしれません。