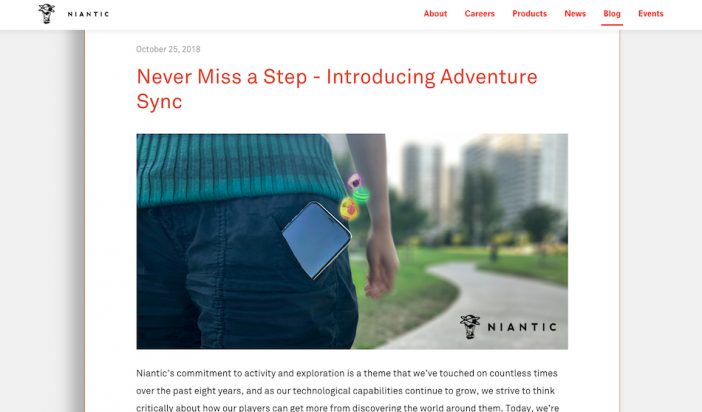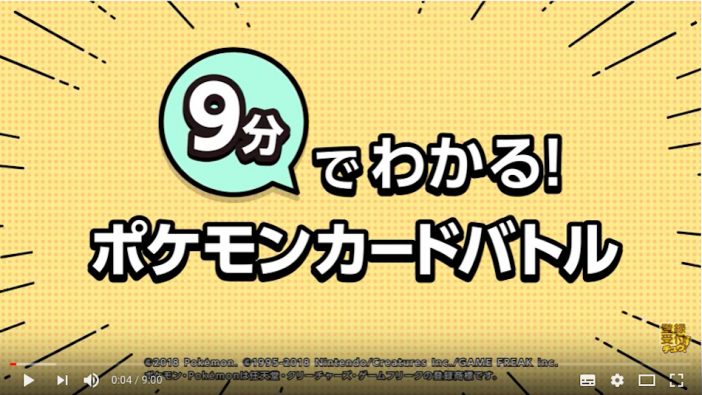ポケモンがファッションテックを加速させる? Original Stitchとの“151種のカスタムシャツ”コラボ理由に迫る

キャラクターのストーリーやコンテクストをデザインに活かす

実際にポケモンシャツに身を包んで登場した3人。ファッション×テクノロジーという時代を先駆けたコンテンツであるポケモンシャツをリリースするにあたり、どのような思いがあったのかを語った。
実際に151匹をデザインするにあたって気をつけた点について、「キャラクターごとにストーリーがあるので、そこをデザインに活かしたいなという点は気をつけました。また、ユーザーの方が感じているキャラクターのイメージをうまくデザインに反映できればなという思いでデザインに起こしました。かっこいいものも、可愛いものもというところはユーザー目線でデザインしました」と話す小杉氏。自身も現在30代であり、いわゆる”ポケモン世代”であったことがユーザー目線につながったと話す。さらに今回のターゲット層は具体的に設定しておらず、むしろシニア世代からティーンまで共通して楽しめるシャツにすることを想定したという。シチュエーションに関しても、ドレスシャツ、カジュアルシャツ、リラックスシャツと3種類を設けることで、ビジネスのシチュエーションだけに捉われず、休日やバケーションなど様々なシーンでの利用を考えてオーダーできることを考慮した。
藤本氏は、ビジネスシーンでの自己表現についても言及する。スマートカジュアルやジャケットの着用など、ビジネスにおいてのファッションが変化していく中、ただ変化についていくだけではなく、そこで実際に自己表現ができているのかということに注目した。彼は「ビジネスではどうしても白か青の無地のシャツになってしまう、そんな方々が多いと思います。そんな中で、ポケモンという魅力的なキャラクターを身につけてもらうことで、ちょっと違う彩りの加わった1日になればいいなと」と話し、それについては、小杉氏も「この企画の中では”験担ぎ”も意識しました。今回のポケモンでも、1匹1匹にストーリーを感じてもらって、それに験担ぎの意味を感じて頂いたり、”コクーンを身につけてもっと忍耐強くなろう”などと意味を感じてもらえたらと思いました」と、ポケモンを身につけることで広がる楽しみについて話した。
さらに今回のコラボレーションについて、海外展開の視野もあるのかという問いに、藤本氏は「まだ具体的な発表はできない状況ですが、海外市場において、お互いにたくさんのファンを持っていますし、そういった方々に商品をお届けできるように、引き続き双方でディスカッションしていけたらと思っています」と前向きな姿勢を見せた。さらにファッションの多様化で小規模なブランドが増えていたり、ZOZO SUITSのような“自分にあったサイズ”の需要が増える中、シャツ以外の展開を視野に入れているのかとの質問には「シャツ以外についても、具体的な商品や時期については明言できませんが、鋭意検討中ではあります」と話してくれた。
さらに、ポケモンを支持する年齢層がどんどん拡大していることについて、首藤氏は「子どもの頃遊んでいた世代が、今30代になり、ビジネスの意思決定ができるようになってきたからこそ、様々な企業さんとコラボができています。『Pokemon GO』リリース以降はシニア世代にもポケモンが浸透し、ほぼ全世代に届けることができるようになりました」と、サービス展開においても世代ごとの区切りをあまり気にする必要がなくなったことを明かす。
最後にそれぞれのお気に入りのポケモンと、当日着用していたシャツについて話してもらった。首藤氏のお気に入りはコダックだが、身につけているシャツはイシツブテ。イシツブテの柄は「両手を使い険しい崖を登る。 その姿を見た人がボルダリングを始めたらしい。」というポケモン図鑑(ウルトラムーン)の文章から由来した柄で、実際に柄の中に人が紛れ込んでいる。こういったコンテクスト由来のデザインを含め、新たに好きなポケモンが見つかるというシャツを選ぶ楽しさを説明した。
一方、藤本氏はポケモンとシャツの柄の両方でピカチュウが好きだそうで「白地に小さくピカチュウがあしらわれたシャツは、白以外あまり着ないユーザーにも手が届きやすい。ピカチュウは電気タイプなので自分にビリっと喝が入れば」と笑顔で話した。小杉氏は好きなポケモンはカラカラだと言い、今回のシャツでも「実はバルジーナという、カラカラの骨を狙うとりポケモンの影が後ろにちょっとだけ入っています。亡きお母さんのお参りに来ているところを狙われるというストーリー性が、シャツにもあるんです」とカラカラの柄に隠された秘密を明かしてくれた。
メインのポケモン以外にも1枚の柄に複数のポケモンが入っている柄もあり、まさに遊び心の詰まったシャツが楽しめるといえよう。それぞれのポケモンの思い出を話し、笑顔でインタビューは終了した。
(取材・文=Nana Numoto/撮影=編集部)