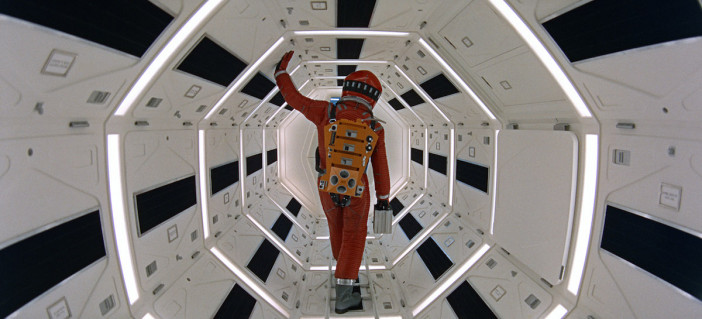『竜そば』『サマーウォーズ』『デジモン』 細田守監督作品から読み解く情報社会の変遷

細田守にとって情報技術とは何か
細田守がアニメーション監督としてデビュー以来、先進的な情報技術やウェブ空間を題材とした作品をコンスタントに手掛けていることは、度々話題にされてきた。
具体的には、ほぼ10年おきに作られた『劇場版デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!』(2000年)、『サマーウォーズ』(2009年)、『竜とそばかすの姫』(2021年)の3作品だ。すでに知られているように、この3作品は、設定や物語も互いによく似ており、セルフリメイクのような様相も呈していることで、細田の作家論の中でもかねてから取り上げられてきた。
そこで主に描かれる情報技術は、コンピュータの中のインターネット世界であり、『サマーウォーズ』と『竜とそばかすの姫』(以下、『竜そば』)ではそれぞれ「OZ」、「<U>」と名づけられた、「メタバース」と呼ばれるような世界規模で展開される仮想世界だ。

また、人工知能(AI)についても『サマーウォーズ』に登場するハッキングに特化した学習型AIプログラム「ラブマシーン」などで描かれている。
「第3次AIブーム」と呼ばれるAIに対する日本の社会的注目度の高まりは、iPhoneのSiriや、Amazonエコーなどのスマートスピーカーが普及する2010年代前半から半ば頃からのことである。そして、その現代のAIブームの大前提となっているいわゆる「ディープラーニング」(深層学習)という新技術が浸透し出すのがだいたい2000年代末から2010年代初頭のこと。そのため、『サマーウォーズ』で登場したラブマシーンは、昨今のAIブーム直前のキャラクターだったということが分かる。という訳で、今回いただいた「AI×細田守」というお題を少し拡大し、「細田守にとって情報技術とは何か」という観点で論じていく。
筆者の個人的記憶からいっても、(『デジモン』はもちろん)『サマーウォーズ』公開当時は、AIは、まだ全くといってよいほど世間では話題になっていなかった。ちなみに2009年当時のIT系のトレンドの中心は、ニコニコ動画などの動画共有サイトやブログ(懐かしい!)などのSNS、初音ミク、スマートフォンなどである(いわゆるWeb2.0やチープ革命)。IT系経営コンサルタント・梅田望夫が2006年に出版した『ウェブ進化論』(ちくま新書)や社会学者・濱野智史の2008年の『アーキテクチャの生態系』(NTT出版)などが言論の主な参照先だった。iPhoneやX(旧Twitter)が日本社会でキャズムを超えるのが、ちょうど2009、2010年くらいのこと。また、「OZ」がなぞらえられるメタバースでは、当時はちょうど、リンデンラボが提供している「セカンドライフ」が話題だった。
情報社会の描き方の変化
では、細田のそれらの作品群では、AIを含めた情報技術や情報空間は、どのように描かれていたのか。
簡単に一つの側面を切り出せば、それは「創発(emergence)」に対する期待の変化にあると言えるだろう。創発とはもともとは物理学や生物学などの分野で使われる用語で、無数の要素(ノード)が局所的で自律的な相互作用を繰り返すことにより、部分の単純な総和にとどまらない、より大域的で高度で複雑な秩序が自生的に派生する状態を意味する。つまり、何らかのメタレヴェルの主体がトップダウン的かつ意図的に作る秩序やシステムではなく、そうしたメタレヴェルを想定せず、膨大なエージェンシーがそれぞれ勝手に動いている偶然の結果として、何らかの組織だった秩序やシステムがボトムアップ的に生み出されることをいう。
20世紀の経済学でいえば、ジョン・M・ケインズの唱えた、政府が有効需要をトップダウン的に操作することによって(公共投資など)雇用を創出する計画統制経済の理論が前者だとすれば、フリードリヒ・A・ハイエクの唱えた、ケインズ的な設計主義を否定し、市場メカニズムに委ねる「自生的秩序」の考え(『隷従への道』)が、「創発」と近い。
ともあれ、ネットの登場からSNSが普及していく2000年代いっぱいまでは、情報社会論やマネジメントの領域では、この創発的な考え方が主流だった。要するに、インターネットの素晴らしいところは、これまで一部のエリートや専門家が独占して独断的に決めてきたさまざまなことが、ネットの無数の「普通の人々」が互いに繋がりあうことによって、これからはいつの間にか勝手にすごいことが実現するようになることなんだ! 万歳! という楽観的な期待である。
その象徴が、例えば2001年に立ち上げられた世界的なインターネット百科事典「Wikipedia」である。いうまでもなく、Wikipediaの執筆者は一般的な百科事典のようにその道の専門家ではない。項目を書き込んでいるのは世界中の一般人のボランティアだが、その彼らが天文学的な数字でその知識を局所的に結集することにより、普通の百科事典にも見劣りのしない相対的に確からしいコンテンツが、徐々に、しかも勝手に組織されていく。こういうものを、「集合知」ともいう。
2009年の『サマーウォーズ』で細田が描いたのも、基本的にはこのWikipedia的な「創発」や「集合知」に対する期待や信仰である。
人類と敵対するAIとして登場する(このあたりも、AIとの共存を好んで描く2010年代以降のリアリティとはずいぶん違う)ラブマシーンがOZの世界を混乱に陥れる。さらに、地球に帰還途中の小惑星探査機「あらわし」を世界500カ所以上ある各施設のどこかに落とそうとする。そんなAIと戦いピンチを迎える主人公の健二やヒロインの夏希を救うのは、自分のアカウントを提供してくれた全世界の何億という人々の力だった。

ところが、2020年代初頭の『竜そば』になると、こうした「創発」や「集合知」をめぐるオプティミズムは一気に影を潜める。いうまでもなく、その表現の変化は、その間の2010年代に起こった情報技術に対する“期待の急激な低下”にある。
私たちはこの10数年を通じて、ネットやSNSが人類社会を単純に豊かで幸せにするのではなく、むしろいかに人々を愚かで盲目的にするのかを嫌というほど味わった。人々が繋がりすぎたことで起こるのは、日常的に個人の人生の幸不幸を左右する不毛な「炎上」や「フェイクニュース」であった。また、AIは私たちにとってより身近で親しみ深い存在になったが、他方で、リテラシーや創造性に対する負の影響も不安視されるようになっている。ともあれ、『竜そば』では「<U>」の何億という人々は、もはや主人公の鈴たちの単純な味方ではない。物語は、無数の人々がコラボレーションして何か大きな力を発揮するというより、そうした膨大なユーザの中から「たった一人」を見つけるという方向へシフトしている。ここには、ここ20年ほどの日本の情報社会をめぐる社会的公正/厚生のあり方の変化についての、細田のアクチュアルな思索の跡が窺われる。
アニメーション監督とテクノロジー
ともあれ、AIを含めた現代のネット空間や情報技術を継続的に自作のモティーフにすることに対して、細田は、これまでにも多くのインタビューでさまざま語っているように、きわめて自覚的である。「僕は、インターネットの世界を舞台に、継続的に映画を作っている世界でも数少ない監督の1人だと思います」(※)。おそらくここには、細田の個人的な作家的資質や関心という以上に、世代的な文脈があるような気がする。
視野を広げてみると、戦後日本の代表的なアニメーション監督には、その世代ごとの固有のテクノロジーとの関わりがあるように思える。1928年生まれ(少国民世代)の手塚治虫ならば「原子力」や「ロボット」。1941年生まれ(焼け跡世代)の宮﨑駿や富野由悠季ならば「兵器」やその「模型」。そして、1960年生まれ(新人類世代)の庵野秀明ならば「特撮」といったところだろう。1967年生まれ(バブル世代)の細田を挟んでその下となると、1973年生まれ(団塊ジュニア世代)の新海誠や、さらに(ロスジェネ世代)の山田尚子、1988年生まれ(ゆとり世代)の石田祐康などになると、本格的なデジタル世代とはいえ、ネットや情報技術を正面から作品で扱うということはほとんど見られなくなる(新海の場合は、作品のテーマというより、制作スタイルの面で先端的なデジタル技術と関わっていた)。
おそらく新海や同年生まれの米林宏昌、山田、石田らの世代では、アーティストの落合陽一のいう「デジタルネイチャー」のように、情報技術やサイバースペースがもはや一種の自明化された「自然」と化しており、あえて主題化するというモチベーションが低いのではないだろうか。むしろ『PUI PUI モルカー』(2021年)で大ブレイクした1992年生まれ(さとり世代、ミレニアル世代)の見里朝希などは、あえてアナログなパペットアニメーションを採用している。あるいは主題的には、新海の『万葉集』(『言の葉の庭』)や山田の『平家物語』(『平家物語』)のように、彼らは古典的な想像力へ向かう傾向にある。
それでいうと、日本社会では、確かに細田の周辺の世代が、コンピュータやインターネット、AIなどの情報技術への関心が相対的に高いと言える。