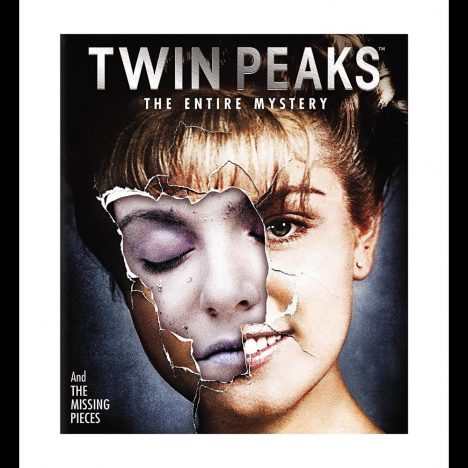何がリンチただ一人の語りを可能にしたのか? 『デヴィッド・リンチ:アートライフ』を読み解く

デヴィッド・リンチ――彼の紡ぐ不可解な悪夢の世界にうなされたことが一度でもあるならば、誰もがその謎を紐解いてみたくなるだろう。本作『デヴィッド・リンチ:アートライフ』は、主に映画製作に入るまでの彼の「アートライフ」に肉薄するドキュメンタリーである。それは、広く認知されているように彼が類まれなる映画作家であると同時に、芸術家であること……というよりもむしろ、芸術家であり続けることでしか生きられない、生粋のアーティストであることを観る者へ知らしめるものである。

映画の冒頭、煙草を片手にアトリエで白い椅子に腰掛けるリンチの姿を、カメラが捕らえる。鳥のさえずりさえ聞こえてくるその穏やかな佇まいが画面に映し出されたかと思うと、画面は一転してリンチのグロテスクなアート作品を次々と挿入していく。それは『ブルーベルベット』(1986)で、田舎町ののどかな光景と一人の男から、地面下の黒々としたうごめく虫たちへとカメラが移行するあのシークエンスに代表される、リンチ映画における特色を再現する。

つまり、平穏から不穏へ、光から闇へ、そして生から死へ、対となる概念への急転換である。映画の途中、不意にうつぶせになり横たわる幼児の人形が映し出される。すると、次のショットではリンチの愛娘ルラが登場する。静止していた同型の物体が、次の瞬間には動き出すという魔術的なこの一連のショットは、まさに生と死という対となる概念への一瞬の移行であり、リンチ映画に見られる自家撞着のたわむれを擬えた粋な演出である。
哲学者スラヴォイ・ジジェクはリンチ映画における「声」、そして「音」が重要なファクターであることを指摘する。本作では、リンチただ一人の「語り」が「声」と「音」のほとんどを担っている。リンチが発する洗練された「声」という「音」は、本作の映画作品としての質を高次化するものとして、また重要なファクターと化しているのである。

本作がそのようにリンチただ一人の語りを可能にしたのは、「カメラは透明なもの、存在しないものになった」という監督の言葉にも表される。リンチが一人、自身について語り続ける。外の世界へ潜在的な恐れを抱いているリンチにとっては、アトリエは紛れもなく彼自身にとってのユートピアであり、くつろげる場所でもある。その語りの中には、明白にリンチの映画作品と結びつけられるようなエピソードが散りばめられているのだが、本作は決してすべてを提示するようなことはしない。リンチの映画のワンシーンを引用することを徹底して拒絶することで、観客の記憶の中のイメージそのものが彼の語りとリンクするようになされている。それはリンチを愛好するファンにとって、至福の営みかもしれない。