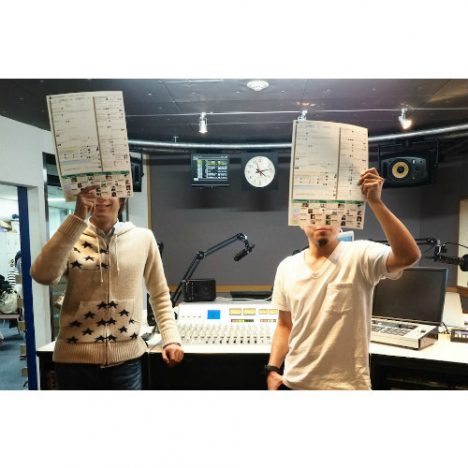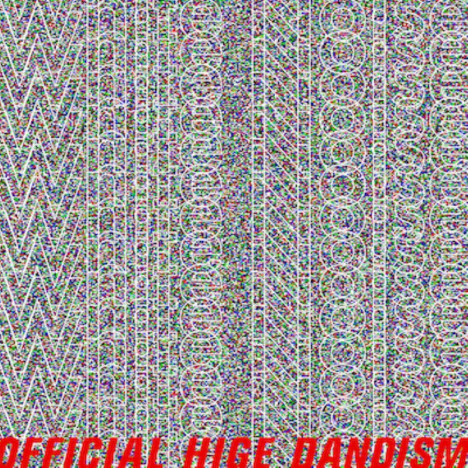Dumyy Lou、“ROCK HOMIES”を名乗る理由 ロックマインド溢れるモウリケイタが「拝啓、俺」で描いた自分との戦い

モウリケイタ(Vo/Gt)が率いるDumyy Louという集団は、「バンド」でもなければ「ソロアーティストとサポートミュージシャン」というチームでもない。彼らが自らを指して使う「ROCK HOMIES」という言葉は、流動的でありながらロックの名のもとに集ったメンバーの強固な絆を表すものだと思う。
そんなDumyy Louは、今年3月に1stミニアルバム『The Dumyy Lou』をリリースし、8月からは3カ月連続のシングルリリースを続けてきた。あくまでモウリの目指すロックンロールをベースにしながら、経験豊富なメンバーの引き出しを存分に開けて音楽性を広げ続ける彼らだけに、曲ごとに違った顔が出てくる感じがしておもしろい。
そしてその3カ月連続リリースのラストを飾るのが、10月18日リリースとなる「拝啓、俺」。タイトルからもわかるとおり、ここに刻まれているのはモウリのディープな自己像だ。ステージで感情を爆発させてロックンロールを鳴らしている彼の素顔をこれまでにないほどシンプルなバンドサウンドに乗せたこの曲もまた、まだ見ぬDumyy Louの新しい顔をリスナーに伝えてくれる。このインタビューは9月26日に開催された自主イベントの直前に行ったもの。モウリに加え、プロデューサーでもある宮田'レフティ'リョウ(Ba)、TETSUYUKI YAMADA(Dr)、香取真人(Gt)というフルメンバーで質問に答えてくれた。(小川智宏)
Dumyy Louは“リミッターを完全に外していいプロジェクト”
――ミニアルバム『The Dumyy Lou』をリリースしてから約半年が経ちましたが、ここまでやってきての手応えはいかがですか?
モウリ:ミニアルバムを作って、ライブはまだ今日で5本目なんですよ。
宮田:それしかやってないんだ。
モウリ:だからこれからがめっちゃ楽しみで。目指している場所が100%見えているわけじゃないけど、そこに向かっていろいろやっていくなかで新しいロックが提示できればいいなと思っています。今も全然手探りなんですけど。
香取:このプロジェクトに参加してから、毎回新しいチャレンジをやらせてもらっていて。レコーディングもそうですけど、チームで一緒にここまでやるのが久しぶりだったので、単純に楽しいですね。そのなかでみんなで模索しながら進んでいくことが今後に繋がっていったらなと思ってます。
YAMADA:とにかくすごいスピード感だなと感じていて。バンドっぽいんだけどちゃんとプロジェクトっぽくもあるというか、モウリくんがやりたいことが1個芯としてあって、そこにレフティのまとめる技術があって、僕らは好き勝手やらせてもらってるっていう感じなんですけど(笑)、すごいスピード感で曲ができていて、ますますこの先が楽しみですね。
――今までやってきたバンドとはちょっと違う?
YAMADA:そうですね。みんながやりたいことを出していくなかで、「それちょっとだせえよ」とか「それかっこいいよ」とか、そういうやりとりがあまりないんですよ。ポンポン進んでいくので。そのスピード感がいいなと思っています。
――まとめ役の宮田さんはいかがですか?

宮田:僕らはモウリくんも含めて、それぞれにバンドマンとしての活動をやってきたバックボーンがあるんですけど、そこからある種一歩引いて、今はバックアップミュージシャン、サポートミュージシャンとしての活動が主になっているメンバーなんですよ。でもそういう状態で活動しているとリミッターみたいなものをかけなきゃいけない部分があって、Dumyy Louをやり始めた当初は「これはどっちなんだろう」みたいなところがあったんですよね。ライブを4、5本やってくなかで、今はリミッターを完全に外していいプロジェクトみたいな気持ちになっていますね。自分たちが培ってきた能力を惜しみなく発揮することによってモウリくんに得てもらえるものがあるし、彼も自由にできる。そういう形がもうちょっとでできるんじゃないかなって気がしています。
――バンドではなく「ROCK HOMIES」という言葉で自分たちを定義しているのもそういうことなんですかね。バンドにしてしまうとそれもひとつの制限になるし、サポートメンバーだとリミッターが生まれてしまう、という。
宮田:バンドだとやっぱりメンバー的な制約とかも生まれてきちゃって、流動的になれないですからね。流動的なんだけど、みんなが思いっきりやっていいよ、みたいな場所。ロックってそういうものかなって思ってるんで。そういう、自分たちが提唱してきた意味がちょっとずつわかり始めているフェーズですね。「あ、こういうことかもしれないな」って。
――そもそもモウリさんはどんなきっかけで音楽を始めたんですか?

モウリ:音楽をやり始めたのは親がギターとかやってて、それを教えてもらって「楽しいな」と思ったのが最初。それで高校の時に軽音楽部でバンドを始めて、いろいろな曲を聴いていくなかで「ロックンロールがいちばんいいな」という結果にたどり着いて、「俺がやるならこれしかねえな」ってなったんですよ。それでロックンロールをやっていくなかでみんなに出会ったっていう。
――SIX LOUNGEに出会ったのがロックンロールに目覚めたきっかけだったとインタビューで話していましたよね。
モウリ:ああ、そうですね。SIX LOUNGEに出会って「俺、やるならこれしかねえ」っていう瞬間があったんですよ。そこから作る曲もそれまでとは全然違うものになっていった。やっぱり最初に聴いたときのドキドキする感覚って今のチャートにはない音だし、またリバイバルしてロックをチャートに入れ込めたらおもしろいんじゃないかなって思ったのがきっかけですね。
――ロックンロールはそれまでやってきた音楽と何が違ったんでしょう。
モウリ:そうだなあ……ソウル、魂ですかね。ロックンロールのなかでもサウンドはいろいろありますけど、なんか俺は分かるんですよね、「これはロックンロールだな、これは違うな」って。自分の中に物差しがあって、そこに向いてるものがたまたまロックンロールだったんじゃないかな。
――メンバーのみなさんは最初に彼に会ったときどんな印象を持ちましたか?
YAMADA:最初に会ったのはレコーディングのプリプロだったよね。驚くほど何の情報もなく、ただ呼ばれて行ったっていう。まあ、レフさん(宮田)のことだからおもしろいことやるんだろうなと思ってたけど、確かにこれはおもしろいなっていうか、遊び心をいっぱい入れていいんだみたいな感じで、めっちゃクリエイティブだなと思いました。モウリくんもおもしろがってくれるし、でもその中でちゃんと好き嫌いを言うんですよね。歳もキャリアも僕のほうが上なんですけど、関係なく言ってくるし。ライブ中におもしろかったのが、僕のほうを向いて「おせえ! おせえ!」って(笑)。マジで最高だなって思った。
――香取さんのモウリさんに対する第一印象は?
香取:最初の印象は「尖ってるな」っていうのがあって。僕も人のこと言えないですけど、見た目も金髪だったりするし。OIKOS MUSIC(宮田の経営する会社)のイベントで箱バンみたいなことをやっていたとき、最後にシークレットアーティストでモウリくんが来たのが最初だったんですけど、だいぶ異彩を放ってました。でもいざ一緒にやるようになってからは、「ロックンロールをやるんだ」っていう気概や尖ってる部分だけじゃなくて、優しさというか人間味も見えてきています。
――なるほど。宮田さんはモウリさんとはどんなふうに出会ったんですか?
宮田:僕がいちばん付き合いが長いですね。もともとはOIKOS MUSIC共同代表の小林(祐二)が「おもしろい子を見つけたからスタジオに連れてくわ」って連れてきたのがきっかけで、そこから一緒にソングライティングのセッションとかをしていくようになって。そうやって実際に一緒にやっていくなかで、モウリくんの中で自己完結するような曲作りよりもバンドライクにセッションをしながら作り上げていった方がいいんじゃないかって思ったんです。でもモウリくんも、いきなり年上の人たちばかりに囲まれて大変だったと思うんですよね。だからふと孤独とかが垣間見えることがあって、今の彼を目の前にして言うのもなんですけど、なんか申し訳ないなって思う(笑)。
YAMADA:(笑)。
宮田:だけどそのなかでアイデンティティを出していく気概や覚悟みたいなものを持ってるアーティストってなかなかいないと思うんです。それはすごいなって思います。そうやってくれるのが僕らとしても嬉しいし、だからこそ自分もちゃんとがっぷり四つでぶつかれる、みたいな。
モウリ:ずっと友達とバンドを組んでガラガラのライブハウスでやってただけなんで、こんなに音楽の知識があってうまい人と関わる機会がこれまで俺にはなくて……。毎日新しいことばっかりでめちゃくちゃ楽しいんですよね。今までバンドもやってたし、シンガーソングライターチックな曲も作ったりしてたんですけど、このプロジェクトをやらせてもらうとなったときに、やっぱりロックンロールをやろうってもう1回火がついたというか、そう思わせてもらえたのが自分のなかでは大きくて。揺るぎないものができたと思います。
――さっき宮田さんが言っていた孤独みたいなものを感じたことは?
モウリ:別に感じたことはないです(笑)。
――(笑)。曲はもちろんモウリさんが作るわけですけど、アレンジはバンドでっていう感じなんですか?
宮田:モウリくんがある程度骨格をDTMで作ってきて「これはこれでいいんじゃない」って進んでいくときもありますし、そこが流動的なのがいいなって。もう1曲作ろうかと言って、30分くらいセッションして曲ができることもあって。
モウリ:それがマジで最高なんですよね。
宮田:いわゆるコライティング、共同作曲みたいなことを僕も海外とかに行ってやったりしてるんですけど、その感覚でスピード感を持ってセッションで曲ができるのが楽しいというか、嬉しいですね。
――楽曲を聴いても、もちろん根っこにはモウリさんのロックンロールというのがあるけど、それを作り上げていく過程でいろいろなアイデアが入ってきているのが伝わりますよね。
宮田:そうですね。ロックンロールに軸足があれば、それを昇華してくれるのはモウリくんだから。グラムロックでもいいし、グランジでもいいし、ハードロックでもいいし、ロックがつけば何でもありだろっていう感じなんです。だからまだモウリくんとはやっていないビート感とかサウンドプロダクションでも、俺らが好きなものをバンバン出していて。ライブが終わった後に「こんな曲があったらいいんじゃない?」みたいな話を俺とテツ(YAMADA)でしていたりもするんです。それもモウリくんが消化してくれるから、やりたいことができるというか。
――バンドを組んでやっていくと、スタイルって固定化していくものだと思うんです。でもDumyy Louの場合はむしろどんどん拡散していく、引き出しが増えていく感じがおもしろいですね。
宮田:僕もサウンドプロデューサーとしてはいろんなジャンルをフュージョンするのが好きなんです。でも過去には、しっちゃかめっちゃかになっちゃったこともあるにはあるんですよ。その自覚はあるんですけど、モウリケイタはDumyy Louのサウンドとして消化できるアイデンティティとボーカリストとしての才覚、あとは彼が持っているロックンロールマインドみたいなものがあるので、絶対にブレないんですよね。
YAMADA:ごま油みたいな感じだよね。
宮田:そう。「ごま油を入れれば中華になるでしょ」っていう(笑)。