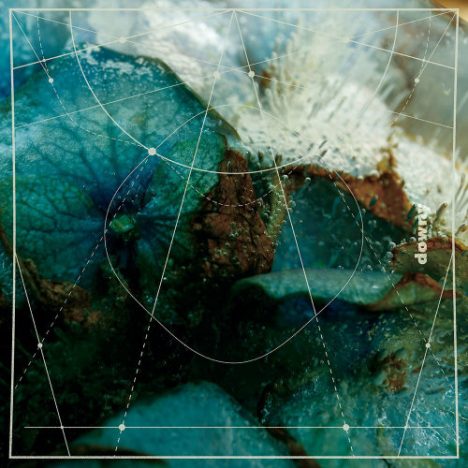金子厚武のプレイヤー分析
LITEのギターは「点と線」から「点と点」へーー新作の音楽的変化を読む
LITEの3年半ぶりとなる5枚目のフルアルバム『Cubic』は、2013年の10周年イヤーを経て、ある種の原点回帰を果たしつつも、新たな領域へと確かに足を踏み入れた、理想的な「2枚目のデビューアルバム」である。
まずは、少し彼らの足跡を振り返っておこう。00年代半ばのポストロック/インストブームの中で登場したLITEは、ミニマルなツインギターの絡みと衝動的なバンドアンサンブルが話題となり、08年発表の『Phantasia』によって、シーンのトップランナーとしての地位を確かなものとした。しかし、その後ポストロックが定型化し、失速していく中にあって、彼らはいち早く「次」を志向し、ジョン・マッケンタイアとの邂逅や、当時盛り上がりを見せていたブルックリンのサイケバンドからも影響を受け、シンセやサンプラーを大胆に導入した傑作『For all the innocence』をモノにしてみせた。
続く『Installation』ではサンプラーを排し、手弾きにこだわることによって、より肉体的なバンドサウンドを目指したが、『Cubic』においてはシンセもほぼ姿を消し、基本的にはギター、ベース、ドラムのみで楽曲が構成されている。その意味では、やはり「原点回帰」と言えるのだが、しかし、バンドの生み出すグルーヴは初期とは大きく異なっている。
武田信幸(Gt.)が『Cubic』のインスピレーション源として名前を挙げているのがディアンジェロ。ネオソウルの伝説的な人物であり、彼の突然の帰還が現在のジャズとヒップホップのクロスオーバーをネクストレベルに導いたわけだが、音数を絞り、ミドルテンポで裏拍を意識したファンキーなフレーズを奏でるオープニングの「Else」は、確かにヒップホップ的なノリを感じる仕上がりだ。
見方によっては突然の路線変更にも見えるかもしれないが、『For all the innocence』のときのように、外側の動きにも開かれた姿勢を持ち、それをあくまで自分たちの解釈で吸収するのはLITEの素晴らしい部分だ。また、現在のブラックミュージックは、そのアンサンブルの中に変拍子やポリリズムが自然と含まれていて、言ってみれば、それはLITEがこれまでずっとやってきたことでもある。
さらに言うなら、LITEの結成に影響を与えた00年代初頭の日本のオルタナシーンといえば、54-71、downy、あるいはZAZEN BOYSなど、ロックバンドによるヒップホップの解釈を志向したバンドが数多く存在したわけで、その意味では、『Cubic』は「原点回帰」どころではない、より本質的な「先祖返り」なのだと言えるかもしれない。
では、ここからはバンドの最大の売りであるツインギターの絡みがどのように変化したかを見てみよう。まず、これまでの特徴を端的に言い表すならば、それは「点と線」であった。オーバードライヴを効かせた硬めの音色で、インパクトのあるフレーズを繰り出す武田のプレイが「点」であるなら、空間系のエフェクターを用いながら、その隙間を縫うようにメロディーを奏でる楠本構造(Gt./Syn.)のプレイは「線」。楠本が途中からシンセを重用するようになったのは、こうしたプレイの特性からしても必然だったと言える。
しかし、『Cubic』ではより音数を削ぎ落とし、ヒップホップ的なアプローチに向かったことによって楠本のプレイもリズム重視になり、より「点」に近づいているのは大きな変化だ。前述の「Else」にしてもそうだし、「Prism」においても、やはり裏を意識したようなリズミカルな「点」のフレーズによるツインギターの絡みが非常に印象的だ。
もう一点、『Cubic』における大きな特徴が、一発録りで衝動を詰め込んだ初期作に対し、セパレートで録音が行われているということ。これによって、今まで役割分担がはっきりとしていた武田と楠本の関係性がよりフレキシブルになり、曲の中で2人の役割が入れ替わったりしている。それがよくわかるのは展開の多いプログレッシブなタイプの曲で、トランペットにタブゾンビ(SOIL&"PIMP"SESSIONS)を迎えた「D」では、カッティングやメロディーの役割がパートごとに入れ替わり、「Warp」においても2人の関係性が「点と点」になったり、「点と線」になったり、刻一刻と変化していくのが面白い。「D」はラテン調だったり、「Warp」がビートミュージック的な色を持っていたりと、より曲調の幅を広げつつ、最大の売りであるギターの絡み自体もまた、確実に変化/進化を続けているのだ。
最後に、「Warp」では武田が日本語で歌詞を書き、ボーカルを初披露しているのも見逃せない。10周年イヤー後も日本はもちろん、アメリカ、ヨーロッパ、アジアと国内外でツアーを続け、だからこそ、日本人ならではの表現にも目を向けたと言えるが、もちろん、これはそんなに堅苦しい話ではなく、彼らが真にボーダーレスな存在であることのひとつの表れに過ぎない。「世界のLITE」であり、「日本のLITE」。彼らのこれからが、ますます楽しみになってきた。
■金子厚武
1979年生まれ。埼玉県熊谷市出身。インディーズのバンド活動、音楽出版社への勤務を経て、現在はフリーランスのライター。音楽を中心に、インタヴューやライティングを手がける。主な執筆媒体は『CINRA』『ナタリー』『Real Sound』『MUSICA』『ミュージック・マガジン』『bounce』など。『ポストロック・ディスク・ガイド』(シンコーミュージック)監修。