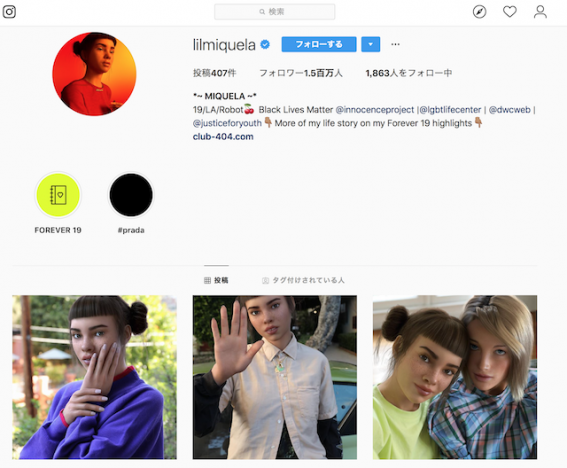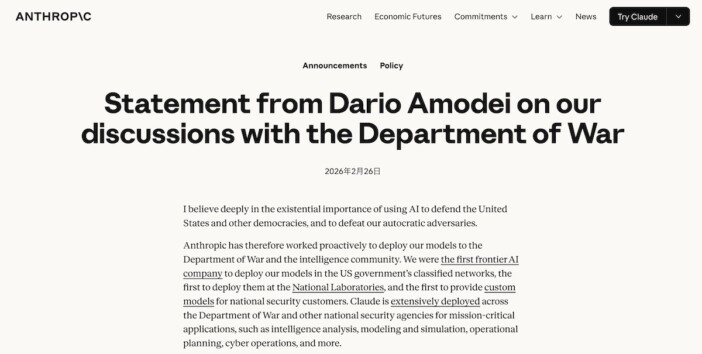渡邉大輔が論じる、バーチャルカメラと「見ること」の禁忌 現代の映画に起きうる変化とは?

現代映画における「顔のクロースアップ」の増加については、すでに昨今の「スマートフォンファースト」の視聴環境との関連からしばしば指摘されることである。しかし、このコラムでは「ポストカメラ的な映像の氾濫」という状況から、もうひとつの仮説的な解釈を提示してみたい。たとえば、気鋭の若手メディアアーティストであり、「ニューエステティック」の代表的な論客として知られるジェームズ・ブライドルは、昨年刊行した最初の著作において、ビッグデータからIoTにいたるまで、情報テクノロジーが進展すればするほど、人間はますます「真実」から遠ざかり、周囲の世界が見えにくくなっていくという危機的状況を論じている(『ニュー・ダーク・エイジ』、NTT出版)。「ポスト真実」の時代において、わたしたちは皮肉なことに、「見えすぎるほど、見えにくくなっていく」のだ。
だとすれば、マネジメントの世界で「認知限界」(ハーバート・サイモン)などと言われる事態にも近い、こうした現代の情報テクノロジーがもたらす状況を、かりに映画のポストカメラ的状況に当てはめてみることも可能だろう。映画はいま、かつてないほどに「なんでも見える」時代に入っている。GoProやバーチャルカメラを使って、どんなイメージでも、どんなカメラワークでも視覚化できる。でも、だからこそ、そうした「なんでも見える」世界をあえて拒む、あるいはそれに背を向ける映像や演出もまた、象徴的な意味をもって現れてきているとはいえないだろうか?
この点については、さきほども名前を出した蓮實重彦の近年の発言がひときわ興味深く思われる。というのも、シネフィル的な往年の映画ファンにはよく知られていることだが、この蓮實こそ、「映画はスクリーンの画面に映る具体的に見えるものだけを論じよ」という批評的スタンス(いわゆる「表層批評」)を強固に打ちだし、それによっておもに80年代以降の日本の映画批評に絶大な影響力をもってきた人物だったからである。ところが、その彼が80歳を過ぎた数年前から、まったく違ったことを突如、述べだしたのだ。
実はわたくしは最近こうも考えているのです。本当に見つづけなければならないのか? ことによると、あるとき見ることをやめてしまうことこそが最大の映画批評であるという可能性もあるのではないか?[…]
いままでのところわたくしは、最善の映画批評に辿り着くためにたえず見つづけることを選んできました。[…]
ただ、ここまでキャリアと年齢を重ねてきたわたくし自身は、見ることをめぐる「人間的」な条件に対してある程度居直ってしまってよいのではないかと感じはじめている、ということです。そうした居直りの表れとして、自発的に見ることをやめるという選択肢もありうるのではないか? 見ることをやめることが批評家でありつづけるためのひとつの道になる可能性もあり、その可能性を示すことはむしろ批評家としてのひとつの務めでさえあるのではないか?──いまはそんなふうに考えております。(インタビュー「「そんなことできるの?」と誰かに言われたら「今度やります」と答えればいいのです」、『ユリイカ』2017年10月臨時増刊号所収)
蓮實のいう「あるとき見ることをやめてしまうこと」、「自発的に見ることをやめるという選択肢」。筆者の見立てでは、その「視覚への懐疑」は図らずもバーチャルカメラ全盛時代に対する映画人のひとつの倫理的なスタンスの表明であり、『ファースト・マン』の映像は、まさにその実践として捉えることができる。

そして、ここまで来て、最後にもうひとつの、昨今話題のあの映画の名前も、このラインナップにつけ加えることができるだろう。そう、昨年末からNetflixで配信され、北米では社会問題になるほどの反響を呼んでいる、スサンネ・ビア監督のSFサスペンス『バード・ボックス』(Bird Box,2018)である。本作はいろいろな意味で、「ポストNetflix」の映画の未来を暗示する演出やモティーフに満ちみちているが、さしあたり、人類を破滅に導く謎のカタストロフを防ぐため、主人公のマロリー(サンドラ・ブロック)たちに課せられる外の世界を絶対に「見ない」という行為は、その意味でポストカメラ時代のわたしたちの観客性の本質を考えるときにたいへん示唆的に映る(さらにいえば、本作が「視覚の抑圧」とともに強調する「聴覚と触覚への信頼」もまた、きわめて現代映画的だ)。いってみれば、目隠しをした我が子を抱えながら、自らも目隠しで必死に森のなかを疾走するマロリーの姿は、『ファースト・マン』の作るチャゼルと、それを鑑賞するわたしたち観客自身のアナロジーなのである。
なんでも見える新たな「バーチャルカメラの時代」と、逆に、何も見えない新たな「暗黒時代」。テクノロジーの進展とともにクリエイティヴィティも進化していくが、2020年代の映画は、この両極端の方向性に挟まれるかたちで進んでいくのではないだろうか。
■渡邉大輔
批評家・映画史研究者。1982年生まれ。現在、跡見学園女子大学文学部専任講師。映画史研究の傍ら、映画から純文学、本格ミステリ、情報社会論まで幅広く論じる。著作に『イメージの進行形』(人文書院、2012年)など。Twitter
■公開情報
『ファースト・マン』
全国公開中
監督:デイミアン・チャゼル
出演:ライアン・ゴズリング、クレア・フォイほか
脚本:ジョシュ・シンガー
原作:『ファーストマン:ニール・アームストロングの人生』ジェイムズ・R・ハンセン著
配給:東宝東和
(c)Universal Pictures and DreamWorks Pictures (c)2018 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED.
公式サイト:https://firstman.jp/
■配信情報
Netflixオリジナル映画『バード・ボックス』
Netflixにて配信中
監督:スサンネ・ビア
脚本:エリック・ハイセラー
Netflix:https://www.netflix.com/title/80196789