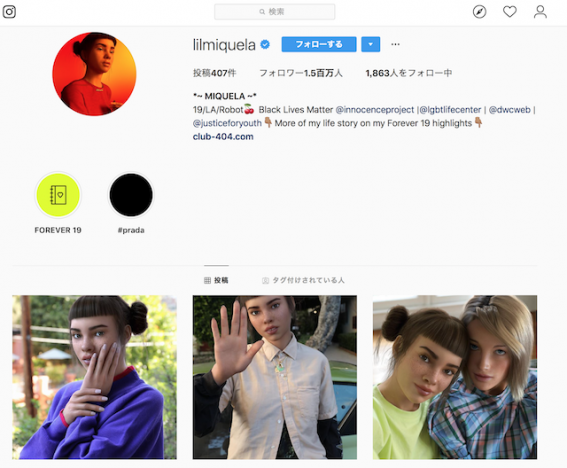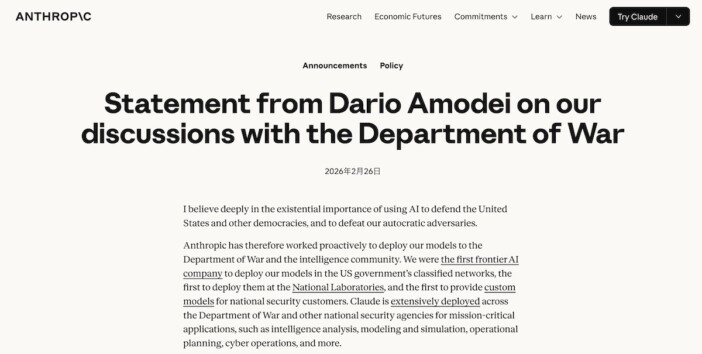渡邉大輔が論じる、バーチャルカメラと「見ること」の禁忌 現代の映画に起きうる変化とは?

繰りかえすように、かつて、20世紀の映画はフィルムという“物質”で撮影されていた。そこでは、原理的に「絶対に撮れない映像」「絶対に見られないイメージ」――それを「映画的イメージの限界」と呼んでもいい――がたしかに存在していた。たとえば1970年代の終わり、著名な映画批評家・蓮實重彦は、それを「人体の落下」のイメージに象徴的に見いだしたのだった(「映画と落ちること」、ちくま学芸文庫刊『映画の神話学』所収)。
フィルム撮影の実写映画では、人体が高所から地面に落下するまでを、ワンショットでまるまる映像におさめることはほぼ実現困難であり、映画監督たちはそれを複数のショットのモンタージュによって処理するしかなかった(いうまでもなく、それを現実に撮影しようとすれば、俳優は死んでしまうからだ!)。そして、20世紀の優れた映画作家や映画批評家たちは、その臨界点にこそ自覚的であり、そこに映画を作ること/観ることの「倫理」を求めてきた。

しかし、いま、映画は「anything goes(なんでもあり)」の時代を迎えようとしている。それが、Go Proとバーチャルカメラが作りあげる「ポストカメラの時代」だ(『キャプテン・アメリカ』のクリス・エヴァンズの身体はどんな高所から落ちても絶対に傷つかない!)。『ブレードランナー2049』のスピナーの飛行シーンにせよ、『レディ・プレイヤー1』(Ready Player One , 2018)のVR空間でのレースシーンにせよ、もはや映画に撮れない映像、見られないイメージは存在しない――少なくとも多くのひとびとがそう信じるに足るような状況が、デジタルテクノロジーによって作られつつある。では、これからの映画表現はいったいどうなるのだろうか?
映画の「ニュー・ダーク・エイジ」
……本来ならば、ここではバーチャルカメラやXRカメラによる映像表現の技術的可能性について論じなければならないだろうが、筆者はひねくれ者なのだろうか、あえてそうした方向とは真逆の可能性について、映画批評の視点から展望を記してみたいと思う。

というのも、ここ最近の注目すべき映画をいくつか見渡していると、いかにもポストカメラ的な、「何でも見てやろう」(by小田実)的な映像ではなく、あえて「見せない」映画、あるいは「見ること」の抑圧・限界をテーマとする物語の映画が目立っているように感じるからだ。たとえば、現在劇場公開中のデイミアン・チャゼル監督の『ファースト・マン』(First Man,2018年)はそうした一本だろう。

1969年、人類ではじめて月面到着を果たした宇宙飛行士ニール・アームストロングを描くこの伝記映画の映像で特徴的なのは、ほぼ全編をとおして、主人公を演じたライアン・ゴズリングをはじめ、登場する人物の顔のクロースアップばかりがひたすら画面に登場することだ。もちろん、人類初の壮大な偉業をテーマとしたこの映画ではアポロ11号の打ち上げシーンも含め、ポストカメラ的なスペクタクル映像が登場しないわけではない。とはいえ、監督のチャゼル(とカメラのリヌス・サンドグレン)は、そうした技術的には当然、実現可能であっただろう想定される見せ場よりも、NASAや自宅の薄暗い空間のなかで苦悩するゴズリングの寡黙な表情ばかりをえんえんと写し続ける。それゆえに、観客たちは物語世界のなかで視界を極端に狭められ、アームストロングが体験している圧倒的な孤独を共有することになるわけだ。つまり、『ファースト・マン』とは徹底して「見せない/見えない映画」なのである。