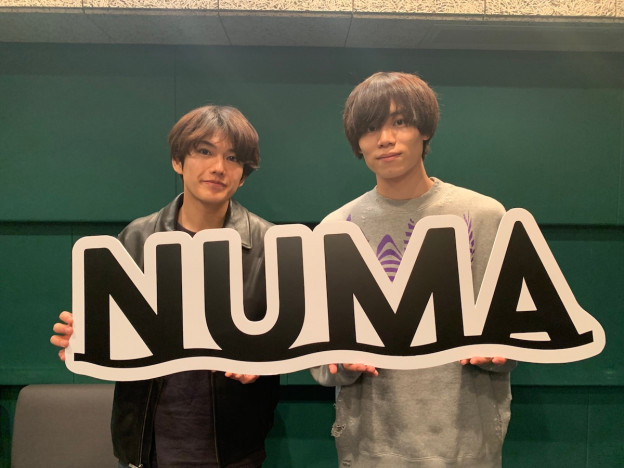太田将熙、30歳の節目に振り返るデビューから10年の歩み 「自分が思う“本物の役者”に」

2013年に舞台『FROGS』のオーディションをきっかけに俳優デビューし、『私がヒモを飼うなんて』(TBS系)や『犬と屑』(MBS)、劇団時間制作10周年記念公演『哀を腐せ』、『シンデレラガール』など、ドラマ、舞台、映画と幅広く活躍する俳優・太田将熙が、2024年にデビュー10周年を迎える。3月25日には川島小鳥が撮影を担当した、デビュー10周年記念のアニバーサリーブック『其のまま。』が発売される。2024年にデビュー10周年、そして30歳という大きな節目を迎える太田に、これまでの俳優人生や今後の展望について語ってもらった。【インタビューの最後には、サイン入りチェキプレゼント企画あり】
「思い描いていた大人ではないなという感覚」
――アニバーサリーブックの発売、おめでとうございます。
太田将熙(以下、太田):ありがとうございます!
――まず簡単に10周年の感想から聞かせてください。
太田:思い返すと本当にあっという間です。いろんな種類のお仕事をさせてもらってきたのでめちゃくちゃ密度は濃いですし、その一つ一つが今の自分を形成していると思っていますが、「駆け抜けてきた」という感じです。気づいたら今10年になっていたのをファンの方からのメッセージで知って、「もうそんなに経ったんだ!」って。
――2024年は30歳になるタイミングです。これまでの10年を振り返ってみていかがですか?
太田:僕はこの仕事を始めたのが厳密に言って19歳くらいで、当時は打ち上げに行ってもお酒を飲めないじゃないですか。だから先輩たちを「いいな」と思いながら見ていましたが、気づいたら年下が増えてきたんですよね。同じ事務所の後輩もいて、彼らがまだお酒を飲めないので一緒にラーメン食べに行って、いい先輩でいようとしています(笑)。そういう時に、「時を重ねているんだな」「俺、おっさんになっているんだな」と感じますね(笑)。
――個人として、30歳を目前に何を思いますか?
太田:個人としては、やはり思い描いていた大人ではないなという感覚です。なんか、22、23歳のままで止まっているんですよね。いろいろ考え方などが変わっているのは確かですが、例えば自然を見たり山に行ったりするとなんか気分が上がっちゃったり、楽しくなっちゃったりすることとか、小学生の頃から変わっていないです。落ち着かなきゃなって思います。
――逆に変わったと感じることは?
太田:今までは結構突っ走ってきたというか、俯瞰よりも主観で物事を見ていました。でも、年を重ねるごとに客観視して場の状況や自分のことを捉えられるようになってきた。それが正確にできるようになってきた、っていうのはあるかもしれないです。
――その気づきのきっかけはあったのでしょうか?
太田:やはり、この10年やってきた大きな功績ですかね。ただ10年だらだらやってきたわけではなくて、自分の中でちゃんと一つ一つの仕事と向き合ってきたと僕は思っているので、それがちゃんと反映されているんじゃないかな。一回の場で気づいたというより、場数や蓄積によるものです。
――幅広いお仕事をするからこそ、違う現場でそれぞれ学びや発見があったことはありますか?
太田:舞台もそうですし、ドラマや映画、声優業などもやってきましたが、どの現場に行っても学ぶことしかないです。舞台と映像の現場でもお芝居の仕方は全然違いますし、その臨み方もまた変わってくる。一つ思うのは、やはりどの現場に行っても一生懸命やっている人はすごく目立つし、輝いているということですね。例えば自分が好きじゃない、もしかしたら望んでいないお仕事をしていたとしても、ちゃんと自分の中で「現場でこうしたい」という明確な目標を作って臨んでいくことによって、自分の人間としての生き方も濃くなっていくと感じました。それが例えば映画などのお芝居の中で、キャラクターの生き様となって表面に出てくる場合もあるだろうし。そう考えると、どの仕事も学ぶことばかりです。
――聞いている私も背筋が伸びる思いです。声優のお仕事やライブもされていますが、それぞれの現場間で感じる違いや難しさなどはどうでしょう?
太田: 新型コロナの流行までは、映像もやってはいたものの、圧倒的に本数としては舞台の方が多くて。ただ、僕はもともと事務所に入りたての時は、ほぼ映像を目的としたレッスンを受けていたんです。その先生のレッスン自体が舞台のお芝居を教えるよりも映像を想定したものだったのですが、僕はそれを知らずに入って。例えば感情をバーって出せばいい、みたいなお芝居をしたら、「ここを切り取った時に、こう見えちゃうよね」というふうに教わりました。ただ、仕事自体はやはり舞台がすごく多かったので、いざ自分で切り替えられると思って映像をめちゃくちゃ見て勉強しても、自分じゃ分からないところで思ったより目線が動きすぎていたり、体が動きすぎていたりしました。舞台って常にお客さんに見えるようにお芝居することを叩き込まれているので、映像の場合、カメラで切り抜いてくれるのに逆にカメラを意識しすぎてしまって、不自然に見えるというか、日常感が出ないみたいなこともありました。そこはすごく研究しながらやっていますね。
――もともと映像のレッスンから始まり、舞台の仕事があって、そしてまた映像の仕事に戻ってとなかなか切り替えが難しいですね。何か突破口は得たのでしょうか?
太田:コロナ禍にお仕事が全部ストップしたわけですが、その直前まで明確にやりたいものが見えなくなっていた時期があったんです。いただいた仕事をとにかくやらせてもらうスタンスで、ありがたいことにお仕事の話はいただけるし、やってきましたが、なんか今ここじゃないところに行きたいなという感覚はすごくあって。それがコロナ禍でいろいろインプットしようと思ったきっかけでした。その結果、やはり僕はすごく映画をやりたいんだなと再確認できたんです。映画をとにかく観まくって、観た後に自分だったらどういうふうにやっていたか、俳優の目線の動かし方や喋り方を、自分自身ずっと家でやっていました。
――コロナの期間がある意味とても大切な時間になったと?
太田:はい、圧倒的に。もちろん、世間的に見るとパンデミックの期間って本当にいろいろダメージがあったし、エンタメの企業や僕らもそれを受けましたが、個人としてはマインドが変わった期間になりました。ただ“おうち時間”を過ごすというより、しっかり未来に向かう時間に使えたのが大きかったですね。その期間、みんなは例えば資格のために勉強したり、何か動いていたりしていたから、当時の僕は個人的に「やばいな」と思っていたんですよ(笑)。ただ、最近になってあの期間にいろいろ考えることができたことが、だいぶ大きかったんだなって思えました。まだ形になっていなくても、思い返すとよかったなと思うことがとても多いです。
――コロナ禍での感じ方、共感します。差し支えなければその期間に観ていた映画を教えてください。
太田: 例えばNetflixやHulu、U-NEXTなどの配信サイトが主流ですが、YouTubeで観られる映画もあったんですよ。その中で短編映画の『純猥談』という作品があって、その第1弾をたまたま見かけて。10分ぐらいのものだったので流し見しようとしたんです。そしたら「すげー面白いな」と見入っちゃって。観終わったあとに、「人って10分でこんなに心を動かされるんだ」と、プラットフォーム関係なく面白いなと改めて思えたんです。その後、僕もその『純猥談』の監督の作品に出させていただいたんですよ。
――なるほど、そういう繋がりだったんですね。
太田:これまで映像をメインにやっていなかった僕の中で、主演をやらせてもらえた作品で、いろんな方に観ていただけたので結構大きかったですね。ラッキーだったっていうのもありますけど、短編映画を観たあと自分から監督に「芝居を見てください」って連絡して、行動できたのも大きかった。「僕はこういう現状で、こう思っていて、でも今いろいろ変えたくて……」と。すると1週間後ぐらいに返事が返ってきて、本当に実現しました。