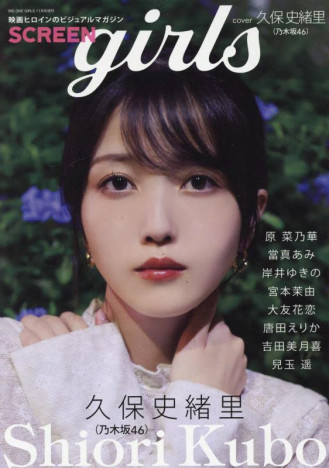『べらぼう』劇伴作家が照射する煌びやかな江戸文化と蔦屋重三郎の生き様 「これは芸術とかそういう話ではない」

芥川也寸志、武満徹、湯浅譲二、一柳慧ら日本を代表する作曲家が名を連ねて来たNHK大河ドラマの音楽。過去、『武蔵 MUSASHI』をエンニオ・モリコーネが手掛けたケースを除けば、外国人が音楽を手掛けるケースは極めて珍しい。
そんな中、『麒麟がくる』に続いて二度目の参加を実現したのが、イギリスや母国アメリカで学んだ作曲家のジョン・グラムである。現在、映画の本場ハリウッドにおいて、音楽から個性が薄れ、背景的に追いやられて行く中、「旋律が書きたい」と意欲を燃やすジョンだが、日本の劇伴の在り方、そして自身が『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』に込めた思いを、『オリジナル・サウンドトラック Vol.1』収録曲の作曲やレコーディングに際しての様々なエピソードと共に語ってもらった。(トヨタトモヒサ)※取材は2025年3月上旬
『麒麟がくる』に続いての二度目のチャンス

ーーまずはジョンさんにとっては二度目の大河ドラマとなりますが、決まった際にはどのように思われましたか?
ジョン・グラム(以下、ジョン):『麒麟がくる』の時には「こんなに素晴らしいプロジェクトは人生で一度しかできないだろう」と思っていました。それほど大きなプロジェクトだったのです。それが今回、二度目のチャンスをいただき、本当に嬉しく思っています。直接の依頼については、LAのレストランで音楽プロデューサーの備耕庸さんから聞きましたが、その場で思わず飛び上がりたくなるくらいの喜びでした。
ーー作品のテーマ、時代背景などはどのように咀嚼していきましたか?
ジョン:自分は両親が大学教授だったこともあり、何か困ったり、分からないことがあるとすぐに図書館へ行って調べものをする習慣が身についていました。今回に関しても、図書館で江戸文化について多くのことを学びました。蔦屋重三郎については英語の文献はあまりなかったんですけど、それでも色々と調べていく内に、徳川幕府や政治家は、彼が送り出した浮世絵や出版物を快く思っておらず、結果的に財産の半分を没収されたことなど、当時の背景を知ることができました。
他にもNHKの製作チームとも多くの資料を共有しましたが、そこで驚いたのが、この歴史(江戸時代)が約250年も続いていたことです。世界的にみれば、どこの国でも何かしらの形で争いが起きており、これほど長く平和が続いた国は他にはありません。だからこそ、煌びやかな文化が形作られたんだと思いますし、そうしたことも学んだことのひとつになります。それからリサーチした体験談として、NHKの製作チームと京都に足を運びました。現地で立ち寄った芸艸堂という版木屋には、何百年も昔の版木が保存されており、それを刷れば今でも本を作ることができるそうです。それこそひとつの倉庫がまるごと版木で埋め尽くされていて、それを直に見ることで日本の歴史を感じ、実際に作曲する上でも大きな刺激となりました。
華やかな江戸文化を落とし込んだメインテーマ

ーー作品の音楽的な顔と言えるのがメインテーマの「Glorious Edo」です。製作チームからはどのようなオーダーがありましたか?
ジョン:当初はもっと芸術に軸足を置いていて、それこそ文学的であったり、思慮深いものを考えていました。ちょっとヘンな言い方ですけど、ドキュメンタリーではないけど、お堅いイメージで捉えていたのです。それを藤並英樹チーフプロデューサーや、大原拓チーフディレクターに話したところ「そうではなく、江戸文化の華やかさや蔦重にフォーカスして欲しい」と伝えられました。その後、一度LAに戻って「江戸文化とは?」「蔦屋重三郎とは?」と考えながら台本を読んでいくと、確かにこれは芸術とかそういう話ではない、ということが見えてきました。そこを理解した上で、では何がテーマになるか? と考えた際に、これが戦国時代なら、どうしても戦が続くわけですが、蔦重が生きた江戸時代は先ほどお話したように平和な時代であり、その結果、富が生まれ、お金が動き、様々な文化が生まれていきました。蔦重が送り出した様々な出版物や浮世絵ももちろんそこに含まれるわけで、そういったところをメインテーマに反映させようと思いました。そこは製作チームと、ディスカッションを重ねていく中で、考えを大きく変えたところです。
ーーメインテーマに関しては、複数のデモを提出するケースもあるかと思いますが、今回はどういったプロセスを踏んで形になっていきましたか?
ジョン:プロジェクトによって色々だと思いますが、今回はそういう流れではありませんでした。先ほどお話したように、製作チームが学問的なものではなく、もっとワクワクするもの、煌びやかな雰囲気を探っていることが分かったので、最初に作ったデモをベースにフィードバックをいただきながら、練り上げていきました。たとえば終結部はデモでの段階ではもっと落ち着いたイメージでしたが、ここも製作陣から「最後までエネルギーを持続させたい」との要望を受けて、エキサイティングな方向性にアレンジし直しています。
ーー大河ドラマといえば、テーマ曲を名門NHK交響楽団が演奏するのも慣例です。本作のレコーディングについてお聞かせください。
ジョン:NHK交響楽団は、弦や金管など、どのパートも圧倒的な存在感を放つと共にいかに融合性が高いオーケストラであるかを改めて実感しました。技術や美しさに加えてそういった部分が何よりの魅力だと思います。しかも「Glorious Edo」は演奏するには、とても難しい楽譜で、自分と親しいハリウッドの第一線で活躍しているオーケストレーターからも「これは大丈夫か?(演奏するには)難しいからやめたほうがいい」と指摘されていました。それがレコーディング当日、下野(竜也)マエストロにお見せしたところ、「これだったら大丈夫、問題ない」との一言で、全く楽譜を変えることなく演奏していただきました。本当にファンタスティックなオーケストラです!
ーーレコーディングを通じての下野竜也さんとのエピソードがあればお聞かせください。
ジョン:あらゆる音楽がそうですが、楽譜で想定していたものが、レコーディングに際して実際に音に出してみると、ちょっと違うことがあり、時には細かくディレクションしないといけない場合もあります。今回、演奏していただく中、ある箇所について「ここはもっとレガート(音符と音符の間に切れ目を入れることなく、滑らかに演奏するよう指示すること)にしてもらいたい」とメモを取っていました。そして演奏が終わった後、調整室に入ってきた下野マエストロの一言が、「ここはもう少しレガートで演奏してほうが良いのでは?」ということでした。まさに自分の考えと一致した瞬間であり、それは非常に印象深い出来事として記憶に残っています。
様々な感情に向き合うことができる日本の劇伴音楽

ーーここからは劇中で流れる楽曲についてお聞かせください。ハリウッドで学ばれたジョンさんですが、向こうは画に合わせて作曲する「フィルムスコアリング」が主流です。一方、日本では番組の放送前と放送中に数回に分けて、数10曲単位でまとめて音楽録音を行い、そこから各話に曲を付けていく、「溜め録り&選曲方式」が浸透しています。こうしたスタイルの違いについてはいかがお考えですか?
ジョン:今、ハリウッドで作られている映画やドラマと、日本のドラマを比較した際に大きく違うのは、今のハリウッドはサウンドデザインの方向に傾いているように思います。音楽自体が質も含めて背景的に使われていて、もちろん、その中にも優れたものはありますし、今のトレンドでもあるのですが、僕自身は旋律を書くことが好きなんです。その長い歴史の変遷を単なる良し悪しで言うつもりではないのですが、自分はあくまで音で感情を表現したいと考えています。そうした中、日本のスタイルでは、映像に合わせて音楽を書かないことで、背景を塗る作業ではなく、様々な感情に向き合うことができます。そこに作曲する上での醍醐味を感じています。
ーー一方で、日本式だと、特に最初のレコーディングに向けては、実際の画を観ることができない中、たくさんの曲を書かなくてはいけません。そうした上での苦労はありましたか?
ジョン:大河ドラマの特徴のひとつとして挙げられるのは、他のドラマとは異なり、全体で40~50話あることです。そして、その物語の中には様々なイベントがあります。人と人が愛し合う瞬間、悲しい別れ、或いは争いや破壊……。あらゆる事象や感情に対して音楽を書いていくわけですが、そこで当時の歴史と照らし合わせて、これは社会としてどういうことだったんだろうか? と考えることもあれば、自分自身が共感を覚えたことを取り入れたりすることもできます。或いは自分の愛する人がなくなったとしたら……。そうした人が持つ感情の揺れは、江戸時代で起こっていることだとしても、同じものです。そういう意味でも誠意を込めて音楽を書くことができたと思っています。
ーーサントラ収録曲から実例を挙げることはできますか?
ジョン:「別れのとき」です。実はこの曲を書いたタイミングで、娘の大学進学が決まり、家を出ることになったんです。しばらくは娘と会えなくなってしまうわけで、やっぱり感傷的にならざるを得ませんでした。「別れのとき」は、そうした気持ちを置き換え、音楽に向かい合い、書いた曲になります。フィルムスコアリングとは違い、逆に画がないからこそできる作曲スタイルで、そこは自分としてはとても大切にしていることです。