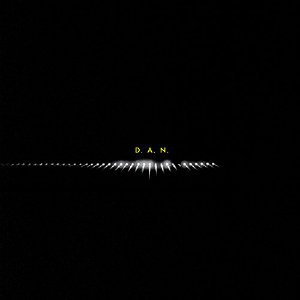新曲「Sink」インタビュー
DYGLが試みた音楽的変化 今ロックバンドとして表現する意味

バンドが大化けする瞬間に立ち会うのは実にスリリングだ。DYGLが3月3日に配信リリースする新曲「Sink」は、きっと驚きをもって迎えられるだろう。UKのインディーロックに憧れ、ストレートなガレージサウンドを鳴らしてきた彼らが、ここでは大きな音楽的変化を試みている。
メンバー4人は一時期までロンドンで生活していたが、2020年にパンデミックの影響もあって帰国。年内にリリースされるであろう3rdアルバムに向けて、各々の自宅からリモートでの制作を進めている。今回の取材にあたって、ニューアルバム用に作られたデモ音源と、バンド側が綴ったコンセプトノートが事前に送られてきたのだが、これがまた驚くような内容だった。後者から一部引用してみよう。
「次回作のテーマとしては、主に二つ。一つ目は、90年代後半〜00年代初頭にかけてポップパンクやオルタナの時代に渦巻いていた享楽的なカラフルさ、みんなで歌える曲の強さ、MTV的というか、『クロスビート』的というか、MDプレーヤー的というか、あの時代の突き抜けた歌えるロック/ポップスのムードを再解釈してみること。二つ目は、コロナ禍において蔓延している時代のムードを、自然な形であれ、意識的な形であれ、取り入れつつ表現すること」
「最近はティーンを熱狂させる音楽はほぼR&B、ヒップホップに取って代わられている印象。好きなサウンドだから個人的にはそれも楽しい。でもギター、ベース、ドラムだからこそ鳴らせる音世界も楽しいし、二項対立ではなく、現行のトラップ以降の音楽からもインスピレーションを受けながら、ロックバンドとしてのアンサーを作品として打ち立てられたらいいなと思う」
実際、デモ音源はこの文面どおりの内容で、シンガロングしたくなる歌の強さも、トラップやエモラップの影響も、ロックへの揺るがぬ信頼も聞こえてきた。90年代後半〜00年代初頭にインスパイアされた世界観は、3月14日〜22日にかけて愛知、大阪、東京、沖縄と廻るワンマンツアー『SPRING TOUR 2021』のフライヤー(ベルリン在住のアーティストMasako Hiranoが製作)にも色濃く反映されている。DYGLはどこへ向かおうとしているのか。新たな季節を迎えようとしているバンドの4人に話を訊いた。(小熊俊哉)
そもそもロックは死なないと思っている
ーーアルバムのコンセプトノートを読んで、取材を楽しみにしていました。なかなか意外で「どういうこと?」と思った部分もあったけど(笑)、今までのDYGLとはちょっと違うことをやろうとしているのは伝わってきた。まずは、バンドが今どんなモードにあるのか教えてもらえますか。
秋山信樹(以下、秋山):3rdアルバムをどうするのか、(2019年秋に開催された)前作のツアーが終わった後にも話し合ったりしていたんですけど、大きいプランが決まる前にコロナが来たんですよね。そのとき俺らは沖縄と香港のライブが決まっていたんですけど、香港はコロナで飛んじゃって。沖縄は無事に開催できたんですけど、俺は家族が向こうにいるという環境もあって、4カ月くらいそのまま沖縄にいたんです。そこで、バンドとしても個人としても、この先どうやっていこうか考えることが次につながるのかなと思って。
ーーなるほど。
秋山:その後、ようやく何をやろうか話し合ったのが7月くらい。俺は沖縄、下中は京都に住んでいるけどみんなで集まって。ただ、2ndアルバムの制作中もそうだったけど、どういうものを作りたいのか混乱している時期が長かったんですよ。そこにコロナも重なって、どうしようと考え抜いた結果、音を出しながら「これは違う」「こっちに行きたい」とかジャッジした方がわかりやすいし、年内までになんとか曲をまとめて、次のアルバムを作ろうという話になったんです。で、「決めたのにやらなかったら、みんな自分の好きな楽器を1本ずつ折ろう」と嘉本が提案してきて(笑)。
ーーそれは大変だ(笑)。
秋山:でも12月までなんだかんだ曲ができなくて、「どのギター折ろうかな」っていうところまで考えてたんですけど(笑)、マネージャーの知り合いのある店で、偶然みんなで音楽を聴く機会があって。自分たちも聴いてはいたけど、バンドとしてはやってこなかった90年代〜00年代のアメリカのオルタナとかポップパンクが流れていて、この感じは懐かしいし好きだったなと思ったんです。「一周回って、今はこういう歌い込める音楽のほうが、突き抜けていて合ってるんじゃない?」となって。それから嘉本の家に行って、今までのデモを聴き直しながら「Fountains Of Wayneとか、こんなの聴いてたよな!」とか話したりしているうちに、やりたい方向が見えてきたんです。そこからは早くて、11月末から12月にかけてアルバムに収録する曲を一気に作っていきました。
ーーコンセプトノートにも書いてありましたね。「90年代後半〜00年代初頭にかけて渦巻いていた享楽的なカラフルさ、みんなで歌える曲の強さ。MTV的というか、クロスビート的というか、MDプレーヤー的というか。あの時代の突き抜けた歌えるロック/ポップスのムードを今流に再解釈してみること」って。
秋山:そうそう、まさに。
ーーその辺の話を伺う前に確認で、しばらくロンドンを拠点にしていたと思うんですけど。
秋山:2018年の夏から2019年の夏ころまでの1年ちょっとですね。そこから半年間は全国ツアーや海外ツアーもあったので、そのまま日本にいたんです。
ーーバンドとしては、ツアーが終わったらまたロンドンに帰るつもりでいたんですか。
秋山:そこは決まってなかったんですよね。個人的には、いろいろな音楽をインプットする場所としてロンドンにこだわっていたので、とにかく1人で戻ろうという気持ちでいたんですけど。
加地洋太朗(以下、加地):バンドの制作スタイルとして、みんな常に一緒の場所にいるんじゃなくて、基本はセパレートして、何かやるときに集まるスタイルでいいんじゃないかなと思ったので、自分はまた違うところか東京にいるのがいいかなと考え始めていました。
ーー例えば幾何学模様は、アムステルダムにいるメンバーもいれば、日本で暮らすメンバーもいますけど、そういうビジョンを描いていたということですよね。
秋山:まさに。幾何学模様の皆さんのやり方は参考にしていました。
ーー僕は勝手に、DYGLは彼らのように海外をベースにしたバンドになっていくのかなと思っていたんです。でも、あらゆるバンドがそうだと思うけど、パンデミックによって自由に集まるのが難しくなったことで「バンドとして活動することの意味」と向き合わざるを得なくなった。もう一方で、これもコンセプトノートに書いてあったことですけど、ここ数年はロックと呼ばれる音楽が少しずつニッチな存在となり、ギターミュージックが大衆音楽としての強みを失っているという現状もある。その辺りについてはどうですか?
秋山:まず、自分が聴くものに関しては、コロナ以降あまりロックバンドがしっくりこない感じがあったんですよ。でも、作ることに関しては、コロナはすぐ終わるかもしれないみたいなことをどこかで思っていました。だから、将来的にやり方を変えなきゃ、とまでは思わなかったですかね。
下中洋介(以下、下中):僕はコロナが始まる前からバンドに元気がないなと感じていたんですけど、今となったら、ちょっと卑屈になりすぎていたような気がして。みんなバンドが好きなんですよね、きっと。1人でやっているトラックメーカーの人とかも、みんなバンド好きじゃないですか。でも、バンドの話をしても、今はヒップホップとかに比べて面白くないんだろうなと。そういうのに気づき始めてからは、逆にロックバンドを聴いている方が僕は安心していました。人の気持ちが感じられるというか、ロックバンドって感情がこもっていてポジティブな気持ちになれることが多かったので。
ーーたしかに、外に出かけづらくて鬱憤が溜まることが多い中で、ロックを聴きたくなるのも何となくわかる気がしていて。それとさっきの90年代〜00年代のポップパンクやオルタナがしっくりきたという話はリンクするのかなって。その辺りは、下中さんも言っていたように、バンドが盛り上がっていないことに対するカウンターみたいな意識もあるんでしょうか。
秋山:いや、カウンターというのはあまりなくて。もちろんバンドが好きだから盛り上がってほしい気持ちもあるけど、ヒップホップがあって、テクノがあって、ロックバンドがある、みたいな捉え方というよりは、自分の好きなものが混ざった音楽がもっとたくさん増えてほしい。俺らとしても昔あったものをそのままやるよりは、新しいものとして更新していきたいので。ロックの中で新鮮なサウンドが少ないというのは確かにそう思うけど、だからと言って「ロックとしてやってやれ」みたいなのは思っていないかな。ロックを復権するためにやると逆に面白くなくなるような気がするし、普通に楽しい音楽をやっているほうがいいから。
ーー改めて整理しておくと、DYGLというバンドはもともと、The ViewやThe LibertinesみたいなUKのインディーロックに対する憧れからスタートしたわけですよね。The Strokesのアルバート・ハモンドJrがプロデュースした最初のアルバムにも、その感じが素直に反映されていた。そこから2ndでは参照する音楽も古くなり、ソウルやサイケなど音楽的な幅が広がっていった。次の3作目はどんなアルバムになりそうですか。
秋山:まだ出来上がっていないので、ハッキリとしたことは言えないけど……。これまでの2作は、自分が好きなサウンドを自分の中で解釈しながら、それをシンプルに表現してきたように思うんですよ。でも今回は、もっと自分たちのエッセンスが出てくると思う。もちろん、これまでも(好きなサウンドを)そのままやっているつもりはなかったけど、自分たちの手で更新したいという気持ちがより強くなっている気がしますね。だから、今度リリースする新曲も、(参照元が)あるっちゃあるけど、他の何とも似ていないものになったと思います。
ーーたしかに「Sink」、全然わからなかったです。そういうリファレンスが。
秋山:本当ですか、嬉しいです。
ーー寂しい曲なのか、明るい曲なのか、楽曲のテンションすらぶっちゃけわからないというか。その感じもすごくいいなと思って。他の皆さんはどうですか。
嘉本:それこそ2000年代初頭はシンセとかも入っていたり、ロックなのかポップスなのかよくわからない音楽が流行っていましたよね。例えばアシュリー・シンプソンとか。Simple Planとかblink-182はバンド寄りだったんですけど、Green Dayも一部からは「こんなのパンクじゃない」とか言われていたり。どっちつかずな感じの音楽が聴かれていて面白かったので、そのあたりの音楽をすごく参考にしてたかなと思います。
ーーポップパンクは最近リバイバルが起きてるじゃないですか。TikTokとかの影響もあるし、マシン・ガン・ケリーみたいな人も出てきている。でもDYGLが今回やっているのは、ポップパンクをそのまま鳴らすこととも明らかに違う。
下中:例えばパワーコードを弾いたり、ありがちなミュートを入れたり、そういう要素を足していけばポップパンクになるのはみんなわかっているから、あえてそれをやらない、みたいな感じですかね(笑)。逆に、そこへ(ポップパンク以外の)何を入れたらいいのかなって思考で進むことが僕の中では多いです。全員ポップパンク好きだったら作るのが簡単でしょうけど、このバンドはそういうわけでもないですし。
ーーそもそもDYGLは、ポップパンクから一番遠そうなイメージでしたけどね(笑)。みなさんが入れ込んでいたインディーロックとポップパンクというのは、少なくとも当時は相容れない世界だったはずで。
秋山:ポップパンクが好きな時期はちゃんとあったんですよ。俺は音楽聴き始めのとき、むしろそっちが好きですごく聴いてたんですけど、UKロックリバイバルみたいなバンドやThe Strokesあたりを聴き始めてからそれがベースになって、失われたもう片方の時代がバンドに反映されてこなかった。でも、いろいろ考えているうちに、今それが面白いってことに気づいたわけです。
加地:個人的にはポップパンクは全く通ってこなくて、これ大丈夫かなって思ったりもしましたけど(笑)。Green Dayの何曲かは好きだけど……みたいな。でも、でき上がってくるものがすごく良いし、コード感でいうと、むしろ90年代オルタナの色が強いのかなって。その二つのミックスはそんなにないような気がするので、そういうところはすごく好きですね。
ーー僕も“叫ばないPixies”みたいなところがあるのかな、とは思いました(笑)。
秋山:キャッチコピーできちゃったな(笑)。今回のアルバムの影響源はもちろんポップパンクなんですけど、なんだかんだオルタナはデカいし、個人的にはエモラップがすごく好きなので、そのままやったら楽しそうだなとずっと思っていて。エモラップはギターが結構入っていてバンドっぽい感じがするし、これを好きだなと思う気持ちはDYGLでもそのままいけるなと思って、それも混ざっている気がします。あとは、「歌える」というのがデカい気がしますね。前作までは演奏と歌が一体になってバンドっぽい感じがあったけど、今回はポップスを参考にしている分、歌が自由にフロウしている感じがより出ている。それはアルバム全体のカラーとして出そうな気がします。
ーーさっき出たFountains Of Wayneとエモラップの組み合わせは矛盾しない気がしますね。Fountains Of Wayneもキャッチーでシンガロングできる部分もあれば、特に初期はヒリヒリした部分もあったりしたわけで。コンセプトノートには他にも、Soccer Mommyの名前が書いてありました。
嘉本:Soccer Mommyはきっかけとしてデカかったと思います。僕個人の話では聴くものがロックバンドから離れていて、クラブミュージックとかヒップホップ、もっとニッチなものをどんどん求めるようになっていったんですけど、Soccer Mommyとか、あとはClairoもそうですけど、それらは同じライン上で聴けるんですよね。なんでだろうなと思ったら、ロックをもうちょっとアイデアとかサンプリングベースで解釈して、さらにそれをバンド音楽として鳴らしているというのがすごく新鮮だったからで。今までみたいにロックだけに寄るんじゃなくて、もっといろんなアイデアを自然にロックバンドとして形にできたらいいんじゃないかなと考えるきっかけになりました。
ーーその話でいうと、先に聞かせてもらったデモから連想したのはMura Masaでした。彼の最新作にはClairoも参加していたけど、あのアルバムはクラブミュージックの視点からロックを再解釈していましたよね。かたやDYGLはロックの視点からクラブミュージックを再解釈しようとしている。こうやって各々の解釈が混ざり合っていく感じが面白いんだろうなと。
秋山:そうですね。今面白いことをやってる人たちはジャンルにこだわっていない。ヒップホップの人たちがロックスターと歌ったり、ギターをサンプリングしたりしてるけど、「ロックに対して俺らの方が面白いことをやってやる」という意識は別になさそうじゃないですか。そこでロックバンドの方が卑屈になって、「ロックをなんとかしなきゃ」となるのは、罠にハマっちゃいそうな気がしていて。それよりも楽しく音楽をやっているほうがいいし、そもそもロックは死なないと思っているので(笑)。「つまんない」と言われる時代がどれだけ続いても、こんなに面白い音楽は絶対に何かしらの形で続いていくと思うし、無理にリバイブしようとしなくてもいいのかなと思ってます。