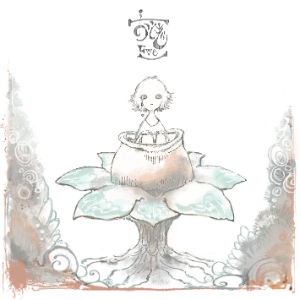Eveによる新たなライブ体験 音楽、映像、パフォーマンスが溶け込んだ『おとぎ』ツアー

シンガーソングライター・Eveのワンマンツアー『2019 春Tour「おとぎ」』のファイナルが4月29日東京・Zepp DiverCityで開催された。
オリコンデイリーアルバムチャートで2位を記録したことも記憶に新しい最新作『おとぎ』(2019年2月)は、Eveが持つ様々な音楽要素を詰め込みひとつの物語を描くような、トータルアルバムとしての魅力を持った作品だったが、この日のライブのテーマは「映画館」。会場の通路には「僕らまだアンダーグラウンド」や「ドラマツルギー」といったEveの楽曲をテーマにした架空の映画ポスターが展示され、開演前に放映される恒例のアニメーション映像も映画館を舞台にしたものになるなど、ライブ全体をひとつの「映像体験」としてパッケージするような、もしくは現実のライブハウスと映像内の映画館をシームレスに繋ぐような雰囲気が用意されていた。その光景に期待を募らせていると、映画の上映開始を告げるブザーが鳴り、Eveとバンドが登場。早速オープニングムービーのような映像とともに「slumber」がスタートする。こうした序盤の構成を筆頭に、今回のライブでは音楽と映像、パフォーマンスが過去以上に境目なく溶け合う、新たなライブ体験が生まれていった。

中でもこれまでとの大きな変更点は、ステージ最後方の巨大スクリーンと、観客の目の前に張られた透明な紗幕の2つを使って生み出される立体的な映像表現。今回のツアーではEveとバンドが終始その2つのスクリーンの間でパフォーマンスを行なうことで、現実の風景にアニメーションが重なる不思議な光景が広がっていく。また、そのアニメーション自体もライブ用にオリジナルなものが用意され、「トーキョーゲットー」や「デーモンダンストーキョー」ではじまった序盤から、MVに使用されたアニメーションとタイポグラフィを使って歌詞を表現した新規映像が次々に融合。そうした演出を、Eveと観客が声を合わせる恒例の「ゲームオーバーです」で巨大な一体感を生んだ「あの娘シークレット」や、バンドの演奏で紗幕にヒビが入る演出ではじまった「アウトサイダー」などにも加えることで、過去の楽曲もまるで新曲かと思えるほど別の体験に生まれ変わっていく様子が印象的だった。

また、中盤に披露された多くの楽曲では、アニメーションだけでなく実写を使った映像表現も融合。雨の演出を加えた「やどりぎ」を皮切りに、「迷い子」では影絵的なイメージがスクリーンを覆い、「ホームシック」では実写の集合住宅の映像によって少年時代の憧憬を思わせるような雰囲気が表現されていく。続く「sister」では、横長のスクリーンを黒板に見立てた実写映像とアニメーションが融合。「楓」では実写テイストの水中の映像が映し出され、最終的にはそれが絵画の中の風景だったと分かる展開で新たな視点を加えるなど、楽曲にあわせてアニメーション/実写映像から最適な表現方法を選択し、それぞれの楽曲の魅力が最大限に引き出されていった。以降は「fanfare」で観客の手拍子を受ける中で高台に立ったEveと、「僕らまだアンダーグラウンド」などのMVに登場する赤い髪の少年のアニメーションとが重なり、ARライブにも通じる圧倒的な没入感がさらに会場を覆っていく。


とはいえ、この日最も印象的だったのは、そうした演出に負けないほど、よりタイトに逞しくなったEveとバンドの演奏/歌の魅力。それをひしひしと感じたのは、人気曲を連発した終盤の怒涛の展開だ。ここでは「ナンセンス文学」を皮切りに、ステージの両端ぎりぎりまでを使って会場を煽った「ドラマツルギー」、広がりのあるサウンドスケープを持った「アンビバレント」などを次々に披露。「次で最後の曲です」と告げてはじまった『おとぎ』を象徴する楽曲のひとつ、「僕らまだアンダーグラウンド」では、終盤に訪れる豊かな音の広がりによって、Eveのキャリア史上過去最大規模の会場が小さく感じられるような巨大なスケール感が生まれていく。ソリッドなギターロックを基調にしながらもより多彩な要素を飲み込んで広がった楽曲自体の魅力と、立体感を獲得した映像、そして盤石の演奏とが融合した圧倒的なライブパフォーマンスで本編を終えた。