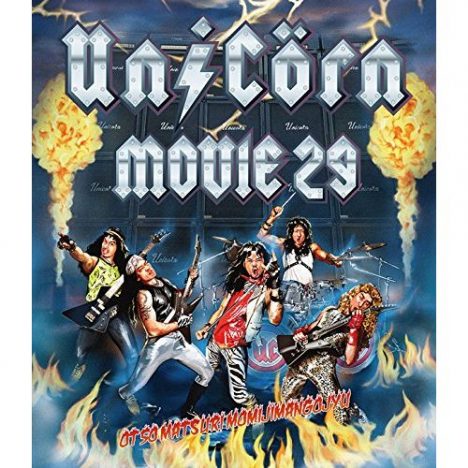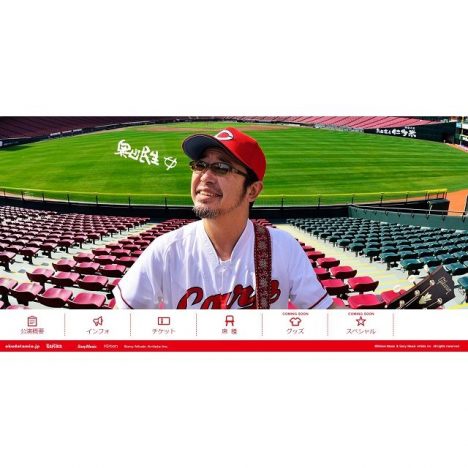兵庫慎司がユニコーン新作を分析
ユニコーン、その特殊なバンド組織論ー-兵庫慎司が新アルバムから読み解く

ユニコーンのこのような制作姿勢は、3枚目のアルバムでありバンドのブレイク・ポイントとなった『服部』(1989年)で本格的に始まり、続く『ケダモノの嵐』(1990年)でセールスの成功のみならず、作品性の高さの面でも、各方面から絶賛される結果を生んだ。『Pati Pati』などの音楽専門誌と『ミュージック・マガジン』のような雑誌の表紙を両方飾ったバンドは、当時としては珍しい存在だ。今のミュージック・マガジンはアイドルとかも普通に表紙になるのであんまりピンとこないかもしれないが、当時は「マジか!」とびっくりしたものです。
ただし。そのようなバンドに化けたことが、そのあとアルバム2枚で解散するという方向に向かっていった多くの要因のひとつになっているのかもしれないが。
ともあれ、2009年の再結成後も、ユニコーンはそのようなバンドの運営方法をキープしたまま……いや、キープじゃないな。いっそうそれを激化させながら、活動を続けている。
考えてみれば、そもそも復活一発目のシングル「WAO!」のボーカルがABEDONだったこと、奥田民生はアコースティック・ギターを背中に回してほぼカウベルをコンコン叩いているだけ、それでテレビに出まくっていたこと自体が、「これからもこういう感じなんでよろしく」という意思表明だった、とも解釈できる。
自分たちでもわからずに作っているのだから、できあがるまでどういうものになるのかはわからない。「作ってみていいものができかなかったら再結成自体をやめる」と決めてからレコーディングに入り、ほぼできあがった時点で「これなら復活あり」とジャッジしたというアルバム『シャンブル』は、そこまでシビアに作っただけあってすばらしい作品になり、解散前も含めてユニコーン史上最高のセールスを記録した。80年代・90年代と00年代以降のCDマーケットの状況を比較すると、これがいかに異常なことなのかがわかるだろう。
ただ、それ以降に関しては、「このアルバムはいい! あり!」と、「このアルバムはさすがにちょっとやりすぎては」との間で、このバンドは進んできた。
具体的に言うなら──あくまで僕個人の感想だが──『Z』は「あり!」で、『ZⅡ』は「ちょっとやりすぎだけどミニアルバムだし、『Z』の未収録作品集だからあり!」だった。で、『イーガジャケジョロ』は、正直に言うと、初めて「このアルバムはさすがにちょっとやりすぎでは」と思った。特にツアーを観て、その思いを強くした。
では、このたびの『ゅ 13-14』はどうなのか。
最初に聴いた時、『イーガジャケジョロ』以上に「このアルバムはさすがにちょっとやりすぎては」と思った。しかし。にもかかわらず、「このアルバムはいい! あり!」と、同時に思った。という、少なくとも僕にとっては初めてのユニコーンのアルバムだ、これは。
らしくないほどアッパーに始まる、作詞作曲歌唱:奥田民生による1曲目「すばやくなりたい」から手島いさむの「オーレオーレパラダイス」、ABEDONの「サンバ de トゥナイト」、手島曲を川西幸一が歌う(そしてライブを見越してかドラムは奥田民生が叩いている)「僕等の旅路」、EBI曲の「道」の頭5曲から、ABEDON曲を奥田が歌う「風と太陽」と川西曲を奥田が歌う「フラットでいたい」でしめくくられるまでの、全14曲。
好き勝手にやっているのに、聴き手を振り落とさない。聴き手と距離近い。聴き手がおもしろがったり、驚いたり、自分を重ねたりして入り込むことのできる風穴のようなものが、そこら中に開いている。
アレンジにおいて、レコーディングにおいて、ありとあらゆるアイディアを曲に詰め込み、言われなきゃ絶対わからないような音の重ね方や音の差し方などを山のように行うのがユニコーンだが、このアルバムにおいてもそれをやっていながら、シンプルで隙間の多い音の質感に仕上がっている。
ハードロック方向とアメリカン・フォーク的な方向、いずれかに振れることが多い、そして特に後者で力を発揮する手島いさむ楽曲。歌声のトーンも含め、淡々とした叙情性に満ちたEBI楽曲。どこから球が飛んでくるのかわからないみたいな意外性に満ちた曲調と、「実は歌詞がいい」という特徴を持つ川西幸一楽曲。メンバーの中でもっとも広くて深い引き出しを持つ(ジャズやラテン等のロック以外のテイストをユニコーンに持ち込んでいるのはこの人だと僕は思っている)ABEDON楽曲。そして、昨年の50歳記念時に発表した「私はオジさんになった」といい、本作の「エコー」にしろ、最近、ソロでやる曲とユニコーンに持ってくる曲の境目がなくなっているフシがある(で、それ、いいことだと思う)奥田民生楽曲。
「とにかくサムいのと恥ずかしいのがイヤ」「だからそれを避ける」のがユニコーンの歌詞の書き方だが、このアルバムでもそれを遂行しながら、同時に、全体的にややシリアスというか内省的な感触を持つ方向のものが多く、それがそのまま聴き手の入りやすさにつながっている。