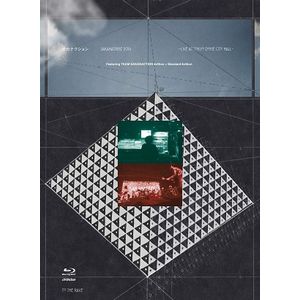『HEN 愛 LET'S GO! 2 ~ウルトラ怪獣総進撃~』インタビュー
POLYSICSハヤシが語る、ウルトラ怪獣への偏愛「オレが曲にしないとな、という使命感はあった」
「ポリシックスのステージングとか自分の歌う曲は、生活と密着していたくない」

——ものすごく大雑把に分けると、アーティストは2通りいるんじゃないか。自分のことを知ってほしい、わかってくれというタイプと、自分は関係なく作り物の世界を楽しんでください、というタイプに分かれる。ハヤシ君は後者のようでもあるけど、実は前者の「自分のことを知ってもらいたい」という気持ちが強いのではないかと。
ハヤシ:おお〜〜〜そう……ですねえ。
——でもそこらのシンガーソングライターみたいな、自分の苦悩を知ってくれとか、ドロドロした内面を吐露したりとか、そういう方向に行かない。いかにドクターペッパーが好きか、いかにDEVOがいいかアピールする方向にいくところが、ハヤシ君の面白いところではないかと。
ハヤシ:そうすねえ……なんかすごいすねえ……そうすねえ……そうです!(笑) なんかどーんと来たなその指摘(笑)。確かにそうだなあ……。
——ハヤシ君だってもちろん人間だから、プライベートでいろいろあったり、悩んだりすることはあるわけでしょう。でもその苦悩する内面とか、一切音楽には出さないじゃないですか。
ハヤシ:まあ……そうですねえ。
——改めて訊きますが、それはなぜですか?
ハヤシ:……いやあ、面白いすね、今回のインタビュー(笑)……あのう、そこはずっと変わらないのかな。ウエットな感情というか……そういうものを音楽に取り入れたくない。ポリシックスのステージングとか自分の歌う曲は、生活と密着していたくないのよ。生活と密着した音楽なんて、自分はまったく作りたいと思わないから。
——なぜ?
ハヤシ:いやあ……この人どういう生活してるのかな、とか……そんなの興味ないでしょ。ポリシックスのライブや映像を見る人は、生活感とか感じたくないんじゃないかな。オレがそうなのね。DEVOの存在感ってそうだったし。あれをビデオで見た時の衝撃ね。それまでのロックの、革ジャン着た長髪の連中が演奏してて、酒瓶が転がってて、ケバい姉ちゃんが前で踊ってるみたいな、そんなイメージだったライブハウスに、突如あんな5人が出てきたらすごい衝撃だろうなと。彼らはふだん何してるかなんてまったく関心ない。ふだんの生活のことなんてまったくリンクさせたくない。1時間のライブの間だけでも、日常のことなんて全部忘れられる。自分のやりたい音楽はそうだし、チケットを買ってライブに来てくれた人には、1時間半の間現実を忘れて、その場でしか味わえない異空間を体験させてあげたい。だからMCとかも……震災が起こったときとかね、自分の中のバランスみたいなものがわからなくなったことはあったけどね。
——震災もそうだし、ふだんの生活でも落ち込んだりすることはあるわけですよね。でもそんな時でもポリシックスをやらなきゃいけないわけじゃないですか。そこで苦しんだことはありますか。
ハヤシ:ふふふふ(笑)……うーん……いや、そこではね、落ち込むこといっぱいあるけど、ライブやるときは関係ないなって思っちゃうけどね。見に来てくれるお客さんとかに対しては…でもみんなそういうもんじゃないの、ミュージシャンって?
——作ってる音楽のイメージと自分の実像があまりにも乖離しすぎてると悩む音楽家もいそうだけど……。
ハヤシ:ああ。それはあった。ありましたね、そういう時は。2003年かな。自分が自信をもって作った『National P』というアルバムがあまり売れなくて。そうしたらあるインタビューで「今の日本のポップ・ミュージックのマーケットで、そこを求めてる人は少ない」と言われて。マネージャーともそういう話をしてたところだったから、ああ自分のやってることって求められていないのかなって、悩んだ時期もありました。でも……だからといって、じゃあ何をするんだってなったとき、そこで音楽を変えるのか。でもやっぱりそんなのありえないと思って。そこで自分の中で何かが起こったんですよ。逆境だけど、なんとか状況を変えたいと思って。今の現状をぶち壊すような曲を作りたい。そこで生まれたのがなぜか「I My Me Mine」(2005年)なんだよね(笑)。そのときちょうど海外ツアーやり始めた時で、すごく受けたから「ああ、やっぱりこれでいいじゃん」と思えた。