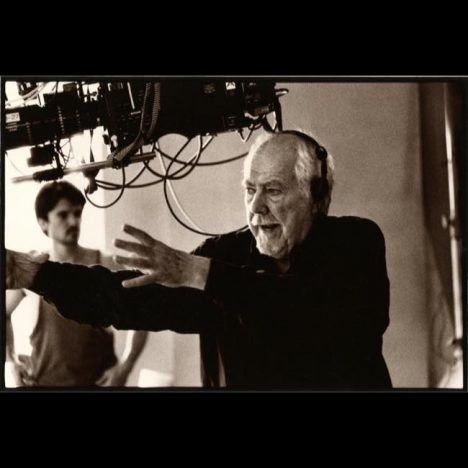橋口亮輔監督は新作『恋人たち』で何を描こうとしたか? 東京国際映画祭での発言から考察

不条理な世界のなかで心を病みながら、それでも寄り添うように生きていく夫婦を描き、報知映画賞最優秀監督賞、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞(木村多江)、ブルーリボン賞最優秀新人賞(リリ ー・フランキー)など数多くの賞を受賞した映画『ぐるりのこと。』(2008 年)から7年。まさしく待望と言っていいだろう、橋口亮輔監督のオリジナル新作長編映画『恋人たち』が、いよいよ全国公開される。それよりも一足早く、先頃閉幕した第28回東京国際映画祭の「Japan Now」部門に出品され、満員の観客たちから熱い喝采を受けた本作。本稿では、去る10月28日(水)、新宿ピカデリーで行われた公式上映後のトークショーに登壇した橋口監督の発言をもとに、この『恋人たち』という映画の背景と内容、そして監督が本作で意図したものについて考察していきたいと思う。
『恋人たち』が生まれるまで

橋口亮輔監督の近作に、『ゼンタイ』(2013年)という60分程度の小品がある。全身タイツを愛好する男女の悲哀をオムニバス形式で描いたこの映画には、有名俳優がいっさい出演していない……というか、本作は橋口監督のワークショップ(実践型演劇講座)に参加した俳優たちのエチュード(即興)をもとに作られた“習作”であった。そして、今回の『恋人たち』もまた、当初は『ゼンタイ』と同じく、監督のワークショップに集まったメンバーたちのために考えられた企画であったようだ。橋口監督は言う。「『ゼンタイ』は、ワークショップに参加してくれた40人ぐらいの人を全員起用して撮ったのですが、今回もそれと同じように、いくつかのエピソードをもとに作れるかなと思って……それはきっと、“恋愛の群像”を描くものになるんだろうなと思っていたものですから、それで最初に『恋人たち』というタイトルをつけてしまったんですよね(笑)。でも、なかなか『ゼンタイ』と同じようには作れなくて。で、これはやっぱりもう、100%ゼロから始めなきゃダメなんだと思って、ちょっと途方に暮れまして。ワークショップのメンバーには、いつ脚本が書けるか分からないけど、とりあえず脚本を書くからって言って……結局、脚本があがるまで、8ヶ月も掛かってしまいました」。
それに伴い、いわゆる“習作”として扱いから、プロの俳優も交えた“新作長編映画”へと企画が変わっていったという本作。その脚本を書くうえで、監督が留意したポイントは、以下の3つであったという。「まず、ワークショップに参加してくれた彼ら(篠原篤・成嶋瞳子・池田良)ありきの企画ですから、彼らの個性を活かしたものにしなくてはならないと思いました。ただ、それで2時間の長編を作るとなったら、『ゼンタイ』のようなエチュードだけでは、とてもじゃないけどもたない。だけど、これまでの長編映画のように、僕自身のなかにあるものを100%出すような映画を作るとなると、アマチュアに近い彼らにそれを背負わせしまうのも、なかなか荷が重い。だから、その配分を考えながら、彼らの個性も活かしつつ、僕自身のモチーフも描きつつ……なおかつ、それをやるなら、今の日本の空気といったものも盛り込みたい。この三本柱を同時に考えながら、いろんな役者さんの顔を思い浮かべて……この役は木野花さんに頼もうとか、この役は光石研さんに頼もうとか、このいい加減なやつの役はリリー・フランキーに頼もうとか(笑)。そうやって役者を当てはめながら、だんだんと脚本ができあがっていった感じなんですよね」。キャリアの異なる俳優たちが、違和感なく同じ世界に生きているように見せること。そこに何よりも監督は気を配ったという。
3人の登場人物について
映画は、明日に未来を感じることすら困難な“今”を生きる3人の登場人物たちの姿を並行して描きながら展開してゆく。通り魔殺人事件によって妻を失い、橋梁点検の仕事をしながら裁判の準備に奔走する男・アツシ(篠原篤)。そりが合わない姑、自分に関心を持たない夫との平凡な暮らしに突如現れた男(光石研)に心を揺り動かされる主婦・瞳子(成嶋瞳子)。親友への想いを胸に秘めたゲイのエリート弁護士・四ノ宮(池田良)。この3人のキャラクターは、それぞれ監督自身のどんな思いが託されているのだろうか。「簡潔に言いますと、主人公のアツシという役は、僕が『ぐるりのこと。』という映画を撮ってから体験した、さまざまな感情が反映されています。ある意味、僕自身と言ってもいいかもしれない。主婦・瞳子に関しては、僕の実体験というよりも……僕が15歳の頃に両親が離婚して、18歳のときに父が38歳で初婚の女性と再婚したのですが、そのお嫁さんを見ていて、「この人は、こんな結婚をして幸せなんだろうか?」と思った記憶がありまして。その父が、3年ほど前に亡くなったのですが、彼女は最後まで連れ添って……すごく幸せな、充実した人生を送っていたようなんです。人の幸せというものは、傍から見ていては分からない。そんな僕の思いも、瞳子には投影されています。だから、瞳子は、けっして不幸せな女ではないというふうに、僕は描いたつもりです。そして、もうひとりの登場人物、弁護士の四ノ宮に関しては……彼は心に欠落を持った人間です。映画のなかで、看護師さんが四ノ宮に「痛いですか?」と聞いて、彼が「いえ、痛いかどうか、よく分からないです」と応えるシーンがありますが、あの台詞は、自分の心が痛いのかどうか、自分が傷ついているのかも、本人は分からないという意味を込めた台詞でした。肉体の欠損は見えやすいけど、心のなかの欠落は見えづらい。そのことのほうが、本当はものすごく重いことなんじゃないだろうかというふうに思って、この3人のキャラクターを作りました」。