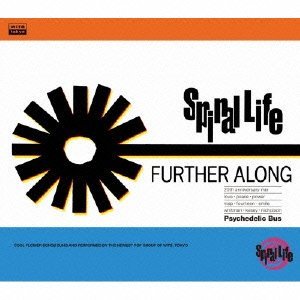石田ショーキチが語る「激動のシーン20年」(第1回)
デビュー20周年の鬼才・石田ショーキチ登場 Spiral Lifeと90年代の音楽シーンを振り返る
1993年にSpiral Lifeのメンバーとして、1stアルバム『FURTHER ALONG』で音楽界にデビューした石田ショーキチ(当時は石田小吉と表記)。約3年という短い活動期間ながらも鮮烈な印象を残したSpiral Lifeを経て、Scuderia Electro、MOTORWORKSといったユニットで精力的に活動する一方、音楽プロデューサー、エンジニアとしても大きな足跡を残してきた。彼はまた、ポピュラー音楽史に関する知見や、音楽業界やシーンに対する鋭い分析眼にも定評があり、リアルサウンドでもぜひ詳しくお話を聞きたいと考えていた。全3回でお届けする集中連載インタビューの第1回目では、デビュー作を新たにミックスした経緯から、Spiral Lifeが目指したもの、さらには90年代の音楽業界についても語ってもらった。
――石田さんがSpiral Lifeのメンバーとしてデビューしてから今年で20年。先日、1stアルバムを『FURTHER ALONG-20th anniversary mix-』として新たにミックスされましたが、20年ぶりに同作と向き合ってみて、どんな感想を持ちましたか?
石田:「自分のものであって、自分のものでない」という感覚でしたね。こういう音楽家は多いと思うのですが、僕はマスタリングまで終わったら、自分の作品を聴かないんです。それどころか、家でも音楽をあんまり聴かないので、まさに“作りっぱなしの20年”だった。『FURTHER ALONG』が僕にとって大事な作品であることは間違いないけれど、いざマルチデータを開けてみると、「こんな曲あったっけ?」という曲もあるし、どこまで自分で演奏して、どこからサポートミュージシャンにお願いしたかわからない曲もある(笑)。ある意味で、初めてプロデュースする若者と向き合うような感覚もありました。
――今の視点から見て、何か新しい発見はありましたか。
石田:いろいろ驚いたことはありました。特にコーラスのハーモニーに対するこだわりはすごかったな、と感じましたね。自分自身が60年代のイギリスの音楽に傾倒して音楽を始めたところがあるので、それが如実に、一点の曇りもなく出ていたところが面白かったです。The Beatlesはもちろん、AnimalsやThe Holliesといったリバプールサウンド、イギリスのビートバンドのコーラスワークを徹底的に模倣していた部分がありました。自画自賛するわけじゃないけれど、これまでたくさんの若者のプロデュースをやらせてもらった中で、20年前、若者だった自分たちのようなコーラスワークができる若者たちにまだ会っていません。自分を褒めてあげていいな、とちょっと思いましたね(笑)。
――Spiral Lifeは60年代のビートバンドの影響を受けつつ、当時のオルタナティブ・ロックの音色やムードも取り入れていましたね。
石田:根幹としてメロディやハーモニーを徹底的に美しいものにした上で、当時でいう現代的なギターロックにしたいという気持ちがありました。それを先にやっていたのがTeenage Fanclubだったり、出てきたばかりのOasisだったりで、美しいメロディと轟音ギターが共存していた。そういうことを日本でも実現したかったです。ただ、あらためてマルチデータを聴いたら、ギターの音がけっこうしょぼかった(笑)。いろいろ理由があると思いますが、自分自身はズブのアマチュアで音作りがあんまりうまくなかったのはもちろん、ギターロックというジャンルでのギターの音作りに関して、エンジニアやプロデューサーなどのスタッフ陣もあんまり知らなかったんだと思います。そういうところにこだわりを持っている“大人”が当時、日本にはあまりいなかったんでしょう。なので、今回のリミックスでは、ギターの音質の作り直しにはかなり手を入れました。
――当時、世界的に起きていた新しいバンドの波を、“大人”の人たちはまだつかみ切れていなかったということですか。
石田:日本ではまだ、という感じでしょう。93年というと、まだ80年代のレコーディング技術の名残が本当に強かった。良い悪いではなくて、習慣的にそういうものだったんでしょうね。
――当時の音楽シーンでは、過去の音楽を掘り起こして新たに解釈するムーヴメントの「渋谷系」があり、Spiral Lifeもそのひとつとして語られるところもありました。ただ、ご本人たちはそれを否定していましたね。
石田: 「渋谷系の括りに入れられているな」ということは、自分でも理解していました。コアな渋谷系の人たちからは「あんなの渋谷系じゃない」と言われましたし、僕たちはもう少しロック的なスタンスにいると思っていたので、自分たちが渋谷系だとは考えていなかったですね。渋谷系って、レコード屋さんでソフトロックやR&B系をサクサク漁る人たちのもので、人が知らないものを掘り起こしてきてサンプリングする“悪戯”の音楽ですよね。僕たちもそういうことをやらなかったわけじゃないけれど、基本的に「ロックである」という思いがあったから、立ち位置は少し違ったと思います。アメリカでグランジの盛り上がりがあって、そこに同調したいという気持ちは、特に車谷くんには強かったみたいですし。