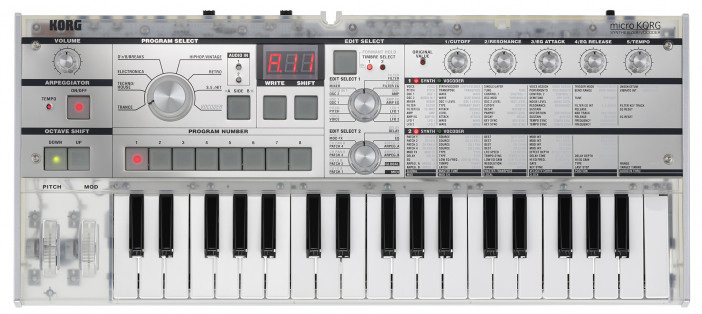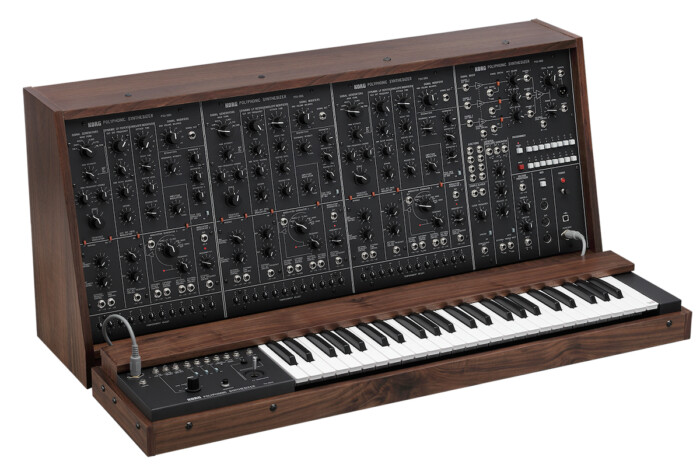マルチ・ミュージシャン、武田理沙が語る『miniKORG 700Sm』の“遊び心”

1973年にKORG初の量産型モノフォニック・シンセとして登場したこのシンセサイザーの名器『miniKORG 700』。その復刻版である『miniKORG 700Sm』がこの度発売された。
『miniKORG 700Sm』はオリジナルサイズよりも少しコンパクトに作られており、スプリングリバーブ、アルペジエーター、ジョイスティック、アフタータッチ、プログラムメモリー、USB端子、MIDI IN端子やCV/GATE IN端子など、『miniKORG 700』に搭載されていなかった機能も追加されているうえ、オリジナルの大きな特徴であった"太く、クリアで抜けの良いサウンド"は健在だ。
今回はそんな同機について、ドラムに鍵盤などさまざまな楽器を使いこなすマルチミュージシャンの武田理沙にインタビュー。彼女が愛機として使用する『KingKORG NEO』との比較やKORG製品への愛と共に、『miniKORG 700Sm』の面白さについて語ってもらった。
ターニングポイントとなった“実験音楽”との出会い

ーー音楽活動を始めたきっかけを教えていただけますか?
武田:音楽活動の原点は、3歳の時に母親から習わされたクラシックピアノです。そのころは音楽をやりたいという衝動はなく、とりあえず母の意向に沿って練習を続けていましたが、大学受験のタイミングで一旦辞めてしまったんです。
でも、辞めた途端に自分には音楽が必要だったということに気がついたことで、大学入学と同時に音楽活動を再開しました。ただ、そのころはいまのように本格的にやっていきたいというわけではなく「とりあえず大学に入ったらもう一度やってみるか」というくらいの気持ちでした。
ーー これまで聴いてきた音楽遍歴や音楽的な影響について教えていただけますか?
武田:最初に聴き始めた音楽はクラシックで、ストラヴィンスキーなどをよく聴いていました。そのころはまだ小学生だったので、音楽的な影響については考えていなかったんですけど、自分のなかではJ-POPよりもクラシックの方がより音楽に近いという感覚が何となくありました。
ただ、その影響が現在の私の楽曲制作にすごく大きな影響を与えているかというとそうではなく、いまはその時に興味があるものを作るという感じで音楽制作をしています。自分の思考回路というか、いろいろな方向に考えが広がっていく感覚をそのまま音楽にしているというイメージですね。
ーー現在は、ピアノ、ドラム、そしてシンセサイザーなど、さまざまな楽器を演奏されていますが、音楽活動再開後すぐにいまのようなスタイルに行き着いたのですか?
武田:音楽活動を再開した時、純粋に自分が衝動的にやりたいと思ったのがドラムでした。それで大学のジャズ研究会に入りました。初心者で楽器を始める方も結構いたので私も始められるかなと思って、思い切って始めてみたんです。そうしたらどハマりしてしまって、学生のころは真面目に講義を聞かずにずっとドラムの練習ばかりしていました(笑)。本当にハマると、そればかりやってしまうんです。
ーーシンセサイザーを使うようになったのはいつごろですか?
武田:大学卒業後に“実験音楽”と呼ばれている世界を知り、今度はそちらにどハマりしました。その時に気がついたのが、自分が音として認識しているのは、ピアノやドラムといった従来の楽器だけだったということです。でもその世界を通じて本来はあらゆる音が音楽になり得るということを知りました。
すべての音を音楽として捉えられるようになったら即興演奏をより一層楽しめると思ったんです。それでもっとも適しているのは何かと考えた時に、鍵盤の感覚には慣れていたので、1番いろいろな音が出せるシンセサイザーを選びました。そこから独学で勉強しながら、ずっとシンセサイザーのことを探求し続けています。