銀座の街にリズムを作る「余白」の重要性 Ginza Sony Park永野大輔に聞く“都市と公園”の新たなあり方

「半年以上先のことは決めない」「ソニー製品のPRの場にしない」というルール
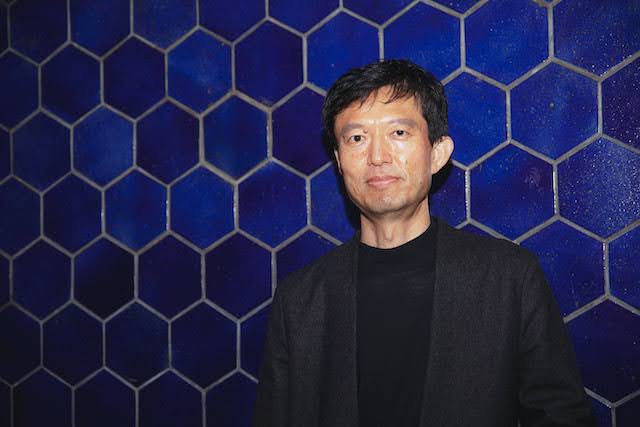
ーーパークの展示は、アートで固めることもできたの思うのですが、エンターテインメントやテクノロジーを融合した空間となっていますよね。この方向性はどのようにして決まったのでしょうか?
永野:今やっている「#014 ヌーミレパーク(仮)」は、Ginza Sony Parkが2018年8月にオープンしてから14回目のイベントなのですが、最初から何をするかを決めていたわけではなく、走りながら企画・決定していきました。
ーー以前、「半年先までのことしか決めない」とおっしゃっていましたね。
永野:そうなんです。ただ、オープンのときには1年間のルールとして「ソニー製品のPRの場にはしない」というルールを作りました。ここは公園であって、ストアでもなければショールームでもない。ここで製品をPRしてしまうと、公共性よりもビジネスを優先して銀座への恩返しは嘘ってことになっちゃいますから。徹底的に「ソニーが作る公園」にこだわりました。
ーーGINZA PLACEにはショールームがありますが、それとの対比の意味もあるのでしょうか?
永野:私は今まで、ソニーとお客さまとの関係の中で、ブランドがどう認知されるかを研究してきました。お客さまは、始めからソニーという会社をブランド認知するわけではありません。ウォークマン®やプレイステーション®など、コンテンツや商品が接点となって初めて会社が認知されるんです。Ginza Sony Parkも同じで、お客さまの1番近くにある接点として位置付けたんです。「ソニーってユニークで遊び心があるね」と認知してもらうためのインターフェースが公園なわけですね。
そのために徹底的に公園らしくしようということで、まず最初にローラースケート場を作りました。そのあとは、アーティストとコラボしたり、運動会をしたり。できるだけお客さまが公園だと意識できるように設計しました。
ーー初期の企画では、街に開かれた施設として、パブリックな展示が多いですよね。ところが2019年7月からのプログラム「#009 WALKMAN IN THE PARK」あたりから、傾向が変わったように思います。

永野:まさにそこが転換期でした。それまでは公園にこだわって、認知拡大のためにできるだけ開かれた場所にすることを意識していたんです。
そんななか、パークで取っていた来園者アンケートに書いてある「ここはどういう場所ですか?」という質問に対して、1位が「ソニーらしい場所」という回答だったことを知って。この空間自体がソニーらしいと思ってもらっていて、製品がなくてもそれは変わらないんだという確信に変わりました。この場所は公園であるという認知ができあがった。だからこそ、「#009 WALKMAN IN THE PARK」や、東京スカパラダイスオーケストラと作った「#010 MUSIC IN THE PARK」など、公園の中でソニーを全面に出したプログラムに挑戦しても問題ないだろう、という判断になったんです。

ーーエンタメ領域にシフトしていくフェーズですね。
永野:ショールームがメインのソニービルではできなかったことですね。昔のソニーはエレクトロニクスの会社でしたが、今ってエレクトロニクス、映画、音楽、金融、ゲーム、半導体の6つの事業があって、どの事業も業界のトップクラスのポジションにあります。「SONY」という会社名は変わってないんですが、事業は変わってきている。ブランド的にも、エレクトロニクスだけではなく、金融も、エンターテインメントもある会社だと認知してもらう必要があったので、ソニーの多様性を見せるという意味で、テクノロジーだけではない部分を織り交ぜていったんです。
公園とアート・音楽との共通点は「余白」 受け手側に解釈を委ねる

ーーそのなかで感じた手応え、例えば取り上げるジャンルにおける相性の良し悪しなどはありましたか。
永野:相性がいいのは、アートと音楽で、悪いのは、商品の展示などのプロモーションです(笑)。Ginza Sony Parkに来る人の半分は、目的をもっていなくて、通りすがりだったり、休憩だったり、待ち合わせをしたりなどで、何となく立ち寄る人が多いんです。そういう人たちに対して、場の方からプッシュしすぎてしまうと「何か買わなきゃいけない、話を聞かなきゃいけない」という圧を感じてしまうので、あまり居心地が良くないんです。だけど音楽やアートは、受け手側の解釈に委ねられているので、公園のコンセプトと同じなんですよ。要は、どちらも「余白」が多いということです。
ーーそういう意味で、テクノロジーを取り扱う際もアート的に見せているのでしょうか。
永野:そうです。「#009 WALKMAN IN THE PARK」のときも、ただテクノロジーや歴史を並べるのではなく、アートと絡めて展示をしました。アートの要素が入ることによって、ユーザーが接しやすくなる。ウォークマンを知らない世代の方たちも入って来やすいですよね。
ーーGinza Sony Parkで体験する展示は押し付けがましくなく、ビジュアルも洗練されていて、クールな印象を受けます。
永野:テクノロジーだけを前面に押し出した見せ方もあると思いますが、それはGinza Sony Parkとしての役割じゃないよと。お客さまからみればテクノロジーは商品や顧客体験を構成するひとつのツールですから。
ーー展示や制作に関しても、あくまでアーティストやコラボ相手を立てる手段としてテクノロジーを利用しているということですね。
永野:お客さまにも委ねていますが、アーティストにも委ねているんです。なぜ委ねられるかというと、余白があるから。公園には、いろんなものを受入れ、そして受け流していける度量があるので、街にも、お客さまにも、アーティストにも余白を提供できる。それをどう使うかはそれぞれ自由なんです。余白があるとアーティストは喜ぶんですよね。自由であればあるほど発想が広がるので、基本的には作り手に委ねた方が成功率は高いです。ソニーの商品を別の角度から編集してくれるおもしろさもあるので、私たちにとっても新しい世界が見られるのは魅力の1つですね。

ーーKing Gnuとmillennium paradeの世界観を再現した「#014 ヌーミレパーク(仮)」は、いろんなコンセプトやシナジーが一致した企画展示だと思います。パークのコンセプトと、今やりたいことと、彼らの才能がいい具合にマッチしていますよね。
永野:その通りで、一緒に創り上げてくれたPERIMETRON(ペリメトロン)のメンバーには感謝しかないです(笑)。ユーザー、クリエイター、街に委ねると言ったのですが、クリエイターの解釈は自由でありながら、どこまでやっていいんだろうっていう遠慮もある中で、絶妙なバランスですよね。
彼らには「Ginza Sony Parkをジャックしてくれ」と言ってあったのですが、この場を理解して、リスペクトして、会社を知ってもらった上で、ここでしかできないアートワークを展開してくれました。うまく着地点を見つけられた、とても良い経験です。
ーーイベントスペースの中には、コンセプトがしっかりあって、その世界観にぐっと引き込むような作りの場所もありますが、それとは対照的な存在ですよね。Ginza Sony Parkは開放的で、ふらっと立ち入りやすい空間を前提に作られている。
永野:アーティストの中には、それを嫌う人もいるんですよね。横を見ると地下鉄のコンコースだし、オープンしている間は扉が1つもなくて半屋外なので、世界観を作り込みたい人からすると、やりづらいと感じるようです。
そこを含めておもしろがれるかどうかだと思っていて、アーティスト側に寛容さがないとフィットしないかもしれません。
ーーこれまでのアーティストは見事にハマってきていますよね。
永野:その理由として1つ言えることは、会社や団体ではなく、人をみているからだと思います。「こんなおもしろいことをやってるんだけど、一緒にやらない?」と声をかけて、「おもしろいね」と言ってくれる人をメンバーに引き入れる。次はその人から、「こんな人いるよ!」と紹介してもらう、そんな感じでやってきました。King Gnuにしても、スカパラ(東京スカパラダイスオーケストラ)にしても、最初から決まっていたわけでなく、一緒にやれそうな人をたどっていったら、実現しました。きっかけは全部、人ですね。
そしてその方がスピードが早いです。ハイコンテクストで話ができるから、ゼロから詳細な企画書を作って、先方の上司を介してっていうプロセスが今まで1回もないんです。人を決めれば、その人が周りの人を説得してくれますから。
ーー間に入る人の数が少ないので、話の齟齬もないですよね。
永野:ないですね。大手企業だといろんな承認がいるじゃないですか。それがないのがいいですよね。逆にいうと、今回のPERIMETRONが何をやるのか、ビジュアルの最終形は聞かされてなかったんですよ。現場でアドリブで仕上げることが多かったです。地下鉄のコンコースのポスターだって、朝来たらすごいものが出来上がっていて(笑)。これは事前承認した覚えがないんですけど、おもしろいからいいか、と受け入れました。齟齬なく組んでいるクリエイターを信頼して、委ねているわけです。















