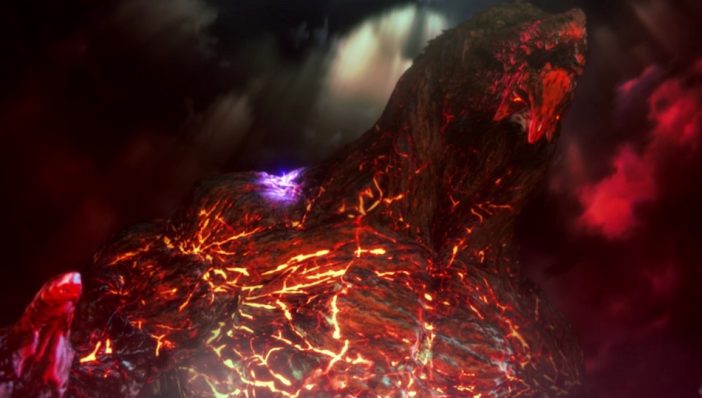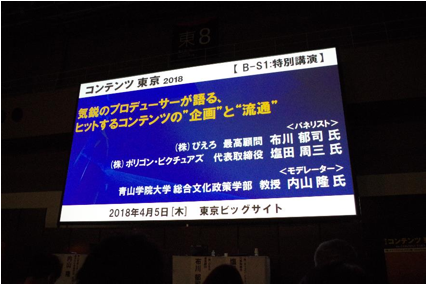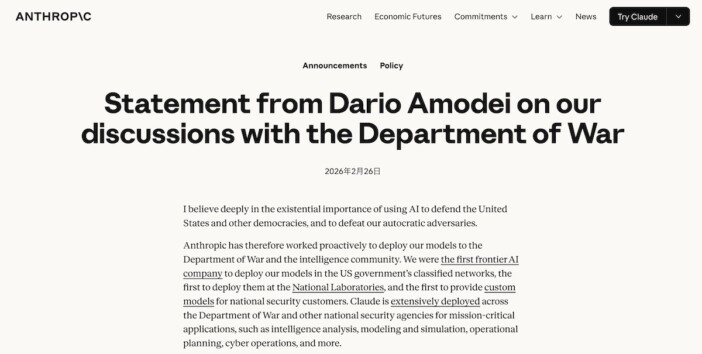日本のアニメはなぜフルCGを忌避し“ハイブリッド”な画面づくりを続ける? その理由を読み解く

高畑勲監督が行った革新的な試み
日本の劇場アニメーションにディズニーのような大転換が起こらず、グローバルな波に乗ろうとしなかったということは、業界的な保守性や、アメリカなどに比べて卓越した才能が多く現れていないという、ある種の不幸がある。そのようなアニメ業界全体を大きく俯瞰し、この問題に最も敏感に反応していたアニメーション作家は、先日亡くなった巨匠・高畑勲監督であったように思える。
高畑監督は、アニメーション表現を新しいものにするため、常に限界を探り新しい要素を投入してきた。その深い知識や哲学を基に、『アルプスの少女ハイジ』(1974年~)や『赤毛のアン』(1979年)など生活描写を丹念に描くことで、アニメーションによって人間の本質に迫ろうとした試みはもちろん、『おもひでぽろぽろ』(1991年)では従来の“アニメ的”な絵からの脱却を模索していた。
ヴィジュアル面において、試みがついに核心をとらえたのが、手描き表現をデジタルに変換したうえ、それがむしろアナログ的な画面を作り上げていたという奇妙さを持つ『ホーホケキョ となりの山田くん』(1999年)だった。この作品、どう革新的だったのか。
通常、手描きアニメーションの作画作業は、動画と背景に分けられる。従来は背景の描き込み量を増やすことで、画面をリッチにするということが行われてきた。そしてこれは、スタジオジブリにおいて高畑監督自身が推し進めていたことでもある。だが、背景を詳細にすればするほど、動画となるペタッとした色で塗られたキャラクターは平面的で、全体の調和がとれなくなってしまう。
高畑監督がリスペクトする、カナダのアニメーション作家フレデリック・バックの『木を植えた男』(1987年)などの作品は、特殊な方法によってスケッチ画をそのまま動かすような質感のアニメーションを制作していた。高畑監督が目指したのは、このような動画・背景の区別なく、全てが同じレベルで動くフルアニメーションの世界を、商業アニメーションの安定的な制作環境のなかに落とし込むことではなかったか。そして同様の試みにおいて完成度が飛躍的に上がったのが『かぐや姫の物語』(2013年)である。