『シン・仮面ライダー』には“子ども成分”が足りない? “特撮ファン”宮下兼史鷹が分析
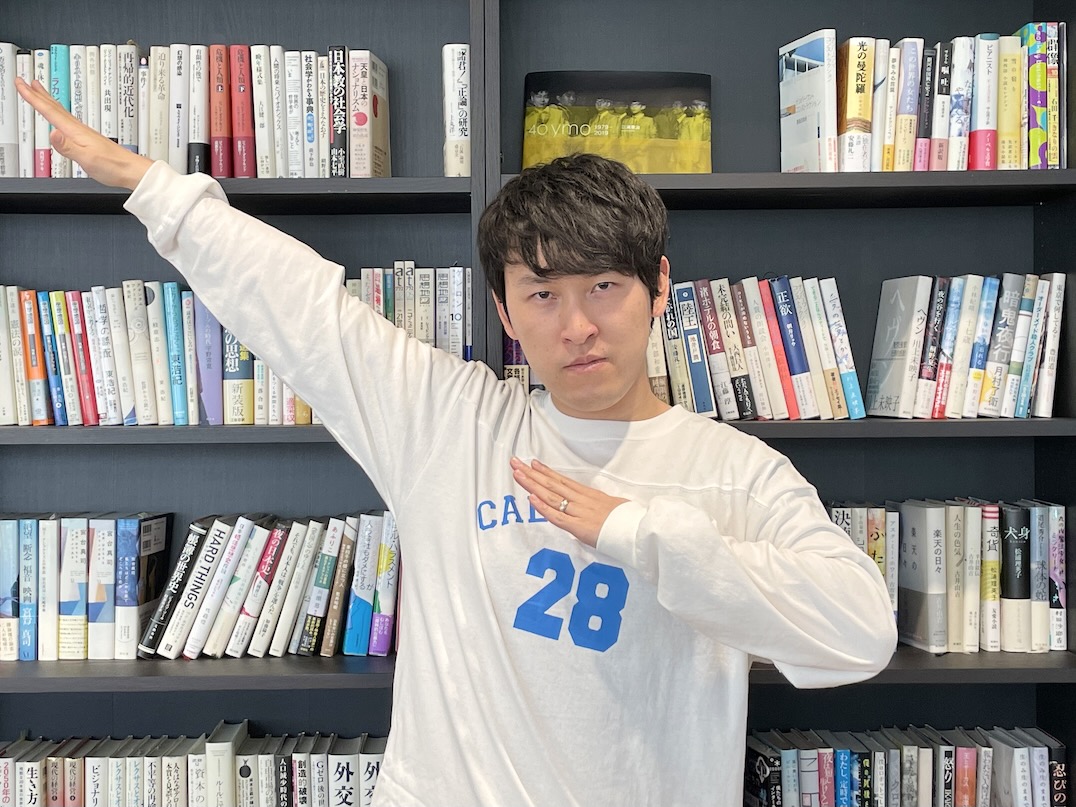
お笑いコンビ・宮下草薙のツッコミとして活躍する宮下兼史鷹。芸人としての顔以外にも、ラジオや舞台など多岐にわたる活躍をしている。おもちゃ収集が趣味、サブカルチャーに精通している無類の映画好きである彼の動画連載『宮下兼史鷹のムービーコマンダー』。第6回となる今回は、全国公開中の映画『シン・仮面ライダー』の魅力について語ってもらった。
TVシリーズを2時間の映画にまとめる難しさ
――『仮面ライダー』が大好きな宮下さんにとって『シン・仮面ライダー』はどうでしたか?
宮下兼史鷹(以下、宮下):まず、僕は生粋の『仮面ライダー』大好きっ子でして、子供の頃に最初に触れた特撮、およびヒーローが仮面ライダーでした。『シン・仮面ライダー』に関しても、子供の頃にやっていた“ごっこ遊び”のような、僕らの想像した理想が実は形になっていて、それって割とすごいことだなと。あれを映像化するって、いろいろな段階や評価を経ないとなかなかできないから、“庵野秀明監督にしか作れない仮面ライダー”として、僕は割と楽しく拝見させていただきました。
――本作は庵野秀明監督による『シン』シリーズ第3弾となりますが、『シン・仮面ライダー』はこれまでの『シン』作品と比べてどのような立ち位置にあると思いますか?
宮下:『シン・ゴジラ』は改めて「ゴジラ」という題材の面白さ、怪獣の素晴らしさが万人に伝わるように撮られている映画だと思いました。あれで日本が誇る「ゴジラ」がどれだけすごいかって再認識されたことが僕はとても嬉しかった。『シン・ウルトラマン』も万人にもわかるし、『ウルトラマン』ファンからすると唸るような演出もあって、好きな人だけではなく、そこまで知らない人でも楽しめる作品になっていた印象があります。そういう意味では、今回の『シン・仮面ライダー』は最もマニアックだと感じました。本当に庵野監督のやりたいことを全部詰め込んだのだと思います。これまでの『シン』シリーズとは少し離れたところにある、別物なんですよね。
――なるほど。
宮下:『シン・ゴジラ』って、そもそも題材である『ゴジラ』(1954年)が2時間のドラマとして作られた映画なんですよ。だから新たに映画化しても、違和感なく“映画”でした。ただ、『シン・ウルトラマン』と『シン・仮面ライダー』はもともと特撮番組で、子供が観る時間帯に、コマーシャルを抜いて約20分の1話完結ものとして作られていた作品です。それを2時間の作品にまとめる時点で、ただ映画をリメイクするのとは違う難しさがあるので、それを知っている特撮ファンは、ちょっと優しい目で作品を観ていると思います。『シン・仮面ライダー』は、顕著に「1話、2話、3話、最終話」みたいな作り方が印象的で、1つのまとまった作品として評価がしづらいんですよね。はっきりと「ここから1話、ここから2話」とは言われませんが、「あ、今ここから2話の感じだな」「話が切り替わったな」って感じで観ると違和感がないです。特撮好きなら本作が割と受け入れられる、というのは、それに慣れているかどうかが関係していると思います。
――確かに、『シン・ゴジラ』と『シン・ウルトラマン』『シン・仮面ライダー』では、そもそもの前提が大きく違いますね。
宮下:ただ……そもそも僕がなぜ『仮面ライダー』が好きかって話になりますが、それはやはり仮面ライダーが子どもを助けるからなんですよ。それがすごく身近に感じられたんです。子どもが「お兄ちゃん! お兄ちゃん!」ってやってきて「お父さんの様子が変なんだよ」と仮面ライダーに訴える。すると「なにっ、じゃあ俺が様子を見てやろう」って見に行くと結局怪人の仕業だった。それで倒して解決した後に「ありがとう、お兄ちゃん」って子どもが言う。そういう意味で言うと、『シン・仮面ライダー』には“子ども成分”が足りていなかったと感じました。TV版では、「その短パンどこで売ってるの?」って聞きたくなるような小太りの少年が駆け寄ってくるわけですよ。演技も達者ではなく、本当に子どもらしさを感じさせる子が「助けて」って言って、その子の「ありがとう」を聞けるところが『仮面ライダー』の好きなところなんです。『シン・仮面ライダー』はそれがないことによって、仮面ライダーが何を助けているのかがよくわからなかった。まあ、ヒロインを守るって話がずっと続いて、その後は人類のために戦うわけですが、守っている者たちの顔が浮かばなかったんですよね。だから、何を守っているのか、そこまではっきりと伝わってこなかったのが、本作にもう少し頑張ってほしかった部分ですね。本来ならやはり、ラスボスと戦っているときに助けを求めた子どもの顔が浮かんだりするんですよ。「負けないでライダー!」ってあの子が言っているんだろうな、と想像して感動するのが僕にとっての『仮面ライダー』なんです。
――言われるまで気づきませんでしたが、確かに本作には子どもが一切登場せず、主人公の本郷猛(池松壮亮)とチョウオーグ(森山未來)らが子どもの頃から抱えるトラウマに向き合う話でしたね。
宮下:そうなんですよ。まあ、劇場には子どもの頃から本当に『仮面ライダー』が好きだったんだろうな、という世代のお客さんが多かったので、彼らが子どもに還って映画を観るという点では“子ども要素”はあったかもしれませんが、劇中にもそれを感じたかったですね。
――ヒーロー側のキャラクターでは、柄本佑演じる一文字隼人が“推し”とのことですが、敵側で気になるキャラはいましたか?
宮下:物語のターニングポイント的な意味で印象深かったのは、やはり西野七瀬さん演じるハチオーグですね。ヴィランや怪人の中には愛すべきキャラがいたり、憎めない奴がいたりしますが、ハチオーグはちょっと思想が変態なんですよね。浜辺美波さん演じる緑川ルリ子に対して少し歪んだ友情の描き方をされていて、正直キャラクターだけで言うと「なんだこいつ」って感じなんですけど、西野さんのビジュアルだけでここまで許せるんだ、って。シンプルに「ルックスってすげえ」って思いました(笑)。西野さんだからこそ成立している点を見ると、庵野さんの「この人にこのヴィランをやらせよう」という采配の面白さやすごさが出ていたのかなと思いました。
――衣装やヘアメイクも物にしていて、何よりあのヘアスタイルでどこから映されてもかわいいのがすごいですよね。
宮下:いや、本当に。僕は普段、中じゃなくて“ガワ”が好きなタイプなんですよ(笑)。仮面ライダーのビジュアルがカッコよくて好きだから、変身すると嬉しいんですけど、今作のハチオーグだけはマスクを被ったときにちょっと残念でした。「ああ、隠しちゃうんだ……」って(笑)。それくらい変身前も魅力的でしたね。劇場でもらった特典カードで西野さんの顔が出たハチオーグのキラカードが当たったので、そこも含めて思い入れがあります。
――これまで宮下さんが感じてきた『仮面ライダー』シリーズに通底するテーマは、『シン・仮面ライダー』にも感じられましたか?
宮下:僕は仮面ライダーに限らず、ヒーローって身近な誰かの死で完成すると思うんですよ。親しい人が死ぬことで、初めてヒーロー活動というものに「こんな思いをもう誰にもさせたくない」っていう説得力が生まれると感じています。そういう意味で『シン・仮面ライダー』は僕が思い描いているヒーロー像や仮面ライダー像と、おそらく同じことを庵野さんも思っているんだろうな、ということが伝わってきました。本当に不謹慎な話ではありますが、僕は子どもの頃「そういう目に遭いたい」って思っていたんです。身近な誰かが亡くなるとか、そういう想像をしては、哀愁のある自分を半ば楽しんでいるみたいな節がありました。それから大人になって、21歳か22歳のときに初めてできた彼女と別れたんですよ。そのときに、「ものすごく悲しい」という気持ちと「あれ、完成したかも……」という気持ちの2つが浮かんで(笑)、その年のクリスマスに1人でラーメン屋に行ったんです。そうしたら、そのラーメン屋の店主が「クリスマスなのにあんさん、1人かい」みたいなことを言ってくれて、「ありがとう、そのセリフを待っていたんだよ……!」って(笑)。そういうことがありました。それくらい、僕は哀愁のある男に憧れているし、ヒーローって“哀愁”だと思うんです。だから、『シン・仮面ライダー』のライダーはものすごくカッコよかったし、哀愁漂う映画なので、僕の解釈と一致していて嬉しかったです。




















