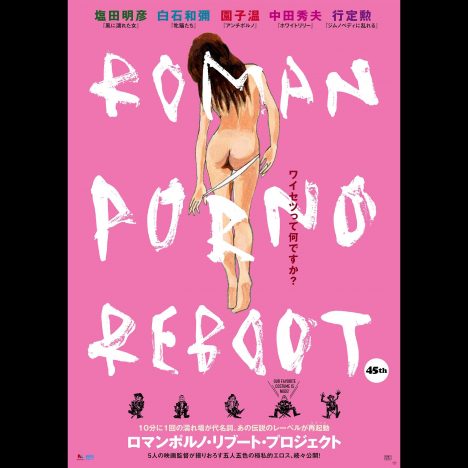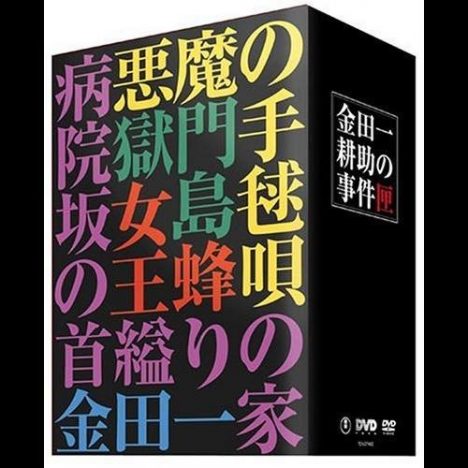庵野秀明、山崎貴に続くのは山田洋次と黒沢清!? 『海賊とよばれた男』が示す日本映画とVFXの関係
デジタル技術を掌握する者が映画界の主流になる

12月29日、NHK-BSプレミアムで『日本のVFXを変えた男 ヒットメーカー 山崎貴の挑戦』というドキュメンタリー番組が放送された。現在上映中の『海賊とよばれた男』の製作準備から完成までの1年にわたって密着した手のかかった番組で、これまでの山崎貴監督作品の歩みから、映画界入りした後、伊丹十三監督の作品でVFX(Visual Effects)を担当していた時代に原点を見つけ出す構成も申し分なく、山崎監督が所属する制作会社・白組の3DCG制作現場も垣間見える。山崎組では「広い駐車場とグリーンバック(合成用の背景)さえあれば映画が出来る」と冗談めかして言われることがあるが、実際、『海賊とよばれた男』の多くのシーンがスタジオのグリーンバックではなく、自然光のもと、駐車場か限られたセットだけで撮影され、本物と見分けがつかないほど巧妙に合成されていく過程を前後で比較しながら映し出していた。先日発売された白組の社史とも言うべき『白組読本』(風塵社)と併せて見るかぎり、今や白組は、かつての円谷プロダクションにも匹敵する日本のVFXで抜きん出た存在であることをうかがわせる。
今の時代に生きる映画監督に欠かせない能力は、VFXをどう活かせるかを判断する力にかかっていると言っても過言ではない。現実の世界には存在しないものから、失われた風景や建物の再現に至るまで、全篇にわたってCG処理を行う作品、ちょっとした1カットに特殊効果や修正が加えられる作品など、VFXが必要とされない作品は皆無と言っていいほどだ。もちろん、VFXを統括するスタッフがいるのだから、監督によっては専門家にお任せということもある。今の技術なら低予算映画でも、そこそこチャチにならないCG処理が可能なのだし、監督が余計な口を挟むよりスムーズに事が進むだろう。ところが、映画全体の印象を左右する重要なシーンがCGの場合、事前のイメージの共有、クオリティの見極めを監督が判断できなければ悲惨なことになる。

森田芳光監督は〈デジタル技術を掌握する者が映画界の主流になる〉と20年近く前に予言していたが、その森田ですら『模倣犯』(02年)のラストで不出来なCGの首が吹き飛ぶというシーンによって映画を台無しにしている。後に自身でも「あれがもう少しリアルにできていれば、ずいぶん印象が違っていたんじゃないかなと思う。結果的に、僕が抱いていたイメージとはかなり違った。(略)ちょっとCGが残念だった。時間的に間に合わなくて」(『森田芳光組』キネマ旬報社)と後悔を口にしていたが、ことほどさように映画の成否がかかる場面でも、リテイクする時間的余裕がないためにそのまま使用せざるを得なくなるという問題は、今に至るまで解決されていない(『模倣犯』の場合は他にも問題があるのだが)。
その意味で『シン・ゴジラ』(16年)は、撮影前にシミュレーション映像のプリヴィズ(Pre Visualization)を全篇にわたって作成し、それに合わせてCGが作成されていくことで効率化ならびに総監督・庵野秀明の特徴でもある緻密な画面構成がVFXにも反映させることを可能にした(実際にはプリヴィズからCGに移し替えるだけでは終わらず試行錯誤があったようだが)。
更に庵野が画面のレイアウトへの1ピクセル単位に至る微調整、コマ送りで画面を見ながら爆発シーンなどで特定のコマを抜くように指示したりと、まさにアニメーション演出の手法で判断を下したことで、従来の日本映画でVFXが監督の演出意図とかけ離れてしまう問題を乗り越えてみせた。度重なるCGへのリテイクによって公開ギリギリまで作業が進められるなど、庵野の粘り勝ちとも言えるクオリティ・コントロールが、日本製ゴジラをリブートさせることに成功したとも言えるだろう。このVFX作業の中心を担ったのも白組である。
『シン・ゴジラ』から半年を経ずに、白組と山崎の最新作となる『海賊と呼ばれた男』は公開されたが、同じ白組でも異なるチーム編成になっており、『海賊とよばれた男』は山崎率いる白組調布スタジオが、『シン・ゴジラ』は白組別働隊の手によるものである。ちなみに『Always 続・三丁目の夕日』(07年)の冒頭に登場するゴジラは調布スタジオが作ったもので、同じ白組によるフルCGゴジラでも全く別物と考えていい。白組スタッフの証言によると、庵野秀明がCG作業を終えた後、「調布のスタッフ、悔しがるでしょうね」(『別冊映画秘宝 特撮秘宝vol.4』洋泉社)と声をかけたというのも、そうした因縁があったからだろう。