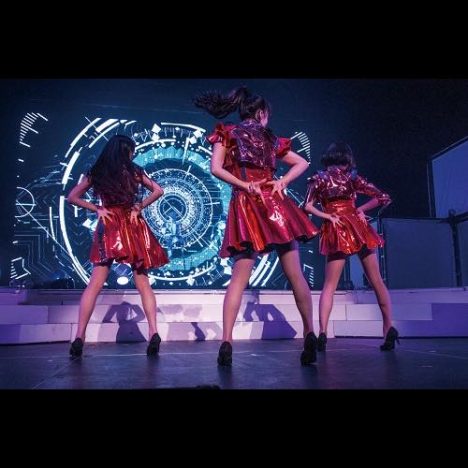橋口亮輔監督が傑作『恋人たち』で描く不安と絶望、そして微かな希望

「00年代におけるベストな邦画は?」と問われると、いつも個人的に是枝裕和監督の『歩いても 歩いても』と、それから橋口亮輔監督の『ぐるりのこと。』を挙げてしまう。これらが映画的に優れているかどうか以前に、私はある意味、この二作に人生を救われたとすら感じており、その気持ちはいまも変わらない。
後から気づいたのだが、『歩いても 歩いても』の公開日は08年6月28日。『ぐるりのこと。』は同年6月7日。これらがほぼ同時に世に出た08年6月とはいったい何だったのか。つい昨日のようでもあり、また、とてつもなく昔のような気もする。
とにもかくにも、あれから7年の月日が経過した。そしてコンスタントに映画を作り続ける是枝監督が『海街diary』を贈り出した今年、橋口監督は『ぐるりのこと。』以来7年ぶりとなる長編映画を完成させた。長きに渡る葛藤を乗り越えて生まれた待望の最新作。それが『恋人たち』だ。

この映画に正直、度肝を抜かれた。なにか「映画とはこうあるべき」とする概念や尺度が全く通用しない境地に到達したというべきか。一瞬一瞬の密度に心がどうしようもなく震え、そして役者たちの「剥き出しの凄み」に激しく圧倒された。
まず映画が幕を開けると、観た事もないひとりの役者が、独白を続ける。真剣な眼差しで妻との思い出について話し続けるのである。
たどたどしくて、演技なのか即興なのか分からないほどリアルな語調だ。もちろん我々は彼のセリフ回しや語りのリズムを初めて耳にするわけだし、それに九州弁のイントネーションも入ってくる。彼は何を言わんとしているのか。なぜこんな独白をしているのか。そもそも彼の身の上には何が起こったというのか。セリフは決して線形には進まない。道草をするかのように蛇行を繰り返す。でもこうしているうちに、我々の心はすっかりと橋口亮輔の新しい語り口の中に、深く深く入り込んでいる。
我々はここから3つの「愛」のかたちが群像劇として立ち上がっていくのを目撃する。主人公は3人。彼らはワークショップで才能を見出された新人俳優たちだという。登場人物のひとりは、かつて通り魔に妻を殺され、心が壊れかけてしまったアツシ(篠原篤)。ひとりは夫と姑との同居生活に愛も干上がり、別の男のもとへ走っていく瞳子(成嶋瞳子)。ひとりは完璧主義で自分本位な弁護士にして、長きに渡って同性の親友への愛を秘め続けている四ノ宮(池田良)。彼ら3人の物語が交互に描かれ(時に少しだけ交錯しながら)140分間という一瞬を織り成していく。