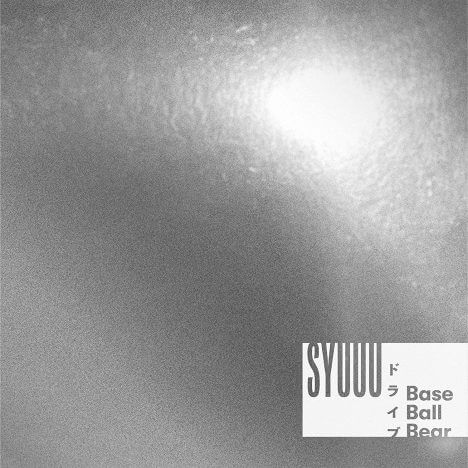material clubの新作で示したロック回帰 小出祐介が語る“正解”も“答え”もない自由な音楽の楽しみ方

Base Ball Bearの小出祐介を中心とするプロジェクト・material clubが、前作から6年ぶりとなる2ndアルバム『material club Ⅱ』をリリースした……と書いたそばから、現在のmaterial clubを“プロジェクト”と紹介するのには少々違和感があることに気づく。なぜかといえば、前作ではあくまで小出の“ソロプロジェクト”という色彩が濃かったそれが、今回は装い新たに「バンド」として再始動したからである。
そのメンバーラインナップは、前作でも制作のパートナーを務めたaccobin(ex.チャットモンチー)と成田ハネダ(パスピエ)の他に、キダ モティフォ(tricot)、YUNA(ex.CHAI)を加えた鉄壁の布陣だ。すでに各所属バンドやサポート活動を通じて、実力・個性ともに高く評価される面々が集った新生material clubが、今この時代に奏でる音楽とはいかなるものなのか。リリースへ至る経緯から、昨今のエンターテインメントシーンに対する思い、そして「やってみたいことをやりたいだけやりたいようにやっていく」というシンプル極まりないコンセプトについて、フロントマンの小出祐介にじっくりと話を訊いた。(柴崎祐二)
多彩な才能が集結した新material club
――前作から6年ぶりということで、なぜこのタイミングでmaterial clubを再始動させようと思ったんでしょうか?
小出祐介(以下、小出):明確なきっかけはあってないような感じなんです。2年前にBase Ball Bearの20周年に合わせた日本武道館公演があって、この後にどんなことをやっていこうかと話し合っている中で、アルバムを出すとしたら次で10枚目だということに気づいたんです。そこで僕が、「このままガーッと集中モードのまま10枚目にいくんじゃなくて、その前に少し変わったことを挟みたいな……」みたいなことをポロッと言ったんですね。そしたら、ドラムの堀之内(大介)さんから、「じゃあ、material clubをまたやればいいじゃん」と提案されたんです。そうやって話をしているうちに、僕自身もやる気になってきて。
――前作は打ち込みを主体とした作りでしたが、今回はバンドサウンドに変化していますよね。それはなぜなんでしょう?
小出:前作からだいぶ時間が経った中で、打ち込みで同じようにやるのが想像できなかったというか、単純にDTMの作業がめちゃくちゃめんどくさかったっていうのもあります(笑)。あとは、Base Ball Bearの活動を続けていく中で、バンドってやっぱりいいなっていう気持ちが高まってきたのが大きいですね。前回は色々な人たちを迎えてコラボレーションしていくというコンセプトがあって、あの時点では自分の中でもそういう手法が新鮮だったんですが、コロナ禍で世の中的にもむしろそういう手法がジャンル問わずより一層広がっていったじゃないですか。じゃあ、今回はやっぱりバンドでやるのがいいなと思ったんです。
――具体的には、どういった「バンドサウンド」を目指そうと思ったんでしょうか?
小出:その段階で「こういうものがやりたい」っていう明確なビジョンがあったわけじゃなくて、まずはメンバーの座組を固めるところから始めて、そこからは自然とBase Ball Bearとは違うものができていくだろうと考えていました。今回も制作パートナーとしてあっこ(accobin)に入ってもらって、同じく付き合いの長いナリハネ(成田ハネダ)にも前作に続いて参加してもらいました。キダ(モティフォ)さんは、一緒に赤い公園のサポートをやった時に、「この人、上手い!」と驚いて。エモーションと技術を両方持っているキダさんみたいな人はなかなかいないし、一緒にできたら面白いだろうなと思ったんです。YUNAちゃんは、Base Ball Bearの堀之内さんに「ドラム候補、誰がいいと思います?」と聞いてみたら、即答で彼女の名前が出てきたんですよ。CHAIでの演奏のイメージが強かったけど、Reiちゃんのサポートだったり、他の現場でもすごく多彩なプレイをしていると知って、すぐにアプローチをしました。結果的に、全パート第一候補の人たちが集まってくれることになりました。
――material clubの名前を冠しているということは、前作からの発展型であるという認識も当然あるんですかね?
小出:シンプルに新しいバンドを組んだ、っていうイメージの方が近いですかね。1stアルバムは初めからライブをやることを想定していませんでしたが、ライブができないことこそがウィークポイントだったんですよ。PC2台で音を流すとか、やる気になればやれたんでしょうけど、自分がそんなことをしている画が浮かばなくて。またmaterial clubをやるなら、生演奏でのライブを前提にしようと思いました。material clubっていう名前を引き続き使っているのは、屋号として気に入っているというのと、この名前があったからこそみんながこうして集まってくれたというところがあるし、当初の「普段やっていることとは違うことをやりたい」というストーリーもちゃんと回収してくれたという思いがありますね。
――皆さんの才能が「素材」として結集したというイメージ?
小出:そうですね。皆さん本当に個性のある人たちなので。
――共通する音楽的なルーツは何かあるんですかね?
小出:たぶん、ほとんどないと思います。影響元とかルーツの話とは別の部分で、それぞれのプレイヤーへシンパシーやリスペクトがあるので、そこがひとつのバンドとして大きいポイントじゃないかなと思います。演奏の面でも、曲作りのクリエイティブの面でもみんな上手くハモっている感覚があって。
――女性メンバーの割合が高いというのも特徴ですね。
小出:そうなんですよ。けれど、意識してそうなったわけじゃないんですよね。日頃から「この人は素晴らしい」って思っていた人を集めたらこうなったという。だから、よくある「女性ならではの演奏が魅力で……」みたいな感覚は一切ないですね。
――共作曲が多いことからもわかる通り、メンバーの皆さんが作曲にも積極的に参加しているというのも新たなポイントですね。
小出:ソングライター兼リーダーとして自分だけがバンドを引っ張っていくという形じゃなくて、全体を僕が取りまとめるにせよ、みんなが全員横並びの状態でやれているのが理想なんです。まずはみんなでワイワイやりたいっていう気持ちが強くて。
ストレートなロックへの思い
――アレンジもコミュニケーションを重ねながら進めていく形ですか?
小出:色々なパターンがあって、僕が土台を作っているものもあれば、ナリハネが作ってきたものに対してどうアプローチするかをみんなで解釈していったものもあります。キダさんきっかけのものもあるし、YUNAちゃんの作ったビートにあっこがシンセを乗せて、さらにメロディをそこに乗せたら、今度は元のシンセが変わって……みたいに、全員が有機的に絡みあいながら進めていった形です。
――スタジオでの録音は「せーの」で録っていった感じですか?
小出:基本リズム録りはそうでしたね。「Curtain part.2」という曲は、クリックを使わずに全員揃って演奏しています。
――この曲は特にロックバンド感が強く出ている気がしました。そういう意味でも前作とは本当に対照的なアルバムだなと感じます。メジャー/インディー問わず、このところの音楽シーン全体に「ロック回帰」的なムードがあると思うんですが、その辺りの空気についてはどう感じていますか?
小出:そういうムードは確かに感じますね。というか、「早くそうなってくれ!」と数年前から思っていました(笑)。それより前、具体的には6〜7年位前は、海外でもどんどんヒップホップが覇権を握るようになって、日本にもそういう流れがきていたと思うし、自分としてもそれを“別の畑”の出来事として傍観するんじゃなくてちゃんと対峙しなくちゃという気持ちがあったんです。それと、国内のメジャーなバンドシーンも少し飽和状態というか、頭打ち的な状況にあったと思うし、そういう状況への反発心も込みでmaterial clubの1stを作ったところもあって。けれど、さっきも言った通りコロナ禍を経て、今度は密室的で“狭い”音楽が溢れすぎているなという気持ちになってきたんですよね。あとは、それと連動してものすごく上手な演奏や高度な構築をする人も増えてきて、チルな音楽が増殖してきつつ、メロディアンサンブルが異様に複雑になっていく流れもあったり。そういう中で、「いや〜、さすがにもうシンプルなロックが聴きたいんですけど!」っていう気持ちが溜まってきて、「なんで誰もやらないんだよ」っていうイラつきが増してたんです(笑)。
――こんな言い方をするとアレですけど、小出さんって常に「逆」をいこうとしますよね。もっと言うなら、「ピュアな逆張り」をしようとする人。
小出:それは間違いないですね。Base Ball Bearもずっとそうですし、それが一貫した自分のスタンスなんですよ。大勢の人がなんとなく無意識的に同じことやっている状況の中に居続けるのが昔から嫌なんです。どうすればカウンターを打てるのか、ということは常に考えています。
――ストレートなロックは、今再びカウンターになりうる、と?
小出:そうです。Oasisの再結成が発表されてあんなに盛り上がるのも、みんなが潜在的に骨太のロックを待望していたことの表れじゃないかと思うし、潮目が変わってきている感じがするんですよね。実際、今年2月に出したBase Ball Bearのミニアルバム『天使だったじゃないか』も、そういう内容になっていると思いますから。
――けれど、今回の『material club Ⅱ』には、そういう「ロック最高!」というフレッシュな感情が反映されている思う一方で、どこか大人の成熟というか、抑制と奥行きみたいなものも感じます。
小出:それはメンバーが5人いることで、各人の個性が入り混じっているからそう聴こえるということかもしれませんね。せっかくこの5人で新しくバンドをやるんだから、バラエティパックみたいなアルバムにしたいという気持ちが強くありました。全部を勢いで押し進めるんじゃなくて、曲ごとのキャラクターの棲み分けをしたいな、と。
――歌詞の面でも直接的なパッションが表出しているというよりも、どこか俯瞰的な印象を受けます。
小出:あまり感情描写や内面の描写を中心に据えないようにしようという気持ちがありました。心情を歌った曲だとしても、あくまでも視覚的な表現を優位に置こうと考えていて。
――だからなのか、どこか往年の歌謡曲やニューミュージックの雰囲気も感じます。松本隆さんとか、阿久悠さんとか、それこそ小出さんが昔からお好きだというユーミンさんとか……。
小出:今名前の挙がった方々には実際すごく影響を受けているし、皆さん感情と景色のブレンドがめちゃくちゃ上手いんですよね。気持ちのことを歌っていたと思ったら、景色の描写になっていたり、その逆も然り。いわゆる“ストーリー”を滔々と語っているわけではないのに、物語が見えてくるというか。正直に言えば、日本語のポップスの優れた型みたいなものがそこで一旦出来上がってしまっているんですよね。だから僕も、今でも繰り返し聴いて研究したりしているんですけど。
――ただ、今回のようなサウンドとの組み合わせということでいうと、やはり新鮮な印象を受けました。
小出:それは嬉しいですね。ロックって、感情的で直接的な表現だと思われているぶん、歌詞の書き方がかえって難しいんですよ。熱いエモーションを叫んで、いかにもな“ストーリー”を語ろうとすれば上手くハマるとは思うんですけど、あまりにもそのやり口が横行しすぎていている気がして、だいぶ前から嫌になってしまって。日本のロックシーンを見渡すと一時期に比べたらそういう傾向も薄らいできた気もするけど、それでもみんなどこかで話の筋を考えることから歌詞を作ってしまっているような気がするんです。サビに感情の盛り上がりの頂点を持っていくことが自己目的化して、ありがちで起承転結的なストーリー構造になってしまっていたり。
――わかる気がします。
小出:だから今回のアルバムでは、そういうロックにまつわるムードや構造を一旦理解したうえで、感情に任せきった言葉を並べるのをいかに抑制するかを考えながら作りました。というか、音楽以外でもそうだけど、“ストーリー”って、絶対になきゃいけないものなのかなっていうのをずっと考えているんですよね。最近の映画を観ていても、どうしてこんなに強く手を引っ張るみたいにとにかく感情移入させようとする作品が蔓延っているんだろう、と疑問に思っていて。
――「主人公に感情移入できたか」とか「いかに共感できたか」のバロメーターが作品の優劣と比例するかのような考え方って、いまだに根強いというか、なんなら再び高まってきている気配を感じます。
小出:でしょう。映画に限らず、仮に感情移入や共感という軸だけで世の中を見ようとすると、それって相当怖い結果になると思うんですよ。むしろ、自分が思いもよらなかったことに出会ったりすることの方が遥かに楽しいと思うんですけどね。それで思い出したけど、先日黒沢清監督の『Cloud』を観てきたんですが……。
――もう、最高ですよね。ただ人がおかしくなっていく様を、冴えまくったカメラで冷徹に映し出していくっていう。
小出:本当に最高。あんなにも感情的な次元で共感できない映画はないと思ったし、すごくひんやりしていてドライ。あんな荒涼としたものを今の日本で作っているということが何よりもカッコいいですよね。