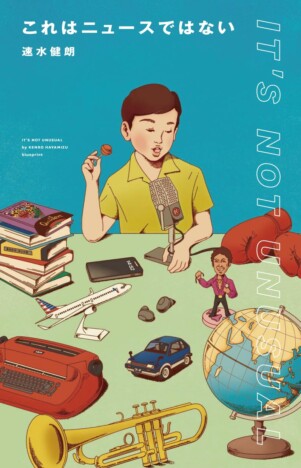フライング・ロータスが語る、『KUSO』と日本文化「三池崇史、塚本晋也、北野武は僕のヒーロー」

「この『KUSO』はみんなのために作ったんだ。本当だよ!」

監督のフライング・ロータスことスティーヴは、満面の笑顔でそう言い切った。『KUSO』(スティーヴ名義)と銘打たれた本作は、米『Esquire』誌に「史上最も気持ち悪い映画」と言わしめた珍作である。94分に渡って、不条理なストーリーとグロテスクな描写が続き、サンダンス映画祭では退席者が続出したとさえ謳われている。「KUSO」はもちろん日本語の「糞」のことで、本人曰く「アメリカでは全く問題がないよ。だってみんな意味がわからないからね。タイトルを教えたって『へぇ、KUSOかぁ。クールだね』で終わりさ」とのことだ。
物語の舞台は、大地震が起こった後のロサンゼルス。人々はみんな奇病におかされ、気の触れた状態で生活している。首に喋る“こぶ”ができた女、ある“とんでもない虫”で人を治療する医者、常にお腹を下している男の子、コンクリートを食べる女性……ひとりとしてまともな人物が出てこない群像劇を、ときにスチームパンク的な時代錯誤のテクノロジー描写を織り交ぜつつ、テレビのザッピングを通してコラージュ的に描き出していく。便器の中から顔を出して元カノを口説く男性もいれば、おっぱい恐怖症に悩む男性もいる。悪夢を見るのに近い感覚がありながら、妙に滑稽であり、時にハッとするような高尚さを感じさせる作品だ。
異質なものを切り貼りして組み合わさることで、観る者をギョッとさせるのは、極めてヒップホップ的な手法である。また、悪趣味な冗談が散りばめられた作風は、90年代の日本のサブカルチャーにおける「鬼畜ブーム」を彷彿とさせる。そうした方法論に、どこか音楽家としてのフライング・ロータスの作品群に通じる部分が感じられるのは、非常に興味深いところだ。

『ソニックマニア』への出演を控えて来日したスティーヴは、8月16日に渋谷シネクイントで行われた『KUSO』のプレミアム上映会に登壇し、本作を制作した理由やその意図を明かした。伝説的ジャズミュージシャンであるジョン・コルトレーンを大叔父に持つスティーヴは、2000年代よりヒップホップに新たな解釈を与える作品を次々と発表し、レーベル〈ブレインフィーダー〉の仲間たちとともに“LAビート”と呼ばれるジャンルを築き上げ、2010年代のあらゆる音楽シーンに多大なる影響を与えたアーティストだ。そんな彼がなぜ今、このような長編映画を撮ったのか。司会者に尋ねられると、「もともと音楽ではなく、映画の道に進もうと考えていたんだ。ハイスクールを卒業したあとは映画の専門学校に通っていたし、自分なりに映画作りを追求してもいた。でも、音楽方面で注目されるようになって、すっかり忙しくなってしまった。いつかは映像の仕事もしようと思いながら音楽活動を続けてきて、2014年にアルバム『You’re Dead!』をリリースした後に、ようやく少し余裕ができたから、念願の映画作りに取り組んだというわけさ」と、意外な回答をする。