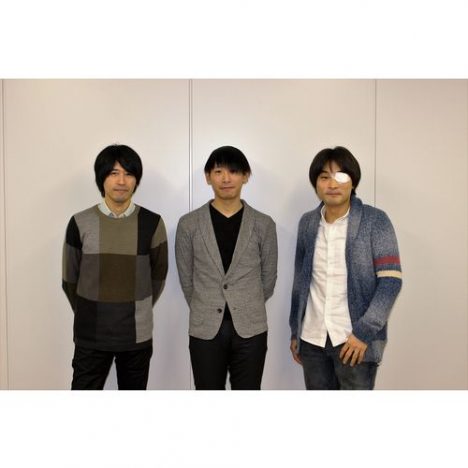2015年音楽シーン総括鼎談(後編)
「ガラパゴスも続ければムー大陸になる」論客3人が分析する、2015年の国内音楽シーン
クラムボン・ミト氏、柴那典氏、金子厚武氏による、2015年の音楽シーンを振り返る対談。前編では、サブスクリプションサービス普及がもたらした音楽シーンの変容、そして創作環境の変化を踏まえた、音楽的「筋トレ」の重要性などを語ってもらった。後編では、ヒットチャートのデータをもとに、2015年にヒット曲が生まれなかったという現状、アニソン・声優シーンの変化、音楽ジャンルやバンドという概念の“拡張”など、話は大きく展開した。
「音楽のことだけ考えて突き詰めるほど、絶対その音楽を聴く人のことを考える」(ミト)
――前編ではテレビの影響が再び大きくなってきたという話で終わりましたが、確かに、テレビを見ながらネットをする、SNSでコミュニケーションを取り合うことが当たり前になっている気がします。
ミト:テレビがコンテンツ化する、というよくわからないことになっていますね(笑)。レコード会社と言われているものも、もはやコンテンツの一部だから、多角的な視点で売るということを考えたときに、何か別のきっかけが生まれてくるような予感がします。僕たちが来年会場限定でCDを売るツアーをするのはまさにそこで。チケット代を抑えたぶん、普段他アーティストのライブで使っている金額との差額で、CDやTシャツなどのマーチャンダイズを買ってもらいたいから。
柴:海外だと、ブルックリンに『ラフトレード』のショップがあって。そこに行くと、商品の8割ぐらいがアナログ盤で、CDは試聴用と、「レコードプレーヤーを持ってない可哀想な人用」というレベルの展開しか存在しないんです。あと、倉庫を改造したような作りになっている店の奥にライブバーのようなものがあり、地元のミュージシャンが演奏して盤を売れるようになっているんですよ。日本でも『TOWER RECORDS』や『HMV』などがやっている手法ですね。
ミト:店舗もバンドと一緒に動いちゃえばいいと思うんです。ライブ会場がその日1日だけ『ラフトレード』のお店にするみたいな。僕たちはまさにそれをやろうとしてるんですけれど、昼イチぐらいからCD用の物販は開けておいて、専用のCD屋にしておく。
金子:『TOWER RECORDS』の方はライブ会場に物販として入っていて、どんどんそれが目立つようになっている気がします。
ミト:ただ流通媒体を経由することにより、売り上げをある程度持っていかれるということをバンド側が理解してない人もいるし、またその流通を通らない場合に発生する利益率がどれだけ破格かということをわかってない人も多い。そのメリット、デメリットを享受した上で面白いことをやるために、一度バンド側も独自な立場に立って、トライ&エラーをしなければならないと思っています。それを後押ししてくれたのはアデルであり、<XLレコーディングス>だったりするわけで。<WARP>もエイフェックス・ツインがグラミーを獲ったことで、かなりの負債を返せたはず。だからこそダークスターやハドソン・モホークにも予算を掛けることができて、EDMに押されて後退する一方だったテクノも、ようやっとブランド力を回復するようになりましたし。
柴:レーベルとしてもそうだし、業界全体としても、そのサイクルをどう太くするかというのが大きな課題ですよね。そこに注力しないと、どんどん文化としての豊かさが減ってしまう。EDMの話題がちょうど出たので話しておきたいのですが、2015年度の振り返りの原稿を書こうと思って、各チャートの年間ランキングを一通り調べたところ、1位は軒並み三代目 J SOUL BROTHERSの「R.Y.U.S.E.I.」だったんですね。でも、実はこの曲って、2014年に出たものなんです。三代目は2015年にアフロジャックとSTYが共作した「SUMMER MADNESS」という新曲もリリースしているのにも関わらず。これって、ネガティブな言い方をすると、2015年はモンスター的なヒット曲が生まれなかった1年といえる。ただし、逆に言うと、今までのように初週売上がいくらかどうかでヒットが決まっていた価値基準がロングセールス型に変わっているということも思います。
――2位はSEKAI NO OWARIの「Dragon Night」で、これも2014年の楽曲でした。
柴:海外のシーンを見ると、EDMはもうトレンドではないんです。シーンの盛り上がり自体はあるけれども、音楽のジャンルというより、ある種、ラスベガスの遊園地みたいなエンタテインメントとして受け入れられている。そういうものが、今年のJ-POPシーンにおいてもヒットし続けたというのは、ネガティブにとらえることもできるし、相変わらず日本はガラパゴスで面白いなとも思います。
ミト:まぁ、海外の文化がディレイするのは日本特有かもしれない。情報もニーズも少な過ぎて、10代のヤンキーでも学校へ行ってる普通の真面目な子でも、それが耳に届くまでに時間が掛かってしまっている。
金子:「R.Y.U.S.E.I.」が売れ続けていることと対照的に、AKB48の新シングル「唇にBe My Baby」が100万枚を切ったことも大きかった。ヒット曲の売れ方が初週で爆発的に売れるものばかりではなくて、長く売れ続ける方向にもし変わっていくのだとしたら、それはポジティブなことと捉えてもいいのかもしれないなと。
柴:そうですね。あと、セールスの話をすると、世界各国で記録的に売れているアデルの『25』は、日本ではそこまで売れていない。でもその状況を「おかしい」とか「恥ずかしい」とか批判するような考え方は間違ってると思うんです。決してグローバルに売れているものが、日本で売れるべきとは考えていなくて。日本の市場は特殊な上に、世界第2位という規模なのだから、アメリカとイギリスに右に倣えをする必要はないんじゃないかな。極論を言えば、もうインドみたいになればいいと思う。
ミト:インド?
柴:インド料理店にいくと、よく店のテレビでインドのヒットチャート番組がやってるんです。そうしたら大抵ボリウッド的なポップミュージックに乗せてインド人のダンサーが踊っている。でもそれを観た僕らは「インドはアデルが流行ってなくておかしい」とか「恥ずかしい」とか思わないですよね。その国独自のポップカルチャーがあって、それが海外から見ても面白いと感じる、という。
ミト:映画だとわかりやすいかもしれない。タイやアジアの映画は、ハリウッドと違う市場を持っているし、『ジェラシックワールド』もタイに持っていくと単館上映なわけですからね。
柴:日本独自の文脈でいうと、μ’sも海外の人にとっては受け入れづらいでしょうね。アニメの中で女の子が歌い踊っていることは理解できるだろうけど、その女の子たちと同じ声を持つ人がリアルでライブをしているわけだから。エンタテインメントも文脈もわからなければ、よくわからないスペクタクルですよね(笑)。
ミト:そうでしょうね。背景を知らない状態でμ’sをみて「すごい」と感じることはなかなかないと思います。今のアニメシーンで起こっていることは、ずっと追っかけてきたいちファンからすると、ちょっと過剰なんじゃないかと感じていて(笑)。僕たちの中で大切にしていたものが、今はこれだけカジュアルになってしまった。それを否定するつもりはないけれど、ある程度全体像を把握していないと誤解を生みやすいコンテンツが多いんです。かつては声優さんにルックスなんて、そこまで必要とされていなかったし、担当したキャラクターがどのタイミングで何を歌い、何のセリフを言ったかが重要だった。μ’sが『紅白歌合戦』に出ることは。喜ばしいのと同時に、その文脈がわからない方に叩かれるのが怖かったりもする。
柴:アニメにはもとからカウンターカルチャー性が備わっていますからね。『ハッピーマテリアル』がオリコン上位になったときに、J-POPファンからいろんな意見が上がって炎上状態になったのもそういうことじゃないですか。でも、いまはそれが当たり前になったし、逆にJ-POPファンという界隈が勢力を失っている。
金子:アニメ文化に比べるとすごく圧縮された短い期間ですけど、ニコ動の中でも同じようなことが起きていますよね。刺激的だったものが、だんだん簡略化されていって、それに対して昔からニコ動にいた人たちが「つまんなくなった」とこぼしはじめている。でも、そういう流れがあったからこそ、米津くんみたいな人が現れてきて、国民的スターになれるくらいの勢いを持っているのは、アニメが辿ってきた長い歴史とのシンクロを感じます。声優さんが裏で活躍することを望んでいる人たちと、ボカロPに顔出しをしないでいてほしいというファンの願いも同じようにみえます。
ミト:それ、よくわかるわぁ(笑)。
柴:今の時代は、アニメもボカロもアイドルもロックバンドも、シンガーソングライターや歌手が担ってきた狭義のJ-POPも含めて、すべてが広義のJ-POPになろうとしていると思うんです。ただ、そうなってくると『紅白歌合戦』などのマスな媒介を通して世間の目を引くことはできても、なかなか音楽の方に注目が集まりづらい。そのために音楽家たち、メディアに何ができるかが課題のように思えます。
ミト:その話を聞いて思ったんだけど、「ミュージシャンは音楽のことだけ考えれば良い」という風潮がありますよね? でも、音楽のことだけ考えて突き詰めるほど、絶対その音楽を聴く人のことを考えると思うんですよ。作った音楽が人を不快にさせようと、驚かせようと、喜びや悲しみを与えようと、その人を“感じさせて、動かす”ことができたら、それは“感動”なんです。それをはき違えたり、わかっていない人たちに限って、バンドというプラモデルのキットで、自分の好きなカタチを作っているだけみたいなことが多い気がします。
金子:音楽以外も含めて、芸術はコミュニケーションじゃないですか。それが、CDの危機を経て、レコード業界・音楽業界全体に不安が過ったことで、「CDだけでも音楽だけでもないんだ。もっと芸術であるべきなんだ」というところに立ち返っているように思います。り、ニコ動などのプラットフォームが加わったことは、その意味でもとても大きかった。すべての背景にコミュニケーションがあるわけだから、そこを更新しようという動きになっているというか。
柴:音楽は機能性があるもので、タイアップソングなどでは、それをどれだけ研ぎ澄ませられるかという勝負になる。一方、自分の好きなことを表現して多くの人を感動させたいというミュージシャンもいる。これを相反するもののようにとらえている人は多いのですが、「機能性に応える」というのは、音楽のもつ力や人に影響を与える力と、コミュニケーションの誘発という3つをそれぞれが突き止めた結果だと思うんです。
ミト:聴き手がより話題にしたいものになっているかどうかですよね。マニアックな話になりますが、SUPER JUNKY MONKEYが最初にニューヨークでライブをやったとき、終演後にKISSのマネージャーに「前座やらないか」と持ち掛けられたそうなのですが、「KISS? ダサいからナシでしょ!」って断ったらしいんですよ。今みたいにネットのない時代だから、それを知った人は「なんてカッコいい!」と口々にそれを伝言して、つい最近になって話題になった。でも、今はネットだと1公演が終わってすぐ、誰かがセットリストをネットに上げていて、90年代と今では伝播の速度も含め、価値観が全く違うことを痛感させられます。僕ら、武道館で「バイタルサイン」をやった時、ピアノの音が止まったのに、お客さんは事故としてとらえず、何のネガティブなトピックにもならなかったんですよ。そういう意味でとらえると、例えばセカオワだって新曲の方向性をことあるごとに大きく変えていて、腹を括って一種の事件性を真面目にもたらしているのかと思いました。
柴:ライブだと日産スタジアム公演で、電車が空を走ってメンバーが降りてくる、なんて演出もありましたね。
ミト:モトリー・クルーのドラムが回ったくらいで騒いでいたわれわれは何だったんだろう(笑)。そういう風に予想と想像、自分たちの知覚を飛び越えるものと、「音」という、どこでも鳴らすことができるものにもっと注力するようになったんだよね。
金子:今年、数々のミュージシャンを取材したなかで、その意識が数年前と比べて非常に高いレベルにまで達していると感じました。
ミト:僕は筋トレが大変だと思う人間ではないので、むしろこれくらいの熱量感で生きていけるなら、ようやっとミュージシャンとして生きていてよかったと思いますよ。みんなで揃って飲んでいても、家帰ってから「やべぇあいつに負けたくねぇ」って打ち込んだりするいまが理想的で。それに対してリタイアしてしまう人は、残念ながら向いていなかったとしかいえない。