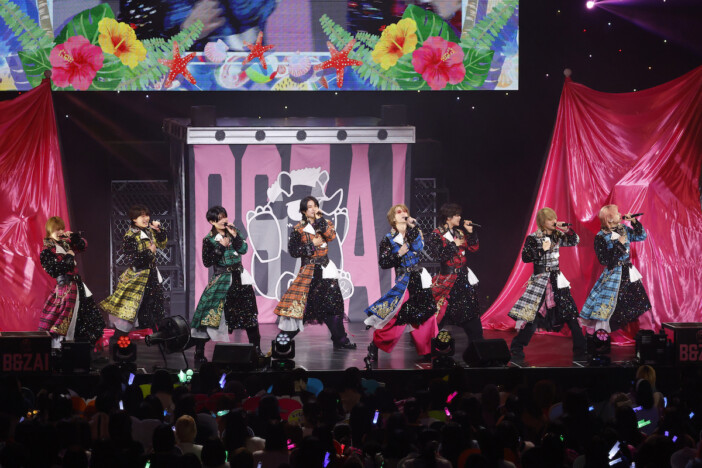市川哲史の「すべての音楽はリスナーのもの」第26回
レベッカが“国産ロック”にもたらしたもの 市川哲史が再結成ライブから振り返る
「『私マドンナみたいになりたい♡』っていう――短絡的でしょ、そっくりなこの曲。もう汚点だわ私、一生の。あははは」
「汚点と言っちゃうと当時聴いてくれた人に申し訳ないんだけど、そうねー……バンドとしてはどうなのかなー。一般的に認められてる部分は、ハッキリ言って褒められたもんじゃなかったと思うよ。だってやっぱり、パクリのフレーズ沢山あったしさー」
あははは。レベッカ解散後、NOKKOは「ラブイズCash」パクリ疑惑をあっけらかんと、こう肯定してくれた。男前だなぁ。
それでも、あのマドンナもどきの怪曲が彼女にとって実はどれだけ大きい意味を持っていたのか、私は徐々に知ることになる。
86年春に代理店を退社すると、主にタウン誌『ほっちぽっち』編集長と人気TV番組『5時SATマガジン』放送作家を始めた。偶然にも両者とも台頭しつつある日本のロックに積極的かつ意欲的なメディアだったので、否応なしに邦楽に接する機会が激増していく。
その過程で私はレッド・ウォーリアーズというバタくさいロックンロール・バンドと出逢い、バンマスの木暮武彦が元レベッカのバンマスであり、しかもNOKKOの元彼氏だったことを知る。
ここではバンドブーム史上に残るファンタジックな二人のラヴストーリーの詳細に触れないが、彼氏を棄ててバンドを採ったNOKKOの苦渋の選択はかの『金色夜叉』をも凌ぐドラマツルギーが、レベッカの説得力を倍増した。
「パクってようとなんだろうと、そういうのもどうでもよかったんだよね。なんかしんないけど演れさえすればねー。だけどなんて言うのかな……そうした原曲の威力を取り除いてもすごくパワフルなものが、自分でも感じられたのね。だから私は(それまでのロックなレベッカよりも)こっちの方がノレたし」
ロックバンド命の彼氏に洗脳されてロックな歌姫に徹してきたけれど、究極の二者択一を経て「自分が本当にやりたいこと」を探求する上で、身体を張った助走がたまたま<マドンナもどき>だったのかもしれない。
そう思うと「ラブイズCash」は、えらく切実なパクリではないか。
そう思うと「フレンズ」は、心を鬼にして袂を分かった同志への<届かないラブレター>にしか聴こえないではないか。
やがて『ロッキング・オン・ジャパン』の創刊とともに、私と日本のロックの関係性は加速度的に濃くなっていく。情報量が圧倒的に少なかったからこそ、洋楽ロックは我々リスナーの妄想力をかき立ててくれた。古井戸の見えない底をずーっと覗きこんでるのは、とても愉しい。しかし国産ロックは国産ロックで、方法論自体がまだまだ未成熟で底が透けて見えてたとしても、表現者の心情や心根が直接聴こえてくるのだ。極端な話、いつでも直接問いかけられる。これもまた愉しいことに気がついた。
日本のロックも悪くないな――そして私は寸暇を惜しんで、日本人ミュージシャンたちととにかく<なにか>を共有するようになった。
そんな自分の原点を、レベッカがひさしぶりに想い出させてくれたみたいだ。
■市川哲史(音楽評論家)
1961年岡山生まれ。大学在学中より現在まで「ロッキング・オン」「ロッキング・オンJAPAN」「音楽と人」「オリコンスタイル」「日経エンタテインメント」などの雑誌を主戦場に文筆活動を展開。最新刊は『誰も教えてくれなかった本当のポップ・ミュージック論』(シンコーミュージック刊)