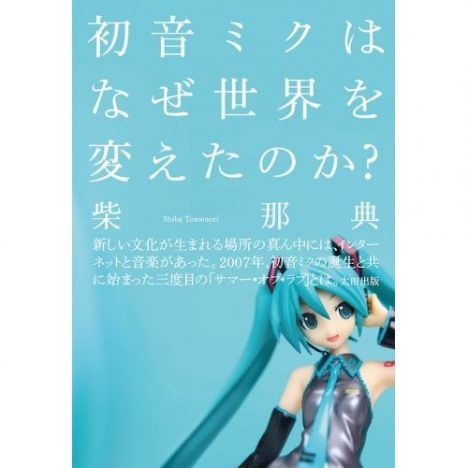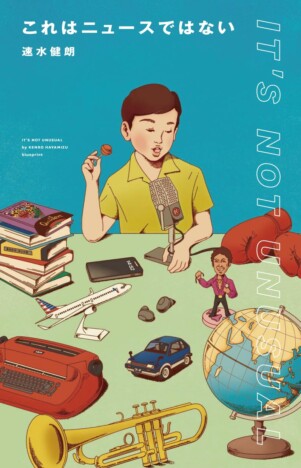『ポスト「J-POP」の時代——激変する音楽地図とクリエイションのゆくえ』一部を紹介
水野良樹×kz×柴那典×宇野常寛の「J-POPの現在と未来」徹底討議 フルバージョンが電子書籍化
共感から参加へ
水野:もう一つは、インターネットが登場したことで、人々が「共感」だけじゃなく「参加」という回路を持ち始めたことがあると思います。
今まで聴くだけだった人たちが、ニコニコ動画でコメントをしたり、あるいは音楽にあわせて絵を公開するようになった。プレイヤーとしての新しい楽しみが生まれて、共感の回路だけでは満足できなくなった。それだけじゃ詰まらなくなってしまった。それも大きいんじゃないかと思います。
kz:90年代の終わりから00年代の初頭に、GOING STEADYさんやモンゴル800さんたちをはじめとする、インディーロックや青春パンクのブームがありましたよね。
彼らはスターという立場じゃなく、聴き手に近い人たちが活躍していた。その延長線上にあるのがAKB48だと思うんです。「自分たちでもなれるかもしれない」と思わせる。いわばそれも参加型の回路の一つですよね。
そういう風に、スターに対して憧れの視線で見上げるのではなく、自分と重なる存在じゃないと響かないようになってきた。そうすると、必然的に細分化されていくわけですよね。共感を抱く対象が狭くなっていく。そのことがあるんじゃないかと思います。
柴:共感から参加へと、ポップスのあり方が変化してきたことが大きい。
kz:そうですね。そのことは、インターネットの登場以前から僕は感じていて。消費の仕方が変わったというのがあると思います。
それこそ、ケータイ一つ持っていたら、感情を誰かと共有できるわけですよね。そういうツールの発達は一番デカいんじゃないかと思うんですよね。
宇野:今、kzさんは共感から参加へという変化がインターネット以前からあったという話をしましたよね。それはすごく重要な指摘だと思います。
音楽がレコードなどのソフトで流通するようになってから、アーティストの物語と深く結び付くようになった。そのときすでにキャラクターミュージック化が始まっていた。そしてそうなると、共感よりも参加の回路が強くなっていく。単に歌詞に共感するより自分が参加し、アーティストに関わりをもつことのほうが音楽を消費する動機としては強いわけですからね。
音楽産業がアーティストを全面に押し出す形式をとった瞬間に、つまりキャラクターミュージックに舵を切った瞬間に、いずれ音楽が必然的にコミュニティミュージックになっていくという流れが始まったということだと思うんです。そうすると、それを超えるにはどうしたらいいのかという問題が浮上しますね。
(中略)
オリンピックのテーマ曲はどう機能したか
宇野:ただ、そこで思うのは、単にオリコンのチャートが機能していないだけなのか、社会全体が興味ある曲、みんなが聴いている曲というのが、果たして存在するのか?という話だと思うんです。
たとえば、変な話、僕はロンドンオリンピックを一秒も見てないんです。ニュース番組も一切見ない。「今でしょ!」っていう流行語も最近まで知らなかった。
そこで、柴さんが言っているのは、単にランキングが機能しなくなったのか、それともメジャーなものが存在し得ないような社会の在り方に変わったのかという問題が出てきますよね。僕は後者だと思いますが。
柴:そこで言うなら、まさに水野さんはロンドンオリンピックの放送テーマ曲を書いたわけですよね? あの時にどういうことを考えました?
水野:ロンドンオリンピックの放送テーマソングを作ろうと思ったときは、確かにオリンピックを観ない人もいるだろうなということは考えましたね。今までは「オリンピックが来た、みんなで応援しよう!」という空気を共有できたと思うんです。
でも、今はいくつものコミュニティもある。興味ない人もいるし、応援する気になれない人も、それこそ東北には沢山いた。
そういう、バラバラな状態がある中で行われるオリンピックだったと思うんです。そういう時に「心をひとつにしよう、みんなで頑張ろう」といったことを歌っても絶対に届かないと思ったんです。
そこで、みんながバラバラであるけども、同じ時間軸にいるし、同じ社会にいるという状況を書いたのが「風が吹いている」だったんです。
だから、あの曲の冒頭では「風が吹いている」という情景描写しか歌っていないんですね。本当は感情を描写する言葉を冒頭にいれるのがポップスの常套手段なんですが、それでは意味がないと思った。
ただそこに場があって、それぞれの人は全然違う方向を見ているかもしれないけど、そういう人たちが一緒の場にいるということを書こうと思って、あの曲を書いたんです。
宇野:その話は非常に興味深いですね。というのも、そこにドリカムと西野カナの違いを重ねあわせて語ることができる。
90年代にドリカムの吉田さんが歌っていたのは、いわゆるバブルのころの都市部に住む一般職の女性のリアリティなんですよね。それが当時のいわゆるF1層と呼ばれる人たちの心にヒットして、そこを中心に周縁に広がってメガヒットに繋がっていった。
今、同じF1層をつかんでいるのは西野カナさんだと思うんですよ。でも彼女の音楽は本当に特定の層の女性にしか聴かれていないと思うんですね。ここに大きな差がある。つまり、これがかつてJ-POPが象徴していた社会そのものの変化がある。要するに、流行の発信源として「都市部のF1層」が機能しなくなっている。少し住んでいる場所や階層がズレただけで「そんな都市部の一般職OLのリアリティなんて聞かされても私には関係ない」と思われてしまう。
それに対して、いま水野さんが話していたのは、特定の人間を主人公にしてシーンを描くみたいなことはやらないほうがいい、ということなんでしょうか?
水野:やらないほうがいいというか、僕はその手段は取れなかったということですね。
柴:kzさんはどうですか? kzさんもオリンピックのような大きなテーマに対しての曲を書くタイプのクリエイターだと思うんですけれども。
kz:Google chromeのCM曲『Tell Your World』は、僕にとってのオリンピックのテーマ曲のようなものだったと思います。あれ自体、オリンピックと近いテーマなんですね。誰が主人公でもないし、そもそもインターネットカルチャーという特定の登場人物のないものだったので。そこで描いたのも事実描写はないし、誰かが誰かに届けるというものではなく、事象そのものを歌った曲だった。
壮大なテーマになればなるほど、個人の人生は曲のスケールを矮小化してしまう。そういうところで邪魔になるんですね。そういった意味でGoogleがボーカロイドというテーマを扱ったのは正しいなと思いました。
「風が吹いている」の冒頭が情景描写になったというのと、それと同じことだと思います。そういう、「場」や「状況」に対しての曲が増えてきたというのはゼロ年代的テーマだと思います。インターネットや、コミュニティのツールが発達してきたからこそ、事象に対して歌える曲も増えてきたのかな、と。