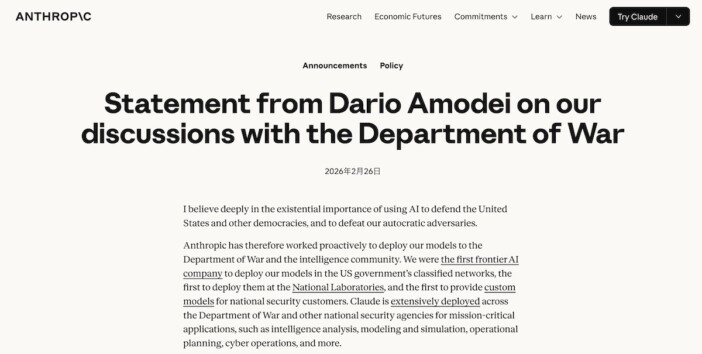遊び心満載のゲーム性と、“PlayStationの顔”になり得るポテンシャル 『アストロボット』先行体験レポート

みなさんはこの青×白の配色と可愛いデザインが特徴の“ASTRO(アストロ)”というキャラクターを知っているだろうか。

知っている、と答えた方の9割以上は、おそらくPlayStation 4もしくは5、またはPSVRのユーザーだろう。それもそのはず、このキャラクターはそれぞれのハードウェアの操作を説明するためのプリインストールソフトに登場するからだ。そんなアストロが、プリインストールソフトを飛び出し、このたび1本のアクションゲームとして9月6日にリリースされることになった。その名も『アストロボット』だ。
このたび先行体験の機会をいただき、実際に『アストロボット』をプレイしてみた。結論からいうと、3Dアクションゲームとしてかなりの出来だと感じた。操作はわかりやすくて直感的で進行のテンポもよく、アクションのバリエーションは多くて難易度もちょうどいい。これはPlayStation 5の『Astro’s Playroom』とも共通するが、DualSenseの触覚フィードバックがこれでもかというくらいに活かされている。水の中に入ればブクブク感が、磁石を持てば金属が張り付いてくる感覚が、氷やガラスの上を歩けばパリパリとしたフィーリングが得られ、ゲーム初心者にも上級者にも“ゲームの楽しさ”を教えてくれる。序盤のステージは都度セーブポイントがあるが、難しいステージは一筆書きのようにスタートからゴールまで辿り着く必要があり、これもまた“気持ちのいい難しさ”を覚えた。

体験会場には、そんな同タイトルを手がけるTeam ASOBIのドゥセ・ニコラ氏も出席しており、リアルサウンドテックも合同インタビューの機会を得ることができた。

ニコラ氏は『Astro’s Playroom』の開発時から「もしこのゲームが上手くいったら、アストロを主人公としたもっと大きなゲームを作るつもりだった」そうで、3年の歳月をかけて開発したという。先述した触覚フィードバックを活かした体験については「水の中に生えている葉っぱの1枚1枚にハプティクスがあるし、壁に触っていても素材が変わるたびにテクスチャも変わる」とかなり細かく設計していることを明かした。
開発で大変だったことはなにか、と聞くと「テンポ」と真っ先に挙げたニコラ氏。その理由については「ユーザーはジャンプアクションゲームをプレイするとき、知らずのうちに『ジャンプ→ジャンプ→ジャンプ→コイン→コイン→パンチ』などの一連の動きにテンポを感じるのですが、それが気持ちいいかどうかがすごく大事なんです」と答えた。これは『Astro’s Playroom』と『アストロボット』の規模感にも影響を受けており「小さなゲームだと全体のテンポの移り変わりを設計するのは簡単なのですが、大きな規模のゲームになると、そのコントロールがとても難しい。作り手側としては20〜30時間の長さのゲームよりも、12〜15時間でも良いテンポをキープしながら進むゲームのほうが良い体験になると感じました」と、3Dアクションゲームを一つのタイトルとして作ることの難しさを教えてくれた。

また、同作は小さなロボット「ボット」たちが宇宙の各地に散らばってしまい、さまざまな星を巡って彼らを助けていくというストーリーなのだが、そこには筆者が体験しただけでも『パラッパラッパー』のパラッパや、『ラチェット&クランク』のラチェットなど、プレイステーションの30年にわたる歴史のなかで誕生した約150種類のカメオキャラクターが登場する。そのことについてニコラ氏は「助けたボットは一つの惑星に集結していくのですが、ゲームの途中でミュージアム的に見ることもできるんです」とコメント。それぞれのキャラクターのアニメーションについても「たとえば『ゴッド・オブ・ウォー』のクレイトスだと怒っている感じが出ていたりと、元々のゲームの内容にカートゥーンっぽさを混ぜています」と、細部にわたるこだわりについて話してくれた。
筆者はこのゲームをプレイして、子どもでも気軽にプレイできるゲーム性はPlayStationの入口として存分に機能すると確信したし、「アストロ」自体がIPとして大きな可能性を秘めていると思った。そのことについてぶつけると「これからの“PlayStationの顔”になってもらいたいと考えていて、グッズ化もしている」と今後に期待が持てる回答をしてくれた。

先述した子どもがプレイするタイトルとしての可能性については「最初にプレイしたゲームには特別な思い出があると思いますし、そこに対する責任がある。ただ、子どもたちだけを対象にするのではなく、大人にもプレイしてほしいし、パラッパやラチェットのように子どもたちの世代は知らないが、大人は知っているキャラクターを出すことで、会話のきっかけになったり、それぞれの世代を繋ぐブリッジとして機能することも期待している」と、親子世代のコミュニケーションツールとしてゲームが果たす役割の一端を担うタイトルにしていく気概を感じた。
かわいすぎる「アストロ」のデザインについて話が及ぶと、ニコラ氏は「ポイントはシンプルな形であること。特に目の部分は大事だと考えていて、子どもでも描きやすいような単純さと可愛さを意識しました。あとはお尻ですね。赤ちゃんっぽさを出すために、おむつを履いているような膨らみの感じを出しました」と、どこか“守ってあげたい”存在としてのかわいさを初期から意図的に演出していたことを明かした。

最後に、ジャンプアクションゲームとして知っておきたい“やりこめる要素”について聞くと、ニコラ氏は「触覚フィードバックにさまざまな仕掛けがしてあります。基本的にはボットを探してゴールを目指すゲームですが、たとえば水の中に入って、水がスパイラルしているところで生えている木にアタックすると特別なアクションが起こったりと、普通にプレイしていれば1000人に1人しか気づかないような要素をたくさん入れました。なので、ぜひ“おもちゃ”としてプレイしてみてください」といたずらに笑いながら答えてくれた。
シンプルでゲームとしても楽しめる一作でありながら、さりげないこだわりを詰め込んでハードとしての可能性も追求するーーまさに開発を手がけたチームの名前を冠したような“遊び心”が凝縮された『アストロボット』。この記事を見て興味を持った方は、ぜひ発売日を楽しみにしていてほしい。
PC接続解禁で、『PS VR2』は“息を吹き返す”のか? 既存デバイスとの比較や可能性を考える
6月3日、『PlayStation VR2』(PS VR2)がPCでも使用可能となることが、突如アナウンスされた。8月7日に発売…