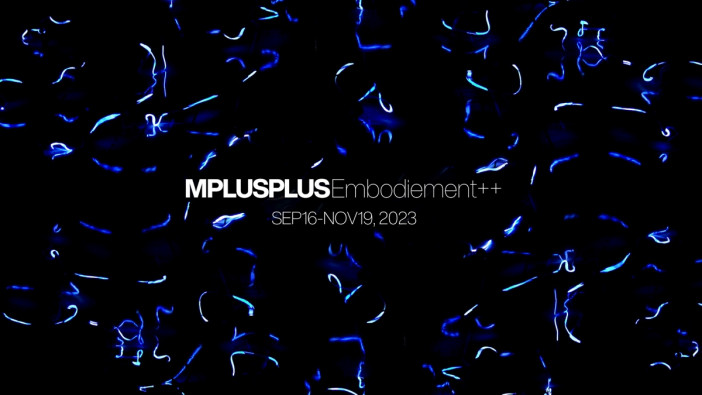連載:mplusplus・藤本実「光の演出論」(第五回)
極限まで光を減らし、シンプルなロボットの動きで“原理”を見せる 『Embodiment++』で藤本実が向き合った原点

プロダクト展では104,000粒のLEDが光り、パフォーマンスでは3作品で“2粒”しか光らない
――今回の展示はキャッチーなはずの光やLEDの存在をあえて制限しているのが面白いと思いました。
藤本:プロダクト展の方では104,000粒のLEDを使って光らせているんですが、こっちは3作品で2粒しか光らないんですよ(笑)。
それは「MPLUSPLUSはアートもやっている」というのを説明するための展示だったからでもあって。そもそも自分のテーマは「動き」であって、その目的のために「光」を使っているんです。これまでライブエンタメでいろんなものを光らせてきたので、外からみたら「光らせたい人」だと思われているかもしれませんけど、そうじゃない。光はあくまでも「動きを表現する一番わかりやすい方法」にすぎないんです。
――光は視覚的にわかりやすいですよね。『Vitality of LightーLight-emitting Existence』は直訳すると「光が発する存在感」という意味になりますが、これは『Humanized Light』ともある種共通するポイントがありそうです。
藤本:そうなんです。分かりやすくというだけだったんで、今回は動的な動きのあるものをどう作り出すかをテーマにして、人間の速度の限界を超える『Unknown RhythmsーHumanized Clock』、ダイナミックスと滑らかさで人間を超える『Morphing Elegance ーRobotic Choreographer』、デジタルにも存在感や気配が出せる『Vitality of LightーLight-emitting Existence』の3つを展示したんです。
『Vitality of LightーLight-emitting Existence』に関していうと、ゾーンに入ったダンサーが歩いてるだけでめちゃくちゃかっこいいと思った経験はありませんか? 僕、そういった存在感の出し方や気配みたいなものは結構存在すると思っているんです。
今回は、それがデジタルにも出せるのかなというのに挑戦したということです。前に「足」の作品(『Pixel Beings -Bboy-』)を出したときもそうなんですけど、映像が平面ではなく人間というフォルムを持ったら存在感や気配を出せる。『Humanized Light』だって、ただの光の線なのに、ちょっと揺らすだけで存在感が出る。そういうことに挑戦してきました。以前は4つの線だったのが、いまは1粒でそれに挑戦しているので、どんどん削ぎ落されてきたなと感じます。
――『Humanized Light』のときのように、あの大きさとあの仕掛けでないと見えないものもあれば、『Vitality of LightーLight-emitting Existence』のように制約を設けたからこそ見えるものも。ある種「対極的な振り幅」を作ったことは藤本さんにとっても大きかったのではないでしょうか。
藤本:そうですね。この10年間、自分の作家性を出すには「人を使わないといけない」と思っていたんです。声がかかってても、2ヶ月間毎日人が行くのは無理なのでと断ったりもしていました。でも、人がいなくてもいいんだということを、10年目にして『Humanized Light』が気付かせてくれたんです。そうしたら、何でも作れるなと目の前が開けたし、またそんな機会がもらえたらいいなと思っていました。そこで今回、CCBTからお声がけいただいたので、今回の新作は意地でも人を使わないようにしようと。
――『Humanized Light』より前はボトムアップというか、人間という制約のある身体をどう拡張していくかという考えがあったと思うんですけど、今回の作品は逆に人間ではないものを使って“人間の可能性を引き出す”という方向に考え方が大きく変わりましたよね。
藤本:そうですね。それができるということにやっと気が付きました。自分が今回伝えたかったのはキャッチコピーにもある「身体性を私たちは受け止め、かつ越えることができるのか」ということで。
これまで、「テクノロジーによる身体性」とは「どう人間に近づけるか」ということだったと思うんです。ヒューマノイドロボットなども、人間の顔や構造にどれだけ近づけるか、人間の腕をどれだけ模せるかといった発想で研究が進んできました。でも、そうじゃなくて、速度やダイナミクスなど人間を構成する一つの要素に絞れば、人間を越えることもできるのではないかと思ったんです。最初に作ったロボットでは要素を入れすぎて逆に越えられなかったんですが、要素を絞ってやっていこうとしたのが今回でした。
――先程のケンモチさんの曲の話にも繋がりますが、音楽もリズムマシンの登場によってビートの概念が変わり、人間が叩けないものが生まれました。けれど、実際にはその10年後や20年後にそれを叩けるドラマーが出てきたりもして、そこからジャズの拡張などに繋がっていったという歴史もあります。そういった、テクノロジーによって人間の可能性が拡張されるというのは、藤本さんの考えと近い気がします。
藤本:多分昔の人って、そんなに速いビートが音楽になるとは思っていなかったんですよ。でも、1回その音楽を聞くと、「早くてもリズムって作れるんだ」と気付きを得て、それに挑戦する人が出てくる。
人間ってイメージできないとできないんですよね。ダンスにウィンドミルという動きがあるんですけど、あれはどの順番で身体が床についてねじれるのかがイメージできないと、実際にその動きを再現することはできないと言われているんです。そういうのが体操やダンスの世界には結構あって。自分の中ではそれが原点になっているんです。
そこへ来て、今回の時計は針の長さが腕や足の長さよりも少し長いくらいなんです。なので「あいつができるなら」というところから、同じ長さなのだから自分にもできるかもしれないという人が現れるかもしれない。実際、作品を観た子どもは見た後に動きを模倣しようと動いていましたから。
ロボットはアームが2本あるので、片方が滑らかに動いてるのに、片方は震えてるということもできます。ですが、人間が四角と三角を片手ずつ同時に描くのが難しいように、違うことを同時にするのって難しくて。手足どちらかが三拍子でどちらかが四拍子という風に分けてダンスをするのって、結構難しいんです。でも、その見本を提示したら、「ひょっとしたらこんなことができるかもしれない」というイメージが湧くので、やる人が出てくるかもしれませんよね。
――そういった音楽的・ダンス的なアプローチも、藤本さんのこれまでやこの後に欠かせないものとなっていきそうです。