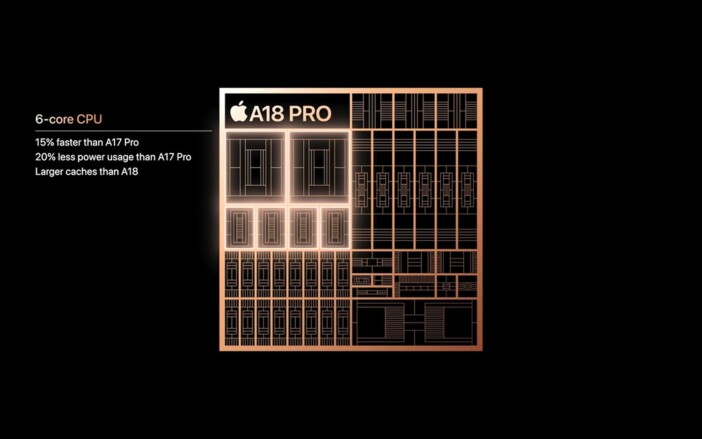映画『フリー・ガイ』に込められた“ビデオゲームへの愛” 「とあるアイテム」を巡る見事な仕掛けとは?

2013年にサービスを開始し、今なお愛され続けるオンラインゲームである『グランド・セフト・オート:オンライン』。広大なロスサントスという架空の世界を舞台としたオープンワールドに世界中の様々なプレイヤーが集まり、法律やモラルを気にすることなく様々なミッションを楽しむことができる。
なかでも人気なのが「強盗」ミッションで、武器や移動手段を入念に揃えたプレイヤー同士が集まり、数百万ドルもの大金を強奪するために銀行の支店を襲撃する。本稿を書いている今も、NPCとしてロスサントス(実際には世界中のサーバの中)で生活している銀行員たちがプレイヤーの襲撃に悲鳴をあげていることだろう。だが、彼らは決してゲーム内に存在するお金の管理をしているわけではない。彼らは、プレイヤーに襲われるために目覚め、出勤し、職場で待ち、実際にやってきたプレイヤーを目の当たりにして悲鳴を上げ、被害に遭い、帰宅する。これを永遠に繰り返す。それこそが彼らに割り当てられた役割であり、仕事なのである。身も蓋もない言い方をすれば、彼らはプレイヤー側の体験をよりリアルに、かつ楽しいものにするためだけに生きている。
先日公開された映画『フリー・ガイ』は、極端に言えば「もし、その銀行員が自我を持ち、自分の意志で行動を始めたとしたら?」という疑問を形にした作品である。本作の舞台であると同時に作中のゲームの名称でもある「フリー・シティ」は、都市を舞台としたオープンワールドであり、ゲームのプレイヤーはその世界で車を強奪したり、銃やミサイルを乱射したりと自由に暴れまわることができる。王道タイプからシュールなものまで様々なスキンを身に纏うこともできるし、『ロックマン』に登場するロックバスターのような既存のIPのアイテムを使うことも可能だ。そんな「フリー・シティ」において、本作の主人公であるガイ(ライアン・レイノルズ)は、冒頭で書いたような「こういうタイプのゲームにおける銀行員」としてのルーティンを疑うことなく繰り返し続けている。だが、ある女性との出会いをきっかけに、彼はNPCとしての存在を脱却し、自らの理想へと向けて突き進むようになり、その行動はゲームの外側である現実世界にも大きな影響を与えていく。
ビデオゲーム的な表現に固執せず、違和感を活かした普遍的なコメディ

『フリー・ガイ』のようなビデオゲームを題材とした映画は、ゲーマーの注目を浴びるからだろうか、ある程度話題になりやすい側面がある。一方で、それが映画として評価されるかというと、(もちろん例外はあるが)残念ながらそういうわけにもいかなかったりする。おそらく、その原因の一つとしては、元々ビデオゲームだからこそ成立していた表現を、映画という異なるフォーマットへ持ち込んだ時に生まれる違和感がそのまま残ってしまっていたり、あるいは無理矢理変換したことでかえって奇妙に感じられてしまうことが挙げられるのではないだろうか。映画の中で主人公の目の前に突然「LEVEL UP」という文字が浮かび上がったり、そこら中に弾薬や回復アイテムが落ちていたら違和感があるだろうし、逆にゲームでは慣れ親しんでいたはずの武器を実写で再現すると奇妙に感じてしまう、といった具合に。
『フリー・ガイ』はそういったビデオゲーム的表現による滑稽さを、むしろ効果的に表現として機能させることに成功している。もっとも象徴的なのは「サングラス」の存在だろう。本作では「フィールド上のアイテムやHUDに映っているはずのUI要素はプレイヤー側が着用しているサングラスのみに見えており、NPC側は『サングラスはサングラス族(NPC側から見たプレイヤーの通称)しか着用してはならない』という教えを守っているため、それらに気付くことなく生活している」という設定を導入することで強引に解決してしまったのだ。
この設定の導入によって、普段の主人公のシーンはあくまでフリー・シティを舞台とした現実的なものになり、サングラスを着用してプレイヤー側の能力を手に入れたシーンでのみ、自分のレベルが分かったり、自由に様々な武器を取り出したり、道に落ちている回復薬を見つけて体力回復したりといった“ビデオゲーム的な表現”が描かれるつくりとなっており、映画全体を通して「NPC側とプレイヤー側の視点の違い」がはっきりと分けて描かれているのである。また、これは物語全体における「プレイヤー(人間)≒自由で支配的な存在」/「NPC(AI)≒不自由で従属的な存在」という対称的な構造を強調する機能としても働いている。ビデオゲーム的な表現を活用することで作品の本質的なテーマをより浮き彫りにしているのだ。
この「サングラス」の存在が象徴する通り、本作には様々な既存のビデオゲームを参照したと思われるシーンが取り入れられているものの、その多くは映画という手法にビデオゲーム的表現を取り入れることで生まれる違和感自体を、ユーモアとして的確に捉えた上で作っているように感じることができる。また、プレイヤーが執拗にアピールする『フォートナイト』を想起させるエモートや、背後にいる人物が(主にFPSの対戦ゲームで見られる)倒した相手に煽り屈伸をする場面など、パロディに関してもゲーマーにしか分からないような(あるいはゲーマーが頭を抱えるような)安易なものではなく、シーン自体が単純にコミカルであり、元ネタを知っているとなお面白いという塩梅にうまく調整されている。
また、そもそも本作のコメディとしてのベースとなっているのは、毎日銀行強盗の被害に遭いながらも底抜けに明るいガイの存在そのものであり、彼の振る舞いや言葉の一つひとつが本作を魅力的にしているのだ。だからこそ、観ていて違和感を感じたり、寒々しい気持ちになったり、内輪ウケに走ってしまったような痛々しさを感じたり、といった場面が本作にはほとんどどないのである(また、現実側で登場するアントワン(タイカ・ワイティティ)のあまりにも強烈なキャラクターがさらにその魅力をブーストさせてくれる)。本作は事前のプロモーション(『スーパーマリオ64』や『Among Us』といった新旧の名作ゲームのパロディポスター)を踏まえると、意外にも直接的なパロディの量は控え目に感じられるのだが、その背景には深いビデオゲームへの理解があり、その上で本作を構築しているのだということを感じることができる。