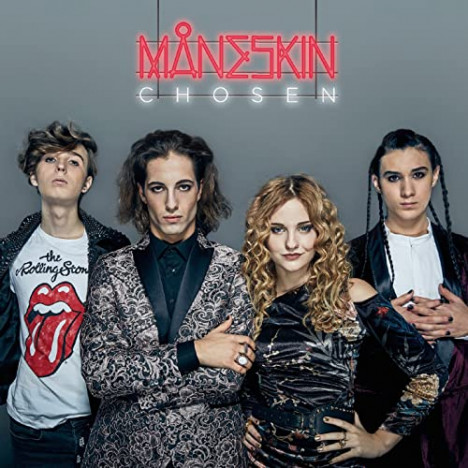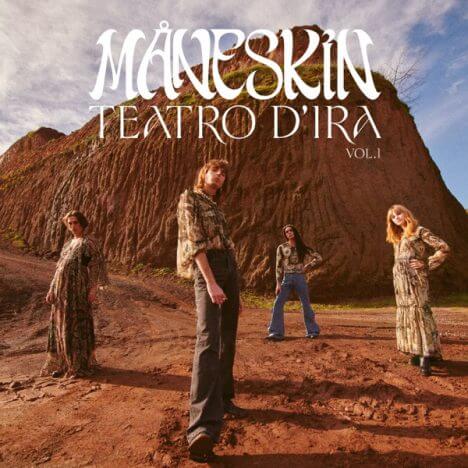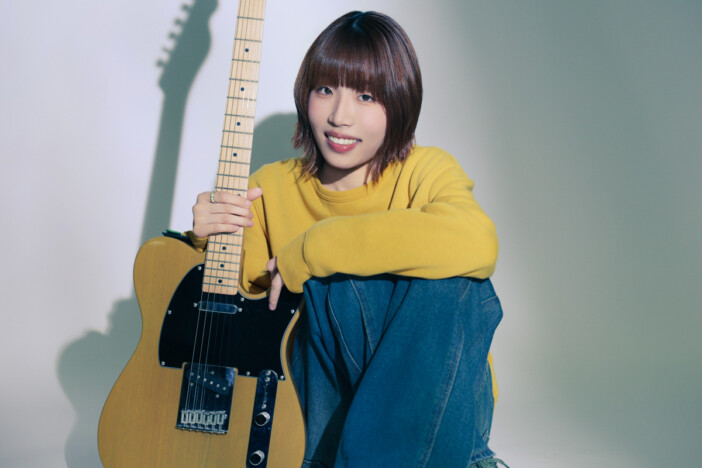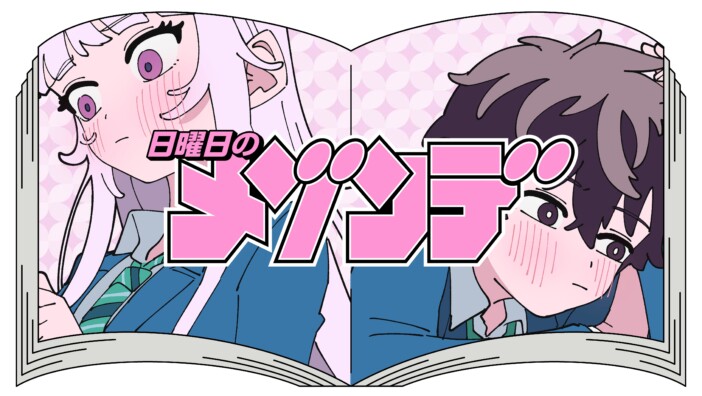【特集】グローバルを取り巻く“ロック”の再評価
Måneskinのロックサウンドが世界に受容された理由 ソニー・ミュージック洋楽担当に聞く、日本市場における洋楽の希望と課題

『ユーロヴィジョン・ソング・コンテスト2021』で優勝を収め、TikTokをきっかけに爆発的なグローバルヒットを記録したMåneskin。フロントマンのダミアーノ・デイビットは、その授賞式で「ヨーロッパ全土へ、そして世界へ俺たちは伝えたい。ロックンロールは永遠に不滅だ!」とコメントしたというが、今まさにUKを筆頭としたヨーロッパ圏におけるロックバンドの隆盛、US圏で顕著なヒップホップやポップミュージックとロックのクロスオーバーなど、世界的に面白い動きが生まれている。
グローバルなチャートやヒットソングといったメインストリームからロックというジャンルが影を潜めて久しいが、またここ数年で徐々に存在感を増してきた背景にはどんな要因があるのだろうか。ザ・キッド・ラロイなど若手アーティストを輩出する株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ<ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル>の黒木美和氏に、グローバルミュージックの潮流、TikTokやサブスクにおける洋楽の聴かれ方の変化、ロックの現在について話を聞いた。(編集部)
本来の意味での「ミクスチャー」が進んだ感じがある
ーーまずはここ15年くらいの洋楽シーンの動向について、黒木さんの見解をお聞かせいただけますか?
黒木美和(以下、黒木):15年前というと2006年ですか。その頃はまだロックにも例えばレッチリ(Red Hot Chili Peppers)が<ワーナーミュージック>から『Stadium Arcadium』をリリースした年ですし、翌年にはMaroon 5が2ndアルバム『It Won't Be Soon Before Long』を<ユニバーサル ミュージック>から出しています。Coldplayが『Viva la Vida or Death and All His Friends』を出したのも2008年だから、その頃はまだロックが何十万単位という規模でアルバムを売っていました。
同時に、その頃から徐々にストリーミングサービスが台頭してきます。日本国内では2015年にApple MusicやGoogle Play Music、2016年にSpotifyがサービスを開始して、シーンの様相がかなり変わりましたよね。『ULTRA JAPAN』が2014年に初めて日本で開催されると、EDMがあっという間に席巻しました。EDMは「エレクトロニック・ダンス・ミュージック」の略で、そのまんまの名前だなと当時は思いましたけど(笑)、私たちの世代だとデジタルロックなんて言われていた音楽に近いのかなと。
ーー実際、スクリレックスなどのスタイルやアティチュードは「ロックスター」のそれでしたよね。
黒木:そうですね。それが落ち着くと、R&Bやヒップホップなどと融合しながらサウンドが変化していきます。それが2018年くらいまで続くのかな、2019年にはEDMの波もだいぶ収束してきて。R&BもヒップホップもEDMも混じり合ったサウンドが、今度は「ラテン」を取り入れるなどしていきます。そういう大きな潮流に、ロックというジャンルは今ひとつ乗り切れずどんどん聴かれなくなってしまう状況が、つい最近まで続いていました。それが、ここ1、2年で再び息を吹き返している印象ですね。カルチャー的にも1990年代のロックアーティスト、例えばNirvanaのTシャツをヒップホップのアーティストが着たりとか、サウンド的にも1990年代のロックをサンプリングしていたりとか、そういうジャンルの勾配も進んだことが大きかったのだと思います。
ーーカニエ・ウェストがMy Bloody ValentineのビンテージTシャツを着て話題になったりもしましたし、1990年代再評価の流れは大きいですよね。
黒木:サウンド面でいうと、思えば1990年代もミクスチャー系のバンドが多かったじゃないですか。Limp Bizkitとか、のちにジェイ・ZとコラボするLinkin Parkとか。当時は白人のロックバンドが、主に中心となってブラックミュージックのエッセンスを取り入れていたようなところもありましたが、今は黒人のヒップホップアーティストの方からロックバンドに接近していくなど、双方からの歩み寄りによって本来の意味での「ミクスチャー」が進んだ感じがありますよね。なぜそうなったのかというと、それこそ「多様性」という考え方がここ数年でちゃんと根付き、若いアーティストやリスナーの間で自然に起きていることなのかなと思います。
ーーそれはやっぱり、YouTubeやストリーミングサービスなどで、古今東西の音楽を等価で聴かれるようになったのも大きいでしょうね。
黒木:それは間違いないですね。YouTubeやストリーミングサービスで音楽を聴くと、自分の知らなかったジャンルへ飛びやすい。1990年代だとDJカルチャーで起きていたことが、もっとオープンになったというか。「あのレコード屋まで行かないと、あの音源は手に入らない」みたいなカルチャーではなくなり、ストリーミングで誰もがいろんなジャンルの音楽にアクセスできるようになった。それこそSoundCloudなどの存在も大きいですよね。リスニングスタイルの変化は、音楽の作り方にも大きく影響しているのだろうなと思っています。
ーーそういった土壌ができたからこそ、K-POPが世界中で聴かれるようになったとも言えます。
黒木:ストリーミング以前は考えられなかったことですよね。しかも、英語ではない楽曲まで世界的にヒットすることも起こり得るという。
ーー先ほどNirvanaの話が出ましたが、例えば2015年頃のエモラップ系アーティスト……ジュース・ワールドやポスト・マローンあたりはカート・コバーンが好きな人が多いですよね。
黒木:しかもジュース・ワールドやXXXテンタシオン、リル・ピープなどこの世を去ってしまったアーティストも多い。死因はオーバードーズや銃殺などそれぞれ違いますが、彼らが1990年代ロックの中でも、そうしたダークな要素に惹かれていたのは何故だったんでしょうね。
ーー彼らと年齢が近いビリー・アイリッシュもダークでエモーショナルな楽曲を作っていますが、いわゆるZ世代が纏っている厭世的なムードはカート・コバーンのそれともシンクロするというか。やはり同世代であるBTSが「Love Yourself」と自己肯定を訴えているのも、それだけ自己肯定できていない人が多いからでしょうし。
黒木:確かに。
ーー彼らはアメリカのアーティストですが、UKはどうでしょうか。最近はBlack Country, New RoadやShame、Fat White Familyなどサウス・ロンドンのシーンが盛り上がっていますが、彼らの受容のされ方についてはどのように見ていますか?
黒木:USと比べるとUKの方が、マーケットがコンパクトなぶんロックバンドに対してもシンパシーを覚えやすいのかもしれないですね。そういう意味では日本とも似た環境というか、ロックバンドの存在感も依然としてある。弊社の邦楽でいうと、King Gnuのようなバンドが出てきたりしますしね。
ーーちなみに今、ソニーで力を入れて取り組んでいるアーティストというと?
黒木:まずはザ・キッド・ラロイ。ジャスティン・ビーバーとのコラボ曲「Stay」は軒並みチャートにランクインされ、BTSを除けば今最も注目されている海外アーティストといえます。ただ、今のところ「Stay」がダントツで売れているので、今後どうやって彼自身の魅力を伝えて「ファン」を取り込んでいくか。それが目下の課題です。
それからリル・ナズ・Xは、数字的な部分でもザ・キッド・ラロイに次ぐ勢いがあります。ラロイも、それからドージャ・キャットもそうでしたが、やはりソーシャルメディアをいかに本人が使いこなしているかがかなり大きいと思いますね。コンテンツとしては、日本人の我々には思いつかないような、かなり刺激的な表現もたくさんあるのですが、そういう「これまで見たこともない新しいもの」を提供してくれるアーティストたちを、我々としても推していきたい。